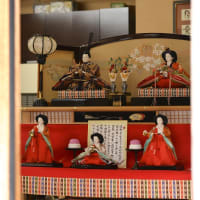~低炭素建築物とは?どんなメリットがあるの?~
 今、地球温暖化に対して温室効果ガスの排出量について全世界で問題視されており、それが住宅にも影響を及ぼしています。
今、地球温暖化に対して温室効果ガスの排出量について全世界で問題視されており、それが住宅にも影響を及ぼしています。
温暖化に対して温室効果ガスの排出量が低い住宅が求められ、平成24年12月4日に施工された「都市の低炭素化の促進に関する法律(エコまち法)」に基づいているのです。そこで、低炭素建築物とはどのようなものか、低炭素建築物の基準は何か、また、どのようなメリットがあるのか調べていくことにしましょう。
◎エコまち法による低炭素建築物とは
エコまち法とは、都市の低炭素化を図るために都市機能の集約化、公共交通機関の利用促進、建築物の低炭素化・緑・エネルギーの面的管理・利用の促進など低炭素な街づくりを目指す法律です。
エコまち法に定める低炭素建築物とは、建築物における生活や活動に伴って発生する二酸化炭素の排出えお抑制するため低炭素化に資する措置が講じられている、市街化区域等に建築される建築物を指します。
低炭素化に資する措置とは以下のことを指します。
(1) 省エネルギー基準を超える性能をもつこと、かつ低炭素化に資する措置を講じていること。
(2) 都市の低炭素化の促進に関する基本的な方針に照らし合わせて適切であること。
(3) 資金計画が適切なものであること。
またこれら(1)~(3)のすべてを満たした建築物について、所管行政庁(都道府県、市または区)に認定の申請を行うことにより、低炭素建築物として認定を受けることが可能となります。
◎低炭素住宅は市街化区域を中心に普及
市街化区域を中心に普及させる理由の一つとして、温室効果ガスの排出量を抑制するには、家屋が集中していない地域より、エネルギーを大量に使う都市部で、総合的に実施することにより効果が見込めるということです。
省エネルギーや二酸化炭素排出の抑制などを目的として、国としても市街化区域などにおいて住宅の低炭素化を推進しており、2020年度にはすべての新築住宅が新たな省エネ基準に合致するよう義務付けられていたのですが、2018年12月3日の国土交通省の部会(有識者会議)で、2020年から義務化が予定されていた「省エネ住宅の義務化」を撤回する方針案が了承されましたが、住宅以外の床面積300㎡~2000㎡の中規模建築物は省エネ適合率が91%(2017年度)で事業者も省エネ基準に習塾、新築件数も少なく行政の対応能力もあるなどとして、問題はないと判断され新たに義務化されることになります。
ところで一般住宅の義務化が見送られた理由には、小規模な住宅(戸建てなど)に限っては、義務化するとついていけないハウスメーカーや工務店、設計事務所があるためとされています。
しかし、「省エネ」「創エネ」「畜エネ」などを駆使して、「ゼロエネルギー住宅(ZEH)」を見据えており、2030年には新築住宅の平均でゼロエネルギー住宅を、2050年にはすべての住宅でゼロエネルギー住宅とする目標が示されています。
また、オフィスビルや商業施設など2000㎡以上の建築物を皮切りに、300㎡以上の建物、そして全ての戸建ての新築住宅と段階を追って義務化していってますが、商業施設などでは既に省エネ化を本格化してきています。
次回は、低炭素住宅の認定条件や基準についてお話をします。