風邪と漢方薬
風邪は、誰もがかかる病気で主にウイルスによって上気道(鼻やのど)に急性の炎症を起こす病気の総称をいいます。
 「風邪は万病のもと」といわれるように、こじらせると肺炎などの重い病気を引き起こすこともありますので、お年寄りや乳幼児、あるいは基礎疾患のある方は軽視することはできません。
「風邪は万病のもと」といわれるように、こじらせると肺炎などの重い病気を引き起こすこともありますので、お年寄りや乳幼児、あるいは基礎疾患のある方は軽視することはできません。風邪に使われる薬として西洋薬あり、のどの痛みや鼻水、鼻づまりなどを改善する対処療法によって症状を緩和します。
今回は風邪の対処方法して漢方薬について考えています。
漢方薬の役割
西洋薬と違い漢方薬は体全体のバランスを整え、本来体が備えている「自己治癒力」を高めることで風邪の改善へと導きます。
例えば、風邪の初期に使われる葛根湯(かっこんとう)は、免疫力を高めてウイルスの繁殖を抑えます。
薬が効いてくると体が温かくなり、発汗が促され、体が楽になります。
しかし、漢方薬は人によって合う薬が違うと言われています。
一般的に風邪の初期には、葛根湯というイメージを持つ人も多いと思いますが、体質によっては別の薬が合うこともあります。
葛根湯が合うのは比較的体力がある人で、熱や頭痛、肩こりを伴う場合です。虚弱な人が風邪をひいた場合は葛根湯ではなく、麻黄附子細辛湯(まおうぶしさいしんとう)や小青竜湯(しょうせいりゅうとう)の方が効くことが、多くの研究で明らかになっています。
麻黄附子細辛湯は、日ごろから足や腰の冷えが強く風邪をひいても熱がそれほど出ない人に向いています。
小青竜湯は、体力のない人が鼻水の出る風邪にかかったときに効果的な漢方薬です。
風邪に効く漢方薬の多くはウイルスに対する免疫力を高めてくれます。
また、その効果を最大限に引き出すためには「養生」が欠かせません。
安静にして、十分な睡眠とバランスのよい食事を取り、体を温め血流をよくすることで免疫が高まります。
漢方薬の服用方法
服用のタイミングは通常、食前または食間ですが、飲み忘れた場合は食後に飲んでも構いません。
服用回数は1日2~3回など症状によって違います。基本的には水か白湯で飲むようにします。薬によって白湯によっては白湯に溶かして飲む場合もあります。
服用するときは、医師や薬剤師の指示に従うようにしてください。
また、薬局やスーパーなどで購入する場合は、症状を薬剤師に相談してから購入するようにしてください。
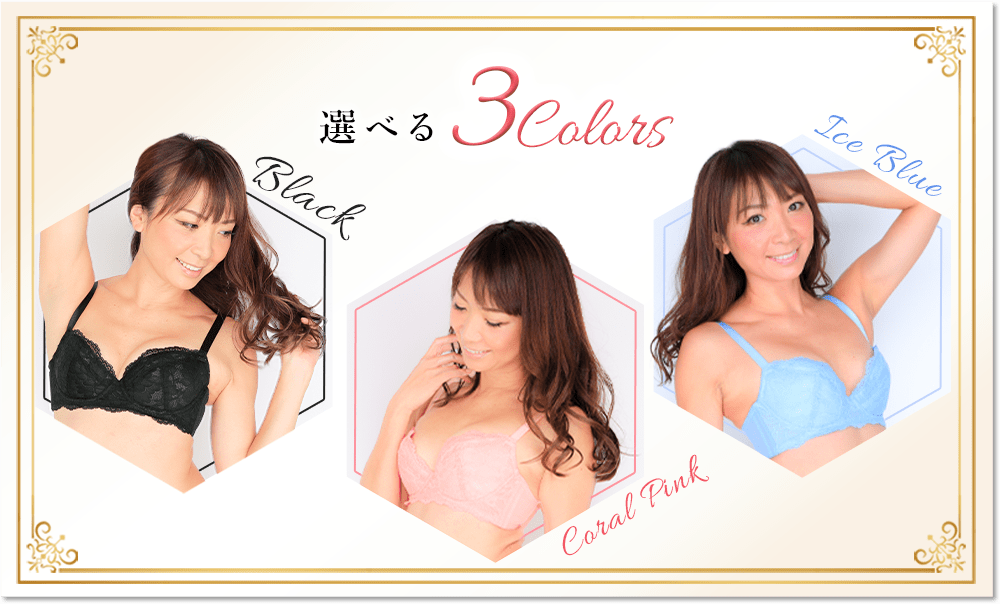










 新型コロナウイルスによって長期期間にわたって誰もが行動制限を受けることになり現在も少しは緩和されたものの感染対策を余儀なくされています。
新型コロナウイルスによって長期期間にわたって誰もが行動制限を受けることになり現在も少しは緩和されたものの感染対策を余儀なくされています。