認知症と難聴の関係とは

高齢化が進んでいく中、どうしても認知症について考えてしまいますよね。また、親が高齢の方にとっては他人事ではないテーマだと思います。
年を重ねるとどうして目や耳が悪くなってしまいますよね。目の場合は老眼鏡や眼鏡といったもので補うことができますし、たとえ白内障になったとしても眼科医で正しい治療を受ければ治る病気です。
しかし、難聴になると認知症のリスクが高くなるということが分かったのです。
難聴になると認知症のリスクが高くなるという報告が、厚生労働省から発表されたのです。今後、超高齢化社会である日本で暮らす私たちにとって、難聴と認知症の関係はとても身近な問題です。
・難聴は認知症の発症要因の一つ
現在、日本人の認知症患者は約462万人(2012年厚生労働省調べ)となっています。この数字からすると、高齢者の4人に1人は認知症、またはその予備軍といわれています。
団塊の世代が後期高齢者となる2025年には、患者数が700万人を超えるとも言われています。
2015年1月、政府は高齢化が急速に進む日本の問題に、認知症の対策強化に向けての国家戦略である新オレンジプラン(認知症施策推進総合戦略)を策定したのです。
認知症発症予防の推進と認知症高齢者の日常生活を支える仕組みづくりに国をあげて取り組みはじめたのです。
その中で認知症の危険因子として「加齢」や「高血圧」のほか、「難聴」も一因として挙げられているのです。
難聴になると、周囲からの情報量が絶対的に減少してしまうのです。その結果、他人の言っていることがよく聞き取れない、会話がうまく成立しない、という経験を繰り返してしまい周囲との関わりを避けるようになるのです。
そして、だんだん社会との交流が減少し、精神的健康にも影響を与え、認知機能の低下をもたらすことがあるのです。
しかし、難聴になったからと言って、すぐに認知症になるわけではありません。難聴によりコミュニケーションが少なくなったり社会との関わりが減ることで、認知機能に影響が出る可能性があるのです。
◎聴覚障害による影響の広がり
音や声などの聴覚刺激が入らない
↓
コミュニケーションが困難になる。危険の察知、周辺環境の把握がしづらくなる
↓
心理的、情緒的影響。孤立、不安、憂うつ、意欲の減退、楽しみの制限
↓
社会との交流、参加の減少
↓
認知機能への影響
・そもそも難聴って?
難聴は年を重ねるにつれ、誰でも起こりうるものです。聴力の低下は30代からすでに始まっていて難聴が進むにつれて、聞こえる音が減っていくのです。
会話の成分ですが、アイウエオなどの母音は比較的低い帯域で、エネルギーが大きく(音量が大きい)、サやタなどの子音の成分は高い帯域でエネルギーが小さい(音量が小さい)のです。
加齢性の難聴は、一般的に高い音から聞こえが悪くなってくるのです。したがって、会話の中でも子音が聞き取りづらくなり、「さかな」と「たかな」や「いちじ」と「しちじ」を聞き間違えたり、聞き分けることが難しくなったりすることがあるのです。
聴力の低下は高齢者の悩みとしてイメージされている事がありますが、実は30代から既に始まっているのです。
聴力の低下は徐々に起こりますので、自分では気づきにくい、というのも加齢性難聴の特徴なのです。
◎難聴が進むとどうなる?
難聴が進むと、だんだんコミュニケーションをとるのが、億劫になってくるのです。
たとえば、「声を掛けても返事がないから余計な話はしない。」聞こえの問題で、家族や友人とのコミュニケーションがしにくいと感じていませんか?
加齢による聞こえは徐々に低下するため、本人も気づかないまま対応が遅れることが少なくありません。
また、難聴は目には見えにくい障害で周囲の人から理解されにくい側面もあるのです。そのため「テレビの音が大きすぎるので一緒に見ない」「同じことを繰り返し尋ねられるので面倒」など、難聴に対する理解不足のために人間関係にも影響を及ぼすこともあるのです。
聴覚情報は様々な情動を引き起こす非常に大切なものです。
会話コミュニケーションは、耳に言葉が入ることから始まります。耳で言葉を聞いて、脳で思考し、言葉で返す。というのが会話をするときの処理プロセスです。
つまり聴覚は、思考をするための大切な情報源であり、この聴覚によって、「楽しい」「うれしい」「悲しい」「怒り」などの情動を引き起こすのです。
したがって聴覚は、コミュニケーションをする上でとても大切なものなのです。
・研究で明らかにされた難聴と認知機能の関係性
聴力の低下は認知機能の低下に関連するということは、さまざまな研究でも示されているのです。
たとえば、1年の加齢による認知機能の低下を比較したアメリカでの研究によれば、健康な人の認知機能テストのスコアは0.5減だったのに対して、25デシベルの難聴をもつ人のスコアは3.86減だったのです。
これは健康な人の約7年分の加齢に伴う認知機能低下が、難聴者には約1年で起こりうるということになるのです。
難聴が認知症の発症の要因の一つである事は、国内外問わず多くの研究機関からも注目を集めているのです。
・補聴器で快適な生活を
難聴の進行をそのままにしておくと、コミュニケーションが不足して孤立が進み、最終的には認知機能の低下やうつ病を発症するリスクが高くなるのです。
そのため、早めに補聴器を使うことで脳に音を届け刺激を与えることが大切となります。
補聴器は、近年で大きく進化しました。多くの難聴の症状に対応できるようになりました。
最近の補聴器は小型で目立たないだけでなく、多くの機能を搭載しているのです。補聴器は、単に音を大きくする機器ではなく、高度なテクノロジーを使い、様々な聞こえの問題を補う大切な聞こえのパートナーとなっているのです。
補聴器は買ってすぐ聞こえると思っている方が多いのですが、買ってすぐに聞こえるようになるわけではないのです。
30代から徐々に低下した聴力に対し、補聴器を使うことで以前の聞こえを取り戻すためには、ある程度の時間が必要となるのです。
急に音を入れるとびっくりしてしまうので、少しずつ音量を上げていき、その人に合う補聴器に調整してくことが必要なのです。
そのためには、信頼できる耳鼻咽喉科専門医や補聴器取扱店を選ぶことが重要となってくるのです。
聞こえの相談はまず、耳鼻咽喉科専門医を受診することからはじめます。
日本耳鼻咽喉科学会認定耳鼻咽喉科専門医の中で、講習カリキュラムの全てを履修し、認定された補聴器相談医制度は、難聴者がそのコミュニケーション障害に有効な補聴器を適正に選択して使用できるように対応することを目的としているのです。
現在、4000名以上の耳鼻咽喉科専門医が認定されていますので、補聴器相談医は、日本耳鼻咽喉科学会のホームページで検索することができますので、お近くの専門医を探してみてください。
・まとめ
難聴が進むと認知症のリスクが高くなる。これは厚生労働省から発表されたショッキングな報告です。
2025年には団塊の世代が後期高齢期に入っていくと難聴の患者数が700万人を超えると言われています。
難聴が進むと周囲からの情報量が極端に減少してしまいます。その結果、他人の言っていることがよく聞き取れない、会話がうまくかみ合わないなど様々な障害が起こってきます。
そうなるとより一層、孤立してしまい精神的健康にも影響を与え、認知機能の低下をもたらすのです。
聴覚情報は様々な情動を引き起こす非常に大切なものです。そこで、補聴器を使うことで脳に刺激を与えることが重要となってきます。
補聴器は買ってすぐに聞こえるというものではなく、調整が必要となります。そのためには日本耳鼻咽喉科学会が認定する耳鼻咽喉科専門医や信頼できる補聴器取扱店を選ぶことが重要となってきます。
 「風邪は万病のもと」といわれるように、こじらせると肺炎などの重い病気を引き起こすこともありますので、お年寄りや乳幼児、あるいは基礎疾患のある方は軽視することはできません。
「風邪は万病のもと」といわれるように、こじらせると肺炎などの重い病気を引き起こすこともありますので、お年寄りや乳幼児、あるいは基礎疾患のある方は軽視することはできません。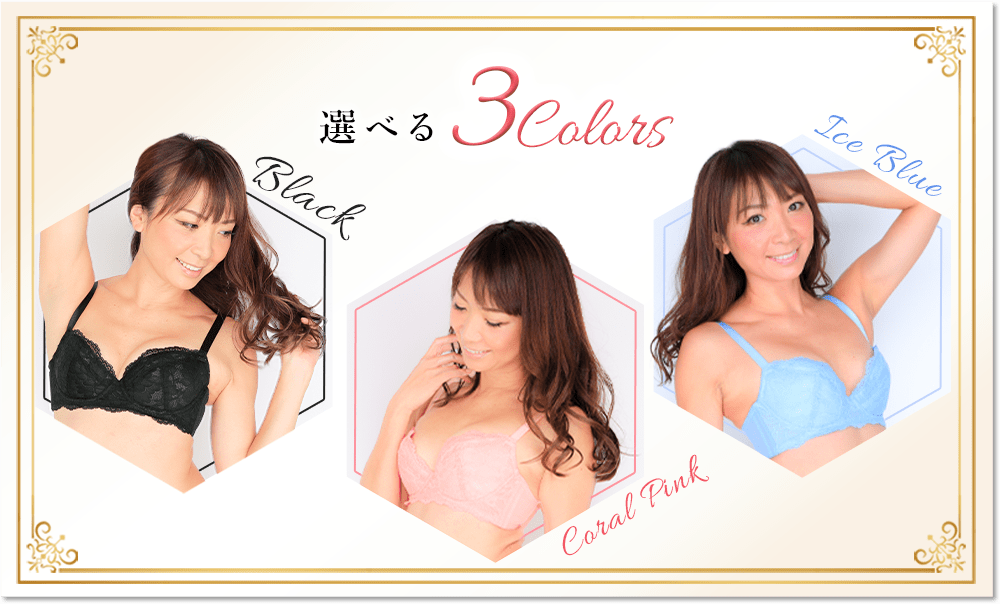










 仮に高塩分な食事を続けているとします。
仮に高塩分な食事を続けているとします。 一般的によく実施される検査について簡単に説明していきます。
一般的によく実施される検査について簡単に説明していきます。
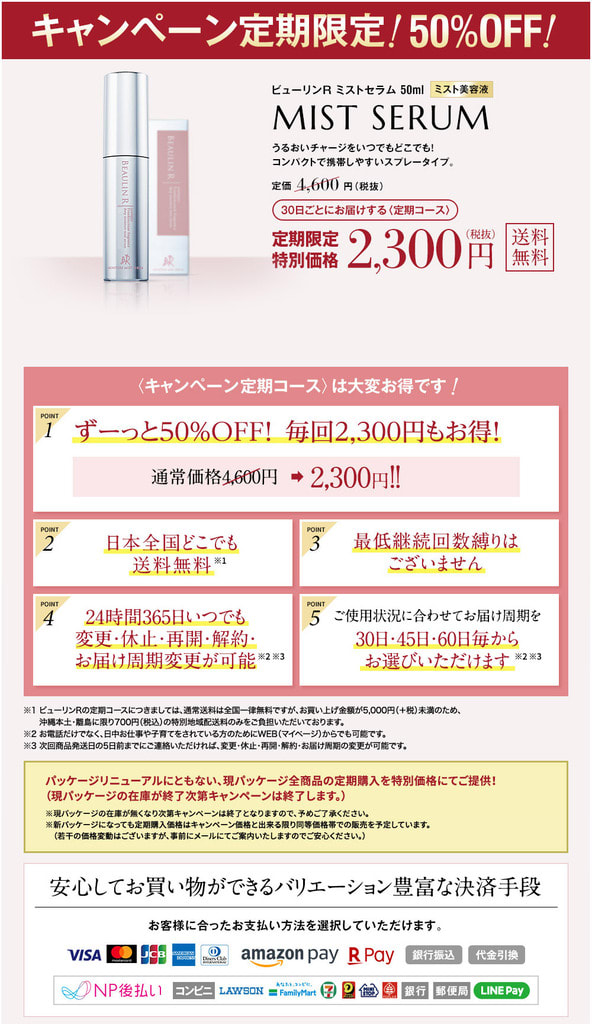





 人工呼吸器ってどのようなモノかご存知ですか?
人工呼吸器ってどのようなモノかご存知ですか?

 外反母趾は最近では一般的な病名として知らていますが、それまでは整形外科を受診する方は少なかったみたいです。
外反母趾は最近では一般的な病名として知らていますが、それまでは整形外科を受診する方は少なかったみたいです。 高齢化が進んでいく中、どうしても認知症について考えてしまいますよね。また、親が高齢の方にとっては他人事ではないテーマだと思います。
高齢化が進んでいく中、どうしても認知症について考えてしまいますよね。また、親が高齢の方にとっては他人事ではないテーマだと思います。