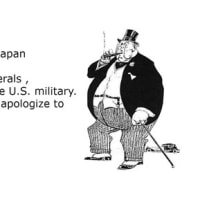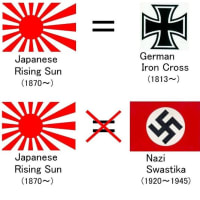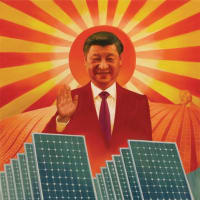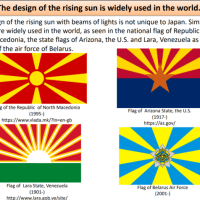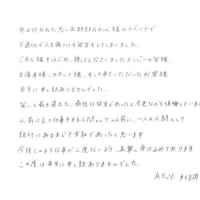What Money Can't Buy: The Moral Limits of Markets [ペーパーバック]
Michael Sandel (著)
忘れないうちに感想文。
Justice でもそうであったが、リベラルのロールズ、リバタリアンのノチックの著作に比べてかなりわかりやすい、というのが一番注目に値する。
で、内容はというと、金で買えないもの、というより、金で買うべきものでないもの、という話。現代社会では金でかうべきものでないものまで、売り買いの対象にしてしまっている、と。
そして、政治的影響力やら、教育、環境などすべてものが買えるとなると、貧富の差があらゆる生活面でものをいうようになっていくるが、いかがなものか?と。
市の命名権など日本でも最近話題になっているが、面白いところで、特定の有名人が今年死ぬか、とかいうのも賭博の対象になったりするそうな。それとか、普通の生命保険はまだ、残された家族のため、という大義があるが、従業員が死ぬと雇用者にかなりの額の保険金がはいるという商売もあるそうで、会社は、従業員の訓練と死んでその交代費用のために保険をかけているのだ、というが、死ねば儲かるというのはいかがなものか、というわけである。それと似たようなので、個人にかけられた保険金を他人に譲渡することができるそうで、その場合、その人が早く死ねば死ぬほど儲かる、というような商品もあるそうな。
で、売買の対象にしてよいものもあるが、商品化してしまうと、、公平性、不平等、自由意志が問題になるものと、商品化されると、その対象の品位が下がり、その対象の意味がかわってしまうものがある、という。
例えば、売春というのは、貧困が原因で売春せざる得ない場合も多いが、その場合は、経済的格差、自由意志が問題になり、かつ、女性として、あるいには人間として、品位が傷つく、といわれる。
page 114
面白いのは、スイスのある地方で、放射性廃棄物を処理の必要性を説いたら、その道義に感銘して、引き受けるという人が多かったが、、受け入れてくれたら、金を出す、と おまけをつけたら、受け入れ支持が減ったのだそうな。 金を出されたからやる、というのと、大義のためにやる、というのでは意味が違うし、金を出されてしまっては、やる価値が低減してしまう場合もあるわけである。
サンデルが出している例ではないが、例えば、走れメロスなんかも、友情のために走ったのと、間にあえば金がもらえるから走った、というのでは、走った意味が異なってくる。そういう意味では純粋な動機が問題にされる場合もあるのである。
で、野球なんかでも、昔は金持ちも貧乏人もみんな似たような場所で、わいわい言いながら観戦・応援していたわけだが、最近は席のすごいのができて、金持ちは見下ろすような特等席で観戦し、また、住む場所、学校も、金持ちと貧乏人とで、棲み分けられるようになってしまってきている、と。
page 203
At the time of rising inequality、the marketization of everything means that people of affluence and people of modest means lead increasingly separate lives. We live and work and shop and play in different places....
Democracy does not require perfect equality but it does require that citizens share in a common life. What matters is that people of different backgrounds and social positions encounter one another, and bump up against one another in the course of every day life. For this is how we learn to negotiate and abide our differences and how we come to care for the common good.
しかし、民主主義社会というのは、共通の生活のなかで、違う背景の人たちが出会い、ぶつかり合いながらも、それぞれが交渉し、譲歩しながら、共通の理想にむかってすすむ社会なのだから、あまりにも貧富の差ができて、貧乏人と金持ちが分離隔離されたような社会になってしまうと、民主主義も機能しなくなるのではないか、と。
するどい問題提起を含むと思うし、経済的価値が経済的価値以外の価値を押しのけてしまう現代社会に警笛をならすものとして、おもしろい。
が、しかし、だからといって、安易に、日本の市場の自由化を否定すべきでもない、日本の市場の自由化やあるいは、民営化は、一部の官僚や民間人がしがみついている既得権益を分散・打破することであって、むしろ、伝統的な意味では貪欲という悪徳の温床になっていなくもない。
page 13
Disillusion with politics has deepened as citizen grow frustrated with a political system unable to act for the public good, or to address the questions that matter most.
政治が、権力闘争に現をぬかして、国家の重要問題に対処していないのは、いずこも同じらしい。
しかし、そういったときこそ、むしろ、われわれにとって大事なものはなにか、われわれの社会が実現すべき価値とはどんなことなのか、などを公共の議論の場にのせて、経済的価値と非経済的価値の棲み分けをしっかりさせていかなくてはならない、というわけであろう。
書評
Wall Street Journal
Review
Telegraph
: review
Independent
review
Independent は経済学者による反論を含んだ書評。
経済学者にしても、貧富の格差の助長を是認しているわけでもなく、貧者が飢えてしまうのはまずい、という功利主義的理由で反対するのだ、と。
mozu
05/14/2012
Time to Admit Defeat
Greece Can No Longer Delay Euro Zone Exit
Part 4: Scenarios for a Greek Exit
ギリシャが破産しても、輸入が減って、内需拡大、輸出が伸びて、観光が増えて、そう悪くないじゃないか、、というのは以前から言われていた。
ギリシャ再選挙へ 「緊縮か、ユーロ離脱か」 欧州債務危機深刻化の恐れも
2012.5.16
どうなるんだろうね。
性暴力被害、24時間支援 6月から東京で電話相談開始
この手の相談所は国や自治体が積極的に支援すべき。
mozu @mozumozumozu
Updated May 15, 2012, 10:39 a.m. ET
China and Japan Fall Out Over Uighurs
どうも、WSJの林という記者の記事には一抹の怪しさを感じることが多いな。
VK May 16, 2012 at 12:56 am
この方のコメントは常に傾聴に値する。
Michael Sandel (著)
忘れないうちに感想文。
Justice でもそうであったが、リベラルのロールズ、リバタリアンのノチックの著作に比べてかなりわかりやすい、というのが一番注目に値する。
で、内容はというと、金で買えないもの、というより、金で買うべきものでないもの、という話。現代社会では金でかうべきものでないものまで、売り買いの対象にしてしまっている、と。
そして、政治的影響力やら、教育、環境などすべてものが買えるとなると、貧富の差があらゆる生活面でものをいうようになっていくるが、いかがなものか?と。
市の命名権など日本でも最近話題になっているが、面白いところで、特定の有名人が今年死ぬか、とかいうのも賭博の対象になったりするそうな。それとか、普通の生命保険はまだ、残された家族のため、という大義があるが、従業員が死ぬと雇用者にかなりの額の保険金がはいるという商売もあるそうで、会社は、従業員の訓練と死んでその交代費用のために保険をかけているのだ、というが、死ねば儲かるというのはいかがなものか、というわけである。それと似たようなので、個人にかけられた保険金を他人に譲渡することができるそうで、その場合、その人が早く死ねば死ぬほど儲かる、というような商品もあるそうな。
で、売買の対象にしてよいものもあるが、商品化してしまうと、、公平性、不平等、自由意志が問題になるものと、商品化されると、その対象の品位が下がり、その対象の意味がかわってしまうものがある、という。
例えば、売春というのは、貧困が原因で売春せざる得ない場合も多いが、その場合は、経済的格差、自由意志が問題になり、かつ、女性として、あるいには人間として、品位が傷つく、といわれる。
page 114
面白いのは、スイスのある地方で、放射性廃棄物を処理の必要性を説いたら、その道義に感銘して、引き受けるという人が多かったが、、受け入れてくれたら、金を出す、と おまけをつけたら、受け入れ支持が減ったのだそうな。 金を出されたからやる、というのと、大義のためにやる、というのでは意味が違うし、金を出されてしまっては、やる価値が低減してしまう場合もあるわけである。
サンデルが出している例ではないが、例えば、走れメロスなんかも、友情のために走ったのと、間にあえば金がもらえるから走った、というのでは、走った意味が異なってくる。そういう意味では純粋な動機が問題にされる場合もあるのである。
で、野球なんかでも、昔は金持ちも貧乏人もみんな似たような場所で、わいわい言いながら観戦・応援していたわけだが、最近は席のすごいのができて、金持ちは見下ろすような特等席で観戦し、また、住む場所、学校も、金持ちと貧乏人とで、棲み分けられるようになってしまってきている、と。
page 203
At the time of rising inequality、the marketization of everything means that people of affluence and people of modest means lead increasingly separate lives. We live and work and shop and play in different places....
Democracy does not require perfect equality but it does require that citizens share in a common life. What matters is that people of different backgrounds and social positions encounter one another, and bump up against one another in the course of every day life. For this is how we learn to negotiate and abide our differences and how we come to care for the common good.
しかし、民主主義社会というのは、共通の生活のなかで、違う背景の人たちが出会い、ぶつかり合いながらも、それぞれが交渉し、譲歩しながら、共通の理想にむかってすすむ社会なのだから、あまりにも貧富の差ができて、貧乏人と金持ちが分離隔離されたような社会になってしまうと、民主主義も機能しなくなるのではないか、と。
するどい問題提起を含むと思うし、経済的価値が経済的価値以外の価値を押しのけてしまう現代社会に警笛をならすものとして、おもしろい。
が、しかし、だからといって、安易に、日本の市場の自由化を否定すべきでもない、日本の市場の自由化やあるいは、民営化は、一部の官僚や民間人がしがみついている既得権益を分散・打破することであって、むしろ、伝統的な意味では貪欲という悪徳の温床になっていなくもない。
page 13
Disillusion with politics has deepened as citizen grow frustrated with a political system unable to act for the public good, or to address the questions that matter most.
政治が、権力闘争に現をぬかして、国家の重要問題に対処していないのは、いずこも同じらしい。
しかし、そういったときこそ、むしろ、われわれにとって大事なものはなにか、われわれの社会が実現すべき価値とはどんなことなのか、などを公共の議論の場にのせて、経済的価値と非経済的価値の棲み分けをしっかりさせていかなくてはならない、というわけであろう。
書評
Wall Street Journal
Review
Telegraph
: review
Independent
review
Independent は経済学者による反論を含んだ書評。
We might agree that the new markets in financial indices of agricultural commodity prices, created by Goldman Sachs and others, are intolerable. For me, the reason is the utilitarian one that they are making very poor people go hungry.
経済学者にしても、貧富の格差の助長を是認しているわけでもなく、貧者が飢えてしまうのはまずい、という功利主義的理由で反対するのだ、と。
mozu
@mozumozumozuト
フォロー
Time to Admit Defeat: Greece Can No Longer Delay Euro Zone Exit http://j.mp/LMhyYj @SPIEGELONLINEさんから
返信 リツイート お気に入りに登録
2012年5月15日 - 16:25 Tweet Buttonから · このツイートをサイ
05/14/2012
Time to Admit Defeat
Greece Can No Longer Delay Euro Zone Exit
Part 4: Scenarios for a Greek Exit
If the drachma returns, it will drastically lose value against the euro, with experts expecting a devaluation of at least 50 percent. Insiders say that a loss of up to 80 percent is even possible. Banks and companies with foreign debts denominated in euros could no longer service them and would have to file for bankruptcy.
As a result, Greece would plunge into an even deeper recession. The IMF estimates a decline in economic output of more than 10 percent for the first year following the return of the drachma. This would set the country back by years in economic terms.
But after that, according to the IMF, the Greek economy will grow even faster than it would without the devaluation. "The turbulence could last one or two years," says Hans-Werner Sinn, president of the influential Munich-based Ifo Institute for Economic Research. But after that, he adds, things will improve again.
The professor's prognosis is based on two assumptions. First, because imports will become more expensive, the Greeks will buy more domestic products, eating Greek instead of Dutch tomatoes, for example. At the same time, the country's exports will become cheaper, making it more competitive. The result: Greek olive oil will displace Spanish oil in German supermarkets.
Tourist Attraction
Many countries have successfully exported their way out of their plights in the past through currency devaluation: Sweden in the wake of the banking crash in the early 1990s, South Korea following the 1997 Asian financial crisis and Argentina after the end of the dollar regime in 2001. In all of these countries, the economy crashed initially, only to recover all the more vigorously in the end.
Greece can reduce its foreign trade deficit by exporting more and importing less. In the last decade, its trade deficit was at a near-record 10 percent. Even in 2010, when the crisis hit with full force, the country imported €32 billion more in goods than it sold abroad. As a result, Greece, supposedly an agricultural country, is still a net importer of food products.
Another economic sector on which many are pinning their hopes is also likely to benefit from the return of the drachma: tourism. A vacation in Greece has become too expensive for many foreigners. But with the new currency, the country could compete once again with its toughest rivals, Turkey and North Africa.
The Fitch rating agency estimates that public-sector claims against Greece will grow to more than €300 billion this year. If the majority of these claims became worthless, the German finance minister alone would face a loss of tens of billions of euros.
This is a large amount, and yet most economists believe it is manageable. It would roughly correspond to the German government's net borrowing for this year. In other words, the economic damage of a Greek withdrawal from the euro for Germany would remain within limits. "The Greek economy is simply too insignificant for that," says the Oxford-based German economist Clemens Fuest
ギリシャが破産しても、輸入が減って、内需拡大、輸出が伸びて、観光が増えて、そう悪くないじゃないか、、というのは以前から言われていた。
ギリシャ再選挙へ 「緊縮か、ユーロ離脱か」 欧州債務危機深刻化の恐れも
2012.5.16
ギリシャ離脱はユーロ全体の信用失墜につながる恐れがあり、欧州全体への影響は読み切れない。逆に、ユーロ離脱の規定がないことから、国民の8割がユーロ残留を望むギリシャが自ら離脱する可能性は低く、危機が拡大するとの見方もある。「緊縮断行か、ユーロ離脱か」-。ユーロ圏諸国とギリシャの神経戦が激しくなってきた。
どうなるんだろうね。
性暴力被害、24時間支援 6月から東京で電話相談開始
性暴力にあった女性と子どもを被害後早くから支えようと、DV(ドメスティックバイオレンス)などの問題にとりくんできた女性たちが「性暴力救援センター・東京」を結成した。6月から24時間の電話相談を受け付け、早期の医療ケアに結びつけていく取り組みを始める。
性被害の場合、早く産婦人科に行って適切な処置を受けられれば妊娠を防げる可能性が高くなり、心身の回復にもつながりやすいとされる。ただ、被害を周囲に話したり、病院に行ったりするのをためらう人が多いのが特徴だ。
こうした課題を解消するため、安心して話せる相談窓口の整備や受け入れる医療体制づくりが各地で進んでいる。大阪では一昨年春に民間の「性暴力救援センター・大阪」が病院内に専用診察室を設けて電話相談を始めた。その夏には、愛知県警などが「ハートフルステーションあいち」をスタート。6月からは佐賀県も始める予定。東京のセンター結成もこうした取り組みの一つだ。
センターの代表は東京都江戸川区のまつしま病院(産科、婦人科、小児科、心療内科)の佐々木静子院長が務める。事務局長の平川和子・東京フェミニストセラピィセンター所長は、被害から何年もたって相談に来る女性たちにカウンセラーとして接してきた。「被害直後からのケアが、どうしても必要。急性期のケアができる場所をつくれば、いろんな支援につながりやすい」と語る。
電話を受けるのは、NPO法人「女性の安全と健康のための支援教育センター」による性暴力被害者支援看護職養成講座(40時間)を修了した看護師ら。必要に応じて、弁護士や精神科医、シェルター(避難所)も紹介する。本人が望めば警察に通報する。
電話相談の番号は03・5607・0799。相談は電話・面接とも無料。活動費は寄付を募っていく。(編集委員・河原理子)
この手の相談所は国や自治体が積極的に支援すべき。
mozu @mozumozumozu
China and Japan Fall Out Over Uighurs http://j.mp/KqboiR @WSJさんから ともあれ筋は通ったな
閉じる
返信 リツイート お気に入りに登録
Updated May 15, 2012, 10:39 a.m. ET
China and Japan Fall Out Over Uighurs
どうも、WSJの林という記者の記事には一抹の怪しさを感じることが多いな。
VK May 16, 2012 at 12:56 am
@Ken Y-N (aka Tepido Naruhodo):
Actually, I’m not too happy with the idea of labelling a single ethnic grouping as a “community” just because of their ethnicity.
You’re right not to be happy. I don’t know how better to put it than that there’s a lot of crap thinking about ethnicity and what it means for individuals. People have multiple ethnicities: you yourself (afaik from that profile about WJT) are a Scot, a Briton, a European, white, a Westerner – and that’s quite aside from the issue of whether that matters more to you than the company you work for, being a biker, a blogger, or an immigrant to Japan or that part of Japan you call home.
“Community” is a tedious modern media invention that justifies pigeon-holing under the guise of empathy. What matters, in the jargon, is salience. Which categories are politically and emotionally important? For me for example, that’s prinarily being a parent (and the partner of a working mother) and an education worker. It’s purely emotional after that that I’m a foreigner – and to be honest, that’s as more a European in a foreign-means-American environment than a westerner. My Japanese needs to be better (that I’m a language learner is another identity) but as the kind of foreigner I am, I don’t have a salient “NJ” identity. I have more in common with a Japanese university teacher than with a 22-year-old Australian on a gap year.
There used to be a time where people dreamt that race would matter less and economics would matter more. (Level3 – this is genuine left-wingery). But for Arudou I think it has always been about being a White Guy In Japan. I’m really not sure he misinterpreted that comment about Koreans and Chinese.
この方のコメントは常に傾聴に値する。