「東京・遠く近き」というタイトルのエッセイは、登山関係の評論で知られる近藤信行氏の著作で、丸善から発行されている「学鐙」に1990年から1998年頃に掛けて全105回に渡り連載されていた作品である。氏は1931年深川清澄町の生まれで、早稲田大学仏文から大学院修士課程を修了され、中央公論社で活躍された。その後、文芸雑誌「海」を創刊し、現在は山梨県立文学館館長を務められている。残念ながら書籍化されていないので、その内容を紹介しながら思うところなど書いていこうという趣向である。
「『大川端』の主人公は、それまで住んでいた山の手の家を離れて代地河岸に引越している。神田川の大川に注ぐあたり、いまの柳橋一丁目にあたるところだが、近所は料亭とか役者の家、妾宅、大商人の別宅ばかりだった。「踊や唄の稽古に行くお酌達は、毎朝のやうに家の前を通つた」とあり、顔なじみの妓が通ると、彼は読みかけの本を手にもったまま、二階から声をかけている。
「これからお稽古。」「ええ。」「早く行つてらつしやい。」この土地に住んで「かういつた挨拶をするのを名誉とも幸福とも感じた」というのである。」
小山内薫の「大川端」を引き続き進めている。この柳橋一丁目あたりというのは、正に木村莊太、荘八兄弟の暮らす第八いろはと目と鼻の先というところである。小山内はこの兄弟とも交流があった。兄の莊太とは親しい間柄で、その結果弟のと荘八とも知り合っていったというべきだろう。荘八は、幼馴染みの女性が柳橋の世界で大人になっていく様を懸賞小説に書いて入賞したと書いている。万朝報に青木哲というペンネームで投稿したものを小山内に
「「荘八君。あれは君だろう?材料でわかったよ。なかなかよかった。」と、小山内さん独特の鼻にかかったクックッと笑う感じの良い嘲弄愛撫を以って云われた時には、僕はきまりのわるい為に全く引込みがつかなかった。」
と書いている。麹町富士見町で育った小山内の下町耽溺の書であるというこの「大川端」世界は、木村莊太、荘八兄弟にとっては極めて身近な世界であった。


この下りに差し掛かる前には、主人公が小田原に静養する母親を訪ねる傍ら、箱根に遊ぶ中洲の芸者たちの所へ遊びに行く様が描かれており、その舞台として長谷川時雨の母が経営していた新玉ノ湯が描かれている。女流劇作家としても著名になっていた時雨とも小山内は勿論交流がある。
「父親が朝鮮での事業に失敗すると、彼は遊び仲間の「佃の竹ちゃん」の世話で、海のほとりの佃島の下宿へ移った。竹ちゃんには長谷川時雨の弟虎太郎の学生時代の面影がうつされている。木場の福井さんをとりまいていた若もののひとりだ。
この小説には作者自身の身辺の事実と虚構が綯い交ぜになっている。父親が朝鮮にいて事業に失敗したというのは、まったくの作り話だし、代地河岸は浅草瓦町(柳橋よりはやや上流に当たる)のおきかえである。引っ越し先も佃島ではなく、埋め立てたばかりの草蓬蓬の月島である。谷崎潤一郎は明治四十三年、第二次「新思潮」の発刊をもくろんで小山内を訪ねたときのことを「当時氏はまだ独身で、月島の海水館といふ下宿に住んでをられた。私は品川の海が見える二階の部屋に通されて、一時間ばかりお邪魔した」と書いている。『大川端』でおきかえた土地からみると、いかにも遊び人、風流人という印象を与えられる。これは作者の設定した舞台装置なのであろう。」
この頃、長谷川時雨は明治40年にようやく水橋信蔵との協議離婚が成立し、新佃島で隠居生活に入った父や兄弟と暮らしていた。母多岐は箱根塔ノ沢の新玉ノ湯の経営に当たっており、小山内のこの作品は時雨の世界とも重なってくるものがあって面白い。木村兄弟と長谷川時雨との間には直接の交流はない。木村莊太は時雨について、伊藤野枝との恋愛事件の後に帝劇で自分を渦中の人物として見ていたことがあると記しているのみである。生粋の日本橋っ子である時雨にたいして、莊太はおそらく自らコンプレックスを作り出していたことだろうと思う。そして、その間の空間を生きていたのが、正に小山内薫であったと言えるように思う。
海水館を近藤氏は月島と書いているが、実は佃島である。といっても、新しく埋め立てられた新佃島で三丁目に今も石碑が建てられている。関東大震災の折に焼失してしまった。この「大川端」は、海水館で明治44年に執筆した。明治40年には島崎藤村も滞在している。かつては房総まで見えたという眺望も、今は晴海に豊洲と新しい埋立地が広がり、それ以前に堤防に遮られて海面を見るにも一苦労する。

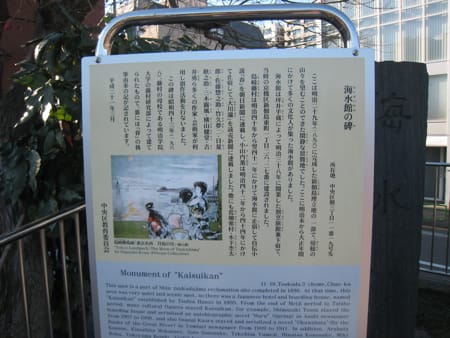
「実際の竹ちゃん、すなわち虎太郎のほうは、のちに新橋の芸妓春奈(時雨の『美人伝』に「胡蝶の春奈」として登場する)と結婚するが、『大川端』の作者は女性にいつも肩すかしばかりくわされている。正宗白鳥は「小山内薫を追想す」(昭和二十二年)のなかで、「あれは年少者に読ませる芸者遊び案内見たいなものですよ」という滝田樗蔭の言葉を記録し、「小山内の小説には、悪どく自己に徹したものもなく、噂話か案内記見たいなものが多かつたやうに、私は記憶してゐる」と書いたことがあったが、自己肯定の甘さがせっかくの題材を中途半端なものにしている。」
演劇界では確固たる足跡を残した小山内だが、小説については厳しい評が出てくる。確かに、この「大川端」を読んでみても、楽天的で呑気で甘いお坊ちゃんの軽い放蕩記といった感は拭えない。どこか欲望に正直というほどでもなく、腹の据わらない煮え切らない男という印象を受ける。この辺り、非常に木村莊太と良く似ているように思える。莊太という男も、煮え切らないという点では人後に落ちない。演劇に情熱を燃やして足跡を残した小山内と、武者小路の新しい村運動に身を投じ、決別した後にも晴耕雨読の生活を希求して三里塚で暮らした莊太。煮え切らないと云いつつも、体の不調を押して演劇活動を続け倒れた小山内と、自らの生涯を赤裸々に描いた自叙伝を書き上げて発行される寸前に自らの命を絶った莊太。都会人の腰の弱さを持ちながら、奥底には激しさも秘めていた二人とも言えるように思える。
時雨の弟、虎太郎は結婚したものの夭折してしまい、男の子が残される。その子は時雨が引き取って育てていった。「長谷川時雨~人と生涯」の著者である長谷川仁氏である。
「小山内薫は明治十四年、広島市の生まれ。父は旧津軽藩士で陸軍軍医だった。鴎外の『澁江抽斎』には小山内玄洋の名で出てくる。母錞(しゅん)は江戸の小旗本小栗信の娘。小栗上野介の分家の出だという。」
三人の妹もみな軍医に嫁いだという一族の中では、芝居の世界にのめり込んだ小山内薫は変わり種であった。この一族には、藤田嗣治という変わり種も出てくるので、やはりどこか収まらないものがあるのだろうか。
「堅気の官吏の家から、文学・演劇に志すものが出たのは、ひとえに江戸・東京育ちの母親の感化だった。」
明治、大正という時代での芝居というものの存在感の大きさというのは、今日では想像することすら難しい様に思う。テレビはもちろんのこと、ラジオもまだ存在しない時代。映画もようやく産声を上げたばかりという時代の芝居というものが、娯楽の王者としての地位として、正に絶対的な王座に君臨していた時代だったと言える。その一方で、役者は人気はあっても社会的な地位は低く、演劇に携わるもの全般に共通して、社会からは低く見られていたのも事実だろう。そんな時代に、官吏の家に生まれて演劇の世界へ入るというのは、あまり普通のこととは思われなかっただろう。永井荷風も官吏の息子であり、彼の父は文学へ傾倒していく息子を嘆き続けたという。
「・・・・・五歳のとき、広島衛戍病院長の父が赴任地で死ぬと、母は子供たちをつれて東京麹町富士見町の持ち家に帰っている。「私はそれから中学を卒へるまで、ここで育つた」とあり、母の親しい友人に「武田のをばさん」がいて、その長男の乳母が画家武内桂舟の母だったことから、薫は桂舟の家に遊びに行くようになったとある。そこは硯友社の作家たちのたまり場だった。子供のころから尾崎紅葉、江見水蔭、弘津柳浪、泉鏡花らの顔をおぼえたというのはそのためである。母親は芸事が好きで、その交際範囲に出てくるのは、近くのインテリ階級の夫人たちだった。」
幼いうちに父親を亡くし、東京育ちの母親の元で育てられたことで、小山内薫という人物の成り立ちが少しずつ見えてくる。その意味では、木村莊太は官吏の家ではないものの、父親は不在に近い存在であり、どこか共通する雰囲気はその辺りから始まっているのだろうかとも思える。
「「十三年」(明治四十一年作)という作品は当時のことを回想していて、毎日のように母のもとにあつまる「家に用のない夫人連」のなかに、帝国大学教授のイギリス人の外妾、アメリカ公使館書記官の内縁の妻、陸軍監督夫人、騎兵中佐夫人、政治家夫人等々がいたと書かれている。「武田のをばさん」はアーネスト・サトウの妻であり、植物学者で日本山岳会創立発起人のひとり武田久吉の母にほかならない。薫の妹の岡田八千代は、父親の遺産、家作料、母の扶助料などで「父の死後、廿年余りを露頭にも迷はず、相当気楽に暮らして来た。・・・・・・母はお人好しで、鐘のあるまゝに人からも多く借り倒されたらしいし、江戸つ子の世話好きで、かなり無駄に金を遣つたらしい」と書いたが、明治の近代化のなかのこのような環境が小山内薫という人物を育てていったとも考えられる。」
明治の東京の中流家庭というものの有り様が、浮かんでくる様に思える。決して庶民とは違うレベルで存在しながら、アッパークラスとも違う位置付けである。こんな話を読んでいると、しばらく前に日本中が一億総中流などと言っていたものが、如何に勘違いであったのかがよく分かる。今日では格差の拡大で状況が変わってきているとはいえ、あの頃でも決して中流というレベルまでは到達できてなどはいなかった。そして、どうやらあの地点が戦後の社会が辿り着いた一つの頂点であった様でもあるのが悲しい。
こういった恵まれた家庭環境の中で育ってきたからなのか、どこか煮え切らない、優柔不断な印象を与える「大川端」の作者だが、明治人らしく直情的に行動する面も見せている。
「彼は一高にすすんでから失恋の経験をした。それがもとで内村鑑三の門をたたいている。」
ここでは、荒川放水路の建設を指揮した技師青山士とも出会っている。とはいえ、小山内が敬虔なキリスト教徒の道を歩むわけもなく、別の恋愛に失敗し、内村門下から遠ざかり、頽廃へと進んだと「自伝」に書いている。その頽廃の成果が「大川端」ということになる。
谷崎潤一郎は、小山内薫の後輩に当たる。
「二人の作家の接点が明治の東京であり、おなじ学校であり、あるいは下町にもあったわけだが、谷崎は先輩としての小山内に礼をつくしながらも、その作品をさほどには評価していない。・・・・・・・・小山内が文壇に打って出たころの作については「障子のところ、私は此れ等の作品を余り好まない」といい、赤門出のチャキチャキの秀才らしい新鮮味があり、才気煥発の趣きがあったが、ややだれ気味でほんのスケッチにすぎない、とかなりきびしい。」
「小山内薫も谷崎潤一郎も東京を舞台に作品を書きはじめた作家だった。その点では都会派の作家であり、東京人ならではの文学であった。しかし山の手育ち、下町育ちのちがいは歴然たるものがある。」
というあたり、著者の近藤氏も下町育ちだけに、山の手育ちに対してみな厳しくて、小山内が少々気の毒に思えてくる。とはいっても、どこか野暮ったさを秘めている、読んでいると隔靴掻痒という言葉も思い浮かぶ「大川端」の主人公の姿を想い起こすと、この辺りの指摘にも頷かざるを得ない。長谷川時雨の弟、虎之助に追い越されていくのもむべなるかなという気がしてしまう。とはいっても、小山内の業績が小説の評価で全て測れるものではもちろんなく、演劇という世界での活動に身命を文字通り賭していったのは言うまでもない。
「谷崎の文壇登場については、その『青春物語』にくわしい。小山内薫の傘下にあつまって第二次「新思潮」を創刊したことについて、谷崎は「われわれとして最も賢い方策であつた」と書いている。赤門出の作家は漱石一派をのぞいては微々たるもので、「ひとり小山内氏のみが文壇にも劇壇にも幅を利かせてゐたから、後進のわれわれがもし先輩を担ぐとすれば、この人を頼るより外はなかつた」とある。」
木村莊太は第一次新思潮の最終号で「新生」という作品を書き、デビューを飾っている。二代目木村荘平を継いだ荘蔵夫婦は文学好きであり、早世した曙の関係で硯友社の文人と親しかった。そんなことから、莊太は第一次「新思潮」に紹介される。そんなことから小山内薫とも親交を結ぶようになり、その縁を頼って第二次「新思潮」の創刊を目論む若手が、小山内と親しい莊太を訪ねたところから第二次「新思潮」が始まっていく。そこに谷崎潤一郎も加わることになり、莊太と谷崎は出会い、意気投合していく。谷崎は莊太よりも三歳年上なのだが、非常にウマが合ったようで、一時は連れだって遊んで歩いていたようだ。この辺りは、弟の荘八が岸田劉生と濃密な友情を育んでいたことと重なるようにも思えてしまう。
やがて、谷崎は文壇で確固たる地位を築き、多忙な売れっ子作家となっていく。
「「新思潮」の終刊とともに発表舞台は「スバル」「三田文学」や「中央公論」に移り、「三田文学」誌上で永井荷風の推讃をうけたことは、あまりに有名な文学史上の事実である。明治四十三年秋から四十四年秋にかけての出来事であった。」
谷崎は、こうして一流作家への階段を駆け上がっていく。
「この華々しいデビュー当時にあって、谷崎は小山内の反感を買ったというのだ。二つの小山内追悼文では、二人の間にちょっとした事件があってとか、「先生」が「さん」になったのにはちょっとしたいきさつがあるので、といいながらも。
「それといふのは、私の文壇への出方が可なりに早く華々しかつたので、何となくそれが癪にさはつて『谷崎の奴はいやに大家ぶつてゐる』といふような悪口をいつて歩いたらしい。故人の欠点を挙げるのも今では思ひ出の種であるからいふのであるが、若い自分の小山内君にはたしかにさういふ気のせまい女性的な一面があつた。大きな顔をしてゐればわれわれの親分として担がれていい人だのに、そんなことから逃げ出した者も少くなかつた。」
と書いた。そのいきさつをさらにこまやかに述べたのがのちの『青春物語』である。」
北荻三郎の「いろはの人びと」によれば、谷崎を評して「あいつは国文科きっての道楽者で、傲慢だし、だらしはないし、始末に困る奴だが、偕楽園という後ろ盾がついている。彼を同人に加えれば、偕楽園の笹沼が資金を出してくれるかもしれないよ。」という大貫雪之助の言で第二次「新思潮」に谷崎潤一郎は加えられたという。偕楽園とは、東京で最初の中華料理店で日本橋亀島町に創業されていたが、若主人の笹沼は谷崎の幼馴染みで、金銭面では親代わりのような存在であったという。そんな話を読んでいると、谷崎という男も一筋縄ではいかない印象であり、小山内に対しての酷評をそのまま受け取るのも小山内に気の毒に思えてしまう。
「谷崎は、小山内の生前には許されなかった弟子のひとりだというのだが、そこには山の手育ちのお坊ちゃん気質と下町生まれのはにかみやがうまくかみあわなかったとも考えられる。「私は自分の恩人であり、わが劇壇第一の功労者である故人に対して、不遜の評価を下したかも知れない。しかしかう云うことを書くのも、今にして故人を愛慕するの情に堪へないからである。故人は実に欠点だらけの人であつた。アラを捜せばいくらでもあつた。何よりもあれ程の才人でありながら、多数を統御する度胸と、落ち着きと、智謀とに欠けてゐた。・・・・・・・・・さう云う点では、弟子から云えば頼みにならない師匠であるが、見様に依つては、氏は後から来る弟子を追ひ越し追ひ越して、常に時代の先頭を切る溌剌たる青年を味方にしてゐたのである。氏が時代の進運と歩調を合わせて永久に若々しかつた所以は此処にあるのであらう」と谷崎は書いている。」
昨今は故人となった途端に、まるで善人100%でその人生を歩んできたかのような云いようが多いのだが、谷崎という人は決してただ先輩をこき下ろしているわけではないことが、よく分かる。こんな言い回しをされているのを見て、小山内は天上から苦笑していたのだろうか?的確な分析と、故人に対する愛情が籠められていることがよく分かる一文だと思う。谷崎という人は確かに一筋縄ではいかない男であり、自らに正直であり続けた男なのだろう。東京の下町育ちでありながら、関東大震災後の新しい東京を受け入れることをしなかったのも、彼の美意識ならではと言えるのかもしれない。
「浜町公園のこうから蠣浜橋跡をすぎ、甘酒横丁を歩く。人形町の大通りをわたり、すこしすすんだところの右側に塚越ビルという建物があって、地下駐車場入口の壁に「谷崎潤一郎生誕の地」の碑がはめこまれている。『幼少時代』その他の文章でくりかえし読んできた「谷崎活版所」の跡地であった。私は好んで人形町界隈を散歩するが、そのたびにこの碑の前で立ちどまってみる。「黒漆喰の土蔵造りの家」の面影は完全に失せ、印刷機械の響きもない。しかしそこに立ちどまるだけで、忽然として在りし日のかたちがみえ、音がきこえてくるようであった。」
親子丼で有名なたまひでと言う店の並び、少し云った辺りに谷崎潤一郎生誕の地はある。震災で焦土と化し、かつての面影は完全に失われてしまったところなのだが、それでも何故町を歩くのかと言われれば、正に在りし日の面影を追い求めているからだとしか言いようがない。変わり果てた町であっても、かつてこの場所がそうだったのかとか、誰かもこの道を歩いたのだろうかと思わされることで、時の流れを越えて思いを巡らせることができる。町の区画さえせめて残されていれば、過去をたどることはできるのだと思う。小山内が歩いた中洲、谷崎の育った人形町。そんな痕跡が数多いことが、都市の財産であるのではなかろうか。過去の町並を跡形もなく消滅させて、完成した瞬間から古びていく超高層ビルには、都市としての奥行きがないのだと思う。
「『大川端』の主人公は、それまで住んでいた山の手の家を離れて代地河岸に引越している。神田川の大川に注ぐあたり、いまの柳橋一丁目にあたるところだが、近所は料亭とか役者の家、妾宅、大商人の別宅ばかりだった。「踊や唄の稽古に行くお酌達は、毎朝のやうに家の前を通つた」とあり、顔なじみの妓が通ると、彼は読みかけの本を手にもったまま、二階から声をかけている。
「これからお稽古。」「ええ。」「早く行つてらつしやい。」この土地に住んで「かういつた挨拶をするのを名誉とも幸福とも感じた」というのである。」
小山内薫の「大川端」を引き続き進めている。この柳橋一丁目あたりというのは、正に木村莊太、荘八兄弟の暮らす第八いろはと目と鼻の先というところである。小山内はこの兄弟とも交流があった。兄の莊太とは親しい間柄で、その結果弟のと荘八とも知り合っていったというべきだろう。荘八は、幼馴染みの女性が柳橋の世界で大人になっていく様を懸賞小説に書いて入賞したと書いている。万朝報に青木哲というペンネームで投稿したものを小山内に
「「荘八君。あれは君だろう?材料でわかったよ。なかなかよかった。」と、小山内さん独特の鼻にかかったクックッと笑う感じの良い嘲弄愛撫を以って云われた時には、僕はきまりのわるい為に全く引込みがつかなかった。」
と書いている。麹町富士見町で育った小山内の下町耽溺の書であるというこの「大川端」世界は、木村莊太、荘八兄弟にとっては極めて身近な世界であった。


この下りに差し掛かる前には、主人公が小田原に静養する母親を訪ねる傍ら、箱根に遊ぶ中洲の芸者たちの所へ遊びに行く様が描かれており、その舞台として長谷川時雨の母が経営していた新玉ノ湯が描かれている。女流劇作家としても著名になっていた時雨とも小山内は勿論交流がある。
「父親が朝鮮での事業に失敗すると、彼は遊び仲間の「佃の竹ちゃん」の世話で、海のほとりの佃島の下宿へ移った。竹ちゃんには長谷川時雨の弟虎太郎の学生時代の面影がうつされている。木場の福井さんをとりまいていた若もののひとりだ。
この小説には作者自身の身辺の事実と虚構が綯い交ぜになっている。父親が朝鮮にいて事業に失敗したというのは、まったくの作り話だし、代地河岸は浅草瓦町(柳橋よりはやや上流に当たる)のおきかえである。引っ越し先も佃島ではなく、埋め立てたばかりの草蓬蓬の月島である。谷崎潤一郎は明治四十三年、第二次「新思潮」の発刊をもくろんで小山内を訪ねたときのことを「当時氏はまだ独身で、月島の海水館といふ下宿に住んでをられた。私は品川の海が見える二階の部屋に通されて、一時間ばかりお邪魔した」と書いている。『大川端』でおきかえた土地からみると、いかにも遊び人、風流人という印象を与えられる。これは作者の設定した舞台装置なのであろう。」
この頃、長谷川時雨は明治40年にようやく水橋信蔵との協議離婚が成立し、新佃島で隠居生活に入った父や兄弟と暮らしていた。母多岐は箱根塔ノ沢の新玉ノ湯の経営に当たっており、小山内のこの作品は時雨の世界とも重なってくるものがあって面白い。木村兄弟と長谷川時雨との間には直接の交流はない。木村莊太は時雨について、伊藤野枝との恋愛事件の後に帝劇で自分を渦中の人物として見ていたことがあると記しているのみである。生粋の日本橋っ子である時雨にたいして、莊太はおそらく自らコンプレックスを作り出していたことだろうと思う。そして、その間の空間を生きていたのが、正に小山内薫であったと言えるように思う。
海水館を近藤氏は月島と書いているが、実は佃島である。といっても、新しく埋め立てられた新佃島で三丁目に今も石碑が建てられている。関東大震災の折に焼失してしまった。この「大川端」は、海水館で明治44年に執筆した。明治40年には島崎藤村も滞在している。かつては房総まで見えたという眺望も、今は晴海に豊洲と新しい埋立地が広がり、それ以前に堤防に遮られて海面を見るにも一苦労する。

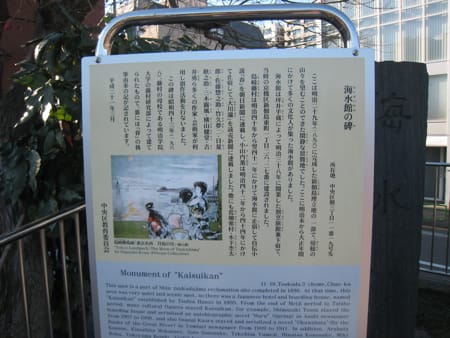
「実際の竹ちゃん、すなわち虎太郎のほうは、のちに新橋の芸妓春奈(時雨の『美人伝』に「胡蝶の春奈」として登場する)と結婚するが、『大川端』の作者は女性にいつも肩すかしばかりくわされている。正宗白鳥は「小山内薫を追想す」(昭和二十二年)のなかで、「あれは年少者に読ませる芸者遊び案内見たいなものですよ」という滝田樗蔭の言葉を記録し、「小山内の小説には、悪どく自己に徹したものもなく、噂話か案内記見たいなものが多かつたやうに、私は記憶してゐる」と書いたことがあったが、自己肯定の甘さがせっかくの題材を中途半端なものにしている。」
演劇界では確固たる足跡を残した小山内だが、小説については厳しい評が出てくる。確かに、この「大川端」を読んでみても、楽天的で呑気で甘いお坊ちゃんの軽い放蕩記といった感は拭えない。どこか欲望に正直というほどでもなく、腹の据わらない煮え切らない男という印象を受ける。この辺り、非常に木村莊太と良く似ているように思える。莊太という男も、煮え切らないという点では人後に落ちない。演劇に情熱を燃やして足跡を残した小山内と、武者小路の新しい村運動に身を投じ、決別した後にも晴耕雨読の生活を希求して三里塚で暮らした莊太。煮え切らないと云いつつも、体の不調を押して演劇活動を続け倒れた小山内と、自らの生涯を赤裸々に描いた自叙伝を書き上げて発行される寸前に自らの命を絶った莊太。都会人の腰の弱さを持ちながら、奥底には激しさも秘めていた二人とも言えるように思える。
時雨の弟、虎太郎は結婚したものの夭折してしまい、男の子が残される。その子は時雨が引き取って育てていった。「長谷川時雨~人と生涯」の著者である長谷川仁氏である。
「小山内薫は明治十四年、広島市の生まれ。父は旧津軽藩士で陸軍軍医だった。鴎外の『澁江抽斎』には小山内玄洋の名で出てくる。母錞(しゅん)は江戸の小旗本小栗信の娘。小栗上野介の分家の出だという。」
三人の妹もみな軍医に嫁いだという一族の中では、芝居の世界にのめり込んだ小山内薫は変わり種であった。この一族には、藤田嗣治という変わり種も出てくるので、やはりどこか収まらないものがあるのだろうか。
「堅気の官吏の家から、文学・演劇に志すものが出たのは、ひとえに江戸・東京育ちの母親の感化だった。」
明治、大正という時代での芝居というものの存在感の大きさというのは、今日では想像することすら難しい様に思う。テレビはもちろんのこと、ラジオもまだ存在しない時代。映画もようやく産声を上げたばかりという時代の芝居というものが、娯楽の王者としての地位として、正に絶対的な王座に君臨していた時代だったと言える。その一方で、役者は人気はあっても社会的な地位は低く、演劇に携わるもの全般に共通して、社会からは低く見られていたのも事実だろう。そんな時代に、官吏の家に生まれて演劇の世界へ入るというのは、あまり普通のこととは思われなかっただろう。永井荷風も官吏の息子であり、彼の父は文学へ傾倒していく息子を嘆き続けたという。
「・・・・・五歳のとき、広島衛戍病院長の父が赴任地で死ぬと、母は子供たちをつれて東京麹町富士見町の持ち家に帰っている。「私はそれから中学を卒へるまで、ここで育つた」とあり、母の親しい友人に「武田のをばさん」がいて、その長男の乳母が画家武内桂舟の母だったことから、薫は桂舟の家に遊びに行くようになったとある。そこは硯友社の作家たちのたまり場だった。子供のころから尾崎紅葉、江見水蔭、弘津柳浪、泉鏡花らの顔をおぼえたというのはそのためである。母親は芸事が好きで、その交際範囲に出てくるのは、近くのインテリ階級の夫人たちだった。」
幼いうちに父親を亡くし、東京育ちの母親の元で育てられたことで、小山内薫という人物の成り立ちが少しずつ見えてくる。その意味では、木村莊太は官吏の家ではないものの、父親は不在に近い存在であり、どこか共通する雰囲気はその辺りから始まっているのだろうかとも思える。
「「十三年」(明治四十一年作)という作品は当時のことを回想していて、毎日のように母のもとにあつまる「家に用のない夫人連」のなかに、帝国大学教授のイギリス人の外妾、アメリカ公使館書記官の内縁の妻、陸軍監督夫人、騎兵中佐夫人、政治家夫人等々がいたと書かれている。「武田のをばさん」はアーネスト・サトウの妻であり、植物学者で日本山岳会創立発起人のひとり武田久吉の母にほかならない。薫の妹の岡田八千代は、父親の遺産、家作料、母の扶助料などで「父の死後、廿年余りを露頭にも迷はず、相当気楽に暮らして来た。・・・・・・母はお人好しで、鐘のあるまゝに人からも多く借り倒されたらしいし、江戸つ子の世話好きで、かなり無駄に金を遣つたらしい」と書いたが、明治の近代化のなかのこのような環境が小山内薫という人物を育てていったとも考えられる。」
明治の東京の中流家庭というものの有り様が、浮かんでくる様に思える。決して庶民とは違うレベルで存在しながら、アッパークラスとも違う位置付けである。こんな話を読んでいると、しばらく前に日本中が一億総中流などと言っていたものが、如何に勘違いであったのかがよく分かる。今日では格差の拡大で状況が変わってきているとはいえ、あの頃でも決して中流というレベルまでは到達できてなどはいなかった。そして、どうやらあの地点が戦後の社会が辿り着いた一つの頂点であった様でもあるのが悲しい。
こういった恵まれた家庭環境の中で育ってきたからなのか、どこか煮え切らない、優柔不断な印象を与える「大川端」の作者だが、明治人らしく直情的に行動する面も見せている。
「彼は一高にすすんでから失恋の経験をした。それがもとで内村鑑三の門をたたいている。」
ここでは、荒川放水路の建設を指揮した技師青山士とも出会っている。とはいえ、小山内が敬虔なキリスト教徒の道を歩むわけもなく、別の恋愛に失敗し、内村門下から遠ざかり、頽廃へと進んだと「自伝」に書いている。その頽廃の成果が「大川端」ということになる。
谷崎潤一郎は、小山内薫の後輩に当たる。
「二人の作家の接点が明治の東京であり、おなじ学校であり、あるいは下町にもあったわけだが、谷崎は先輩としての小山内に礼をつくしながらも、その作品をさほどには評価していない。・・・・・・・・小山内が文壇に打って出たころの作については「障子のところ、私は此れ等の作品を余り好まない」といい、赤門出のチャキチャキの秀才らしい新鮮味があり、才気煥発の趣きがあったが、ややだれ気味でほんのスケッチにすぎない、とかなりきびしい。」
「小山内薫も谷崎潤一郎も東京を舞台に作品を書きはじめた作家だった。その点では都会派の作家であり、東京人ならではの文学であった。しかし山の手育ち、下町育ちのちがいは歴然たるものがある。」
というあたり、著者の近藤氏も下町育ちだけに、山の手育ちに対してみな厳しくて、小山内が少々気の毒に思えてくる。とはいっても、どこか野暮ったさを秘めている、読んでいると隔靴掻痒という言葉も思い浮かぶ「大川端」の主人公の姿を想い起こすと、この辺りの指摘にも頷かざるを得ない。長谷川時雨の弟、虎之助に追い越されていくのもむべなるかなという気がしてしまう。とはいっても、小山内の業績が小説の評価で全て測れるものではもちろんなく、演劇という世界での活動に身命を文字通り賭していったのは言うまでもない。
「谷崎の文壇登場については、その『青春物語』にくわしい。小山内薫の傘下にあつまって第二次「新思潮」を創刊したことについて、谷崎は「われわれとして最も賢い方策であつた」と書いている。赤門出の作家は漱石一派をのぞいては微々たるもので、「ひとり小山内氏のみが文壇にも劇壇にも幅を利かせてゐたから、後進のわれわれがもし先輩を担ぐとすれば、この人を頼るより外はなかつた」とある。」
木村莊太は第一次新思潮の最終号で「新生」という作品を書き、デビューを飾っている。二代目木村荘平を継いだ荘蔵夫婦は文学好きであり、早世した曙の関係で硯友社の文人と親しかった。そんなことから、莊太は第一次「新思潮」に紹介される。そんなことから小山内薫とも親交を結ぶようになり、その縁を頼って第二次「新思潮」の創刊を目論む若手が、小山内と親しい莊太を訪ねたところから第二次「新思潮」が始まっていく。そこに谷崎潤一郎も加わることになり、莊太と谷崎は出会い、意気投合していく。谷崎は莊太よりも三歳年上なのだが、非常にウマが合ったようで、一時は連れだって遊んで歩いていたようだ。この辺りは、弟の荘八が岸田劉生と濃密な友情を育んでいたことと重なるようにも思えてしまう。
やがて、谷崎は文壇で確固たる地位を築き、多忙な売れっ子作家となっていく。
「「新思潮」の終刊とともに発表舞台は「スバル」「三田文学」や「中央公論」に移り、「三田文学」誌上で永井荷風の推讃をうけたことは、あまりに有名な文学史上の事実である。明治四十三年秋から四十四年秋にかけての出来事であった。」
谷崎は、こうして一流作家への階段を駆け上がっていく。
「この華々しいデビュー当時にあって、谷崎は小山内の反感を買ったというのだ。二つの小山内追悼文では、二人の間にちょっとした事件があってとか、「先生」が「さん」になったのにはちょっとしたいきさつがあるので、といいながらも。
「それといふのは、私の文壇への出方が可なりに早く華々しかつたので、何となくそれが癪にさはつて『谷崎の奴はいやに大家ぶつてゐる』といふような悪口をいつて歩いたらしい。故人の欠点を挙げるのも今では思ひ出の種であるからいふのであるが、若い自分の小山内君にはたしかにさういふ気のせまい女性的な一面があつた。大きな顔をしてゐればわれわれの親分として担がれていい人だのに、そんなことから逃げ出した者も少くなかつた。」
と書いた。そのいきさつをさらにこまやかに述べたのがのちの『青春物語』である。」
北荻三郎の「いろはの人びと」によれば、谷崎を評して「あいつは国文科きっての道楽者で、傲慢だし、だらしはないし、始末に困る奴だが、偕楽園という後ろ盾がついている。彼を同人に加えれば、偕楽園の笹沼が資金を出してくれるかもしれないよ。」という大貫雪之助の言で第二次「新思潮」に谷崎潤一郎は加えられたという。偕楽園とは、東京で最初の中華料理店で日本橋亀島町に創業されていたが、若主人の笹沼は谷崎の幼馴染みで、金銭面では親代わりのような存在であったという。そんな話を読んでいると、谷崎という男も一筋縄ではいかない印象であり、小山内に対しての酷評をそのまま受け取るのも小山内に気の毒に思えてしまう。
「谷崎は、小山内の生前には許されなかった弟子のひとりだというのだが、そこには山の手育ちのお坊ちゃん気質と下町生まれのはにかみやがうまくかみあわなかったとも考えられる。「私は自分の恩人であり、わが劇壇第一の功労者である故人に対して、不遜の評価を下したかも知れない。しかしかう云うことを書くのも、今にして故人を愛慕するの情に堪へないからである。故人は実に欠点だらけの人であつた。アラを捜せばいくらでもあつた。何よりもあれ程の才人でありながら、多数を統御する度胸と、落ち着きと、智謀とに欠けてゐた。・・・・・・・・・さう云う点では、弟子から云えば頼みにならない師匠であるが、見様に依つては、氏は後から来る弟子を追ひ越し追ひ越して、常に時代の先頭を切る溌剌たる青年を味方にしてゐたのである。氏が時代の進運と歩調を合わせて永久に若々しかつた所以は此処にあるのであらう」と谷崎は書いている。」
昨今は故人となった途端に、まるで善人100%でその人生を歩んできたかのような云いようが多いのだが、谷崎という人は決してただ先輩をこき下ろしているわけではないことが、よく分かる。こんな言い回しをされているのを見て、小山内は天上から苦笑していたのだろうか?的確な分析と、故人に対する愛情が籠められていることがよく分かる一文だと思う。谷崎という人は確かに一筋縄ではいかない男であり、自らに正直であり続けた男なのだろう。東京の下町育ちでありながら、関東大震災後の新しい東京を受け入れることをしなかったのも、彼の美意識ならではと言えるのかもしれない。
「浜町公園のこうから蠣浜橋跡をすぎ、甘酒横丁を歩く。人形町の大通りをわたり、すこしすすんだところの右側に塚越ビルという建物があって、地下駐車場入口の壁に「谷崎潤一郎生誕の地」の碑がはめこまれている。『幼少時代』その他の文章でくりかえし読んできた「谷崎活版所」の跡地であった。私は好んで人形町界隈を散歩するが、そのたびにこの碑の前で立ちどまってみる。「黒漆喰の土蔵造りの家」の面影は完全に失せ、印刷機械の響きもない。しかしそこに立ちどまるだけで、忽然として在りし日のかたちがみえ、音がきこえてくるようであった。」
親子丼で有名なたまひでと言う店の並び、少し云った辺りに谷崎潤一郎生誕の地はある。震災で焦土と化し、かつての面影は完全に失われてしまったところなのだが、それでも何故町を歩くのかと言われれば、正に在りし日の面影を追い求めているからだとしか言いようがない。変わり果てた町であっても、かつてこの場所がそうだったのかとか、誰かもこの道を歩いたのだろうかと思わされることで、時の流れを越えて思いを巡らせることができる。町の区画さえせめて残されていれば、過去をたどることはできるのだと思う。小山内が歩いた中洲、谷崎の育った人形町。そんな痕跡が数多いことが、都市の財産であるのではなかろうか。過去の町並を跡形もなく消滅させて、完成した瞬間から古びていく超高層ビルには、都市としての奥行きがないのだと思う。




















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます