さて、今回は書籍の紹介。池の端界隈~木村東介著青英舎刊を取り上げてようと思う。著者は非常にユニークな人物である木村東介で、湯島の羽黒洞の主人といえば、分かる人には分かる人物でもある。湯島の羽黒洞は、このブログの初期に文京区湯島の回に登場している。

羽黒洞は民俗美術商というほかにない存在なのだが、それには主人の木村東介という人物の強烈なキャラクターが大きな意味合いを持っている。明治34年山形の生まれ、弟は建設大臣まで務めた政治家の木村武雄である。平成4年に90歳で亡くなられている。元々激しい方であったようで、上京してから昭和初期に国士を気取っていたという。下谷辺りで暴れ回っていたようで、その武勇伝もこの本の面白さでもある。その一党のそれぞれについて書かれているのを読んでいるのも面白いのだが、その背景の東京の町の様子が窺えるのが何よりも貴重なのだ。
東介氏は抗争の挙げ句に足を洗い、美術商へと転身する。最初は柳宗悦氏のところに出入りしていたという。柳宗悦と言えば、駒場にある日本民藝館ということになる。私の母は戦前の一時、日本民藝館の直ぐ近くにあった母方の実家で生活していたことがある。ひょっとするとまだ幼かったうちの母親と東介氏は、駒場ですれ違ったことがあるかもしれない。などと想像しながら読んでいると、なかなか引き込まれてしまう。
東介氏の著書は何冊もあるのだが、現在手に入れることが出来るものは多くはない。東介氏の子孫お方が継承されて羽黒洞は健在なので、ここから在庫のあるものは手に入れることが出来る。私は有栖川公園の東京都立中央図書館で手に入らないものは全て読んできた。
また、この人物に私が興味をひかれたもう一つのことが、このブログで再三取り上げてきた木村荘八との関わりが深いことである。荘八の生前から、東介氏は世間に荘八の本当の価値をもっと認めさせてやりたいと強く願い、それを実現すべく手を打っていたそうだ。木村荘八という人は世間的には名を知られていたものの、絵の評価としてはあまり高値の付く画家ではなかったということだ。本人の認識ともギャップがあったようで、晩年の荘八はその辺りに悩みを抱えていたようでもある。荘八の死後も東介氏はその絵の価値を世間に認めさせていくべく展覧会を企画したりしている。その辺りの内幕と荘八との関わりについては、「ランカイ屋憂愁~鬼才荘八追想記」という小冊子にまとめられている。
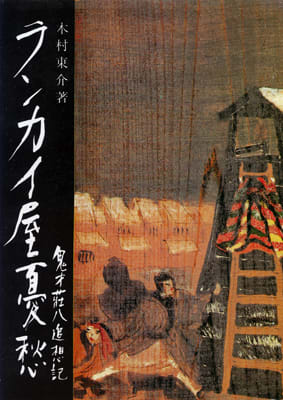
ランカイ屋とは、東介氏の韜晦を含んだ自称であり、展覧会屋という意味である。近年になって荘八を深く知るようになった私には、目から鱗という印象の話であり、また荘八の晩年を思うと胸が痛む内容でもある。
大正っ子シリーズの著者達とは年代から行くと少し上になるのだが、この年代差によって見えている世間が違っているところも含めて、昭和の初め頃の東京の町、社会の有様が非常に面白く読める。綺麗事ではない陰の部分も含めた話がカラリとした持ち味で語られていく。

羽黒洞は民俗美術商というほかにない存在なのだが、それには主人の木村東介という人物の強烈なキャラクターが大きな意味合いを持っている。明治34年山形の生まれ、弟は建設大臣まで務めた政治家の木村武雄である。平成4年に90歳で亡くなられている。元々激しい方であったようで、上京してから昭和初期に国士を気取っていたという。下谷辺りで暴れ回っていたようで、その武勇伝もこの本の面白さでもある。その一党のそれぞれについて書かれているのを読んでいるのも面白いのだが、その背景の東京の町の様子が窺えるのが何よりも貴重なのだ。
東介氏は抗争の挙げ句に足を洗い、美術商へと転身する。最初は柳宗悦氏のところに出入りしていたという。柳宗悦と言えば、駒場にある日本民藝館ということになる。私の母は戦前の一時、日本民藝館の直ぐ近くにあった母方の実家で生活していたことがある。ひょっとするとまだ幼かったうちの母親と東介氏は、駒場ですれ違ったことがあるかもしれない。などと想像しながら読んでいると、なかなか引き込まれてしまう。
東介氏の著書は何冊もあるのだが、現在手に入れることが出来るものは多くはない。東介氏の子孫お方が継承されて羽黒洞は健在なので、ここから在庫のあるものは手に入れることが出来る。私は有栖川公園の東京都立中央図書館で手に入らないものは全て読んできた。
また、この人物に私が興味をひかれたもう一つのことが、このブログで再三取り上げてきた木村荘八との関わりが深いことである。荘八の生前から、東介氏は世間に荘八の本当の価値をもっと認めさせてやりたいと強く願い、それを実現すべく手を打っていたそうだ。木村荘八という人は世間的には名を知られていたものの、絵の評価としてはあまり高値の付く画家ではなかったということだ。本人の認識ともギャップがあったようで、晩年の荘八はその辺りに悩みを抱えていたようでもある。荘八の死後も東介氏はその絵の価値を世間に認めさせていくべく展覧会を企画したりしている。その辺りの内幕と荘八との関わりについては、「ランカイ屋憂愁~鬼才荘八追想記」という小冊子にまとめられている。
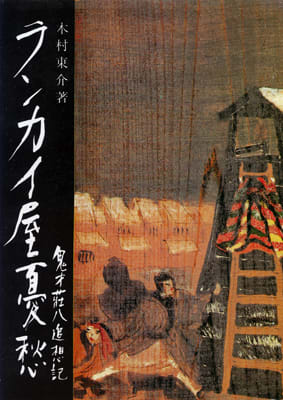
ランカイ屋とは、東介氏の韜晦を含んだ自称であり、展覧会屋という意味である。近年になって荘八を深く知るようになった私には、目から鱗という印象の話であり、また荘八の晩年を思うと胸が痛む内容でもある。
大正っ子シリーズの著者達とは年代から行くと少し上になるのだが、この年代差によって見えている世間が違っているところも含めて、昭和の初め頃の東京の町、社会の有様が非常に面白く読める。綺麗事ではない陰の部分も含めた話がカラリとした持ち味で語られていく。




















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます