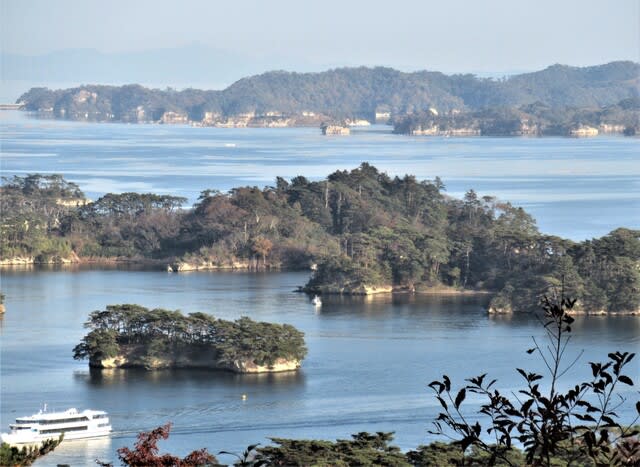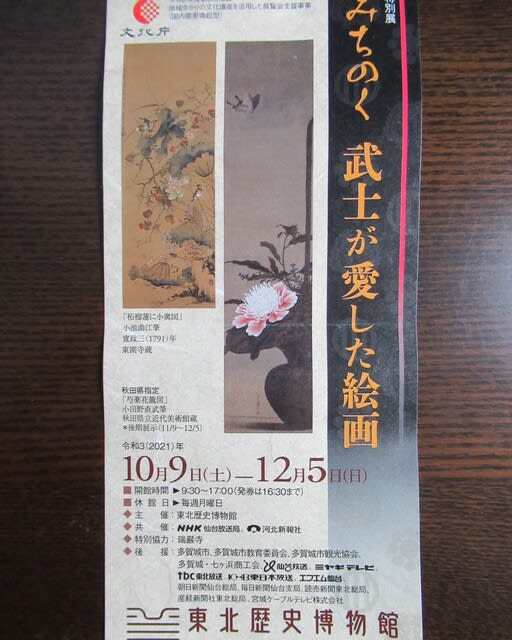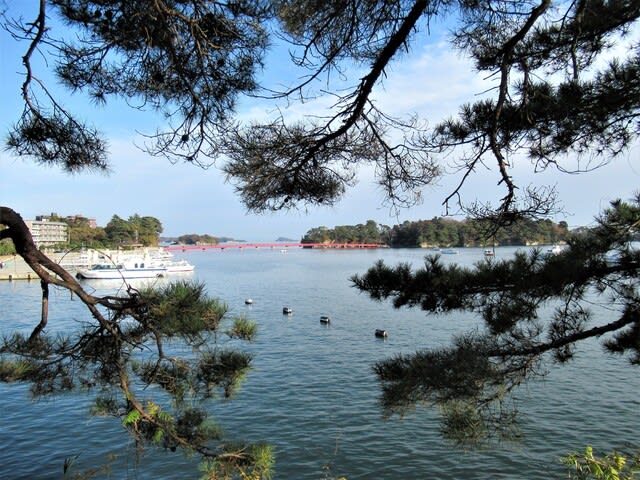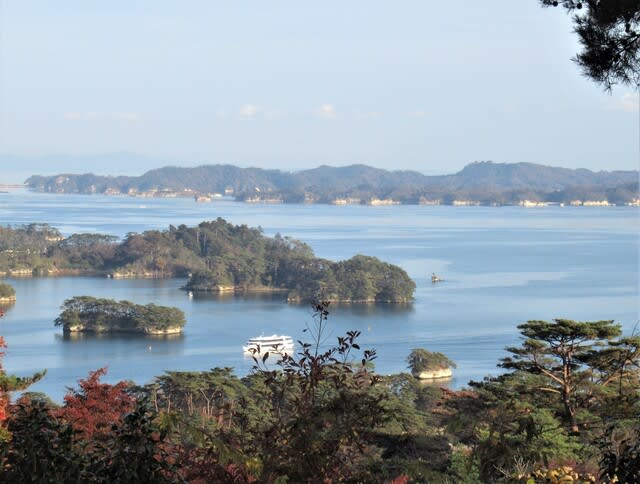一昨日、満開の桜を楽しんできました。
みちのくにも春と、桜の開花宣言するも間もなく、当地方も連日の夏日でいきなり満開となりました。
みちのくにも春と、桜の開花宣言するも間もなく、当地方も連日の夏日でいきなり満開となりました。

半日コースの慌ただしい日程でしたが2カ所を訪ねました。
ここは当県南部の角田市郊外にある高倉公園。
ここは当県南部の角田市郊外にある高倉公園。
当県人でも知る人は少ないでしょう。

古刹高蔵寺を中心に市が公園化したもの。
何度か訪れていますが、桜の季節に訪れるのは、二度目か三度目。
昔からみると格段に整備されました。
公園の入り口から道路沿いに桜並木になっています。
公園の入り口から道路沿いに桜並木になっています。

道路脇には小さな川が流れており、蛍の里としての整備も行われています。

桜は大木、古木はなく、小規模な公園です。
ですが、何といっても静かでゆったり出来るのが良い。
他の名所のように人混みの中を歩く必要もなく、コロナ禍でも気にせず楽しめます。
他の名所のように人混みの中を歩く必要もなく、コロナ禍でも気にせず楽しめます。

この小川に桜の枝が垂れた風情もいい。


このソメイヨシノが一番大きな木のようです。

ベニシダレも見頃になっていました。


園内には古民家で国の重文に指定されている旧佐藤家住宅も移築されています。
江戸中期に建てられたものと言います。

この整備された庭園の向こうに見えるのが、古刹高蔵寺の現在の本堂。

国の重文に指定されている同寺の阿弥陀堂はこの先にあります。

開山1200年ののぼりが立てられていました。

参道を歩くとほどなく阿弥陀堂が見えてきます。

この佇まいが素晴らしい。
この阿弥陀堂は当県最古の木造建築物で、平安時代の1177年に建立されたと伝えられます。
この阿弥陀堂は当県最古の木造建築物で、平安時代の1177年に建立されたと伝えられます。

当県人でも知らない人が多いのではないでしょうか。
お堂の中には阿弥陀如来像が安置されていますが、普段拝観することは出来ません。
このお堂を一層引き立てているのが境内の巨木群。
このお堂を一層引き立てているのが境内の巨木群。
参道の石段を登ったところにある杉の巨木。

しめ縄が掛けられています。
幹分れしていますが、根元の幹周りは8mと巨大。小生がこれまで見た中では、3本の指に入ります。
幹分れしていますが、根元の幹周りは8mと巨大。小生がこれまで見た中では、3本の指に入ります。

こちらは榧(かや)の巨木。
樹齢は300年と言います。多少空洞化しているのではと感じました。

この境内の雰囲気を味わえるので当地を訪ねる気になるのかもしれません。
一昔前、ここをモチーフに墨画会出品作を描きました。すでに記録済みですが再掲。

この後は白石川堤一目千本桜を見に行きました。それは明日。