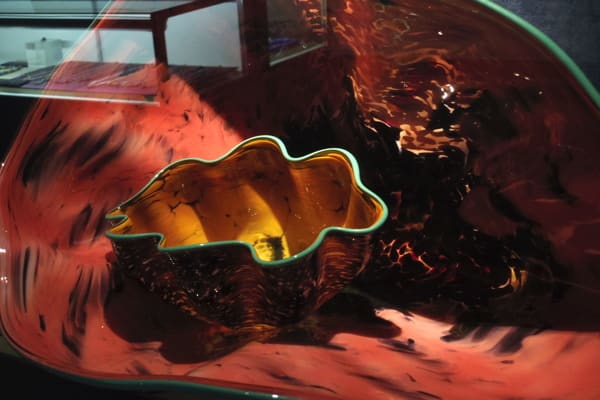11月になりましたね。急に寒くなったりあったかくなったり、台風が来たり。
でも昨日は晴れてあったかく、とても気持ちがいい休日でした。
がんばって江ノ島まで足をのばしてみましたので、よろしければちょろっとおつきあいください。

とはいっても江ノ島へは渡らず。
昨日はとにかく砂浜の海が見たい!!!と森のなかまをせっついて行ってきたんです。
休日の江ノ電は混み方がすごいので、大船駅からモノレールに乗って来たんですが、
こちらは空いててゆったり座れ、景色もなかなか新鮮でした。

さすがにもう海水浴のシーズンではないので、海辺にいるのはサーファーの人やヨット、釣りの人たち、
それに同じく砂浜を散策する人たちのようです。

このちっちゃい姉妹、赤い服のお姉ちゃんは服をぬらさないでいましたが、
妹くんの方は全身びしょぬれになってました・・・風邪ひかないでね〜


浜辺に打ち上げられていたのは海草の茎のようです。昆布、、、みたいだけど違うかな。
さわってみるとちょっとぷよぷよしていました。

強い日差しに波がきらきら

昨日なんかはきっとサーフィン日和だったんでしょうね。波に乗れたら気持ちいいだろうなあ。
この辺りは腰越海岸というそうです。

腰越海岸から一回道路に上がって少し進むと、もう少し砂浜の幅が狭い海岸が見えてきました。
この辺は七里ヶ浜というそうです。

この写真だとちょっとわかりにくかもですが、七里ヶ浜は腰越海岸よりもかなり波が荒いようで、
ざぶーんざぶーんと激しい音をたてて打ち寄せていました。

ふしぎなオブジェがあるなと思ったら、護岸工事用に組み立てられたやぐらのようです。
サビで赤い・・!森のなかまが喜んでいました。なんで。


こうして見るとまるで神殿か何かのようですよね。

この辺は海岸通り沿いに江ノ電も走っているのですが、意外にあまりに近すぎていい感じに撮れず。。
けれどこの鎌倉高校前駅の踏切前には沢山の人がいて、みんなスマホやカメラを構えていました。
しかも聞こえてくる言葉はほとんど中国語。なんで???

ほら、交通整理の人までいるんです。あとで立ち寄ってコーヒー飲んだお店の人に聞いたみたところ、
SLUM DUNKという人気アニメのオープニングに出てくる場所なんだそうで、
中国や台湾から来たファンの人たちが撮影してゆく人気ポイントになっているんだそうです。へえ〜

ちなみにこの話を教えてくれたコーヒー屋さんは、長谷駅から大仏へ向かう途中の道の右手にあるお宅の、
庭先に止めてあるワゴン車がお店になっているかわいいお店でした。
ご主人がドリップでいれてくれる本格的なおいしいコーヒーが三百円で飲めますよ

この後七里ヶ浜の駅から江ノ電に乗って長谷駅へ。目的は

そう、鎌倉の大仏さまです。にゃんと森のなかまも私もまだ見たことがなかったのでした。
それにしても駅からの人の流れの多いこと・・!鎌倉は古い町だから道が狭いし、しょうがないんですよね。
平日に来られればそれが一番いいんいだけどな。。。

大仏さまの背中には扉がついてて空いていました。
ちなみに中も拝観できるそうですが、大変な行列だったので昨日はやめておきました。
このあと、さっきのコーヒー屋さんで聞いておいた近道を使って鎌倉駅まで。
距離は少々あったけど、人の少ない通りで鎌倉駅まで行きつけました。
昨日は三週続けての雨のあとの晴れで、休日にしても人出が多かったんだそうです。
これから年末にかけて、なんとなく慌ただしい気持ちになりそうですが、
いつも行ってるみなとみらいの港の海とも違って、砂浜の海でのんびりできました。
やっぱり海はいいね〜