http://drumscotom.blog29.fc2.com/blog-entry-928.html
【こころの薬30】 中村久子の生き方
いまの日本は、100年に一度の危機といわれ、
暗いニュースばかり流されて、
自分の責任でもないのに、つらい境遇におかれていると感じている方が、
さらに、これから日を追って増えてくるかもしれません。
そこで年頭にあたって、すこしでも元気が出るように
中村久子さんの強い強い生き方をご紹介しようと思います。
ちょっと長くなりますが、最後までお付き合いくだされば幸いです。
ある ある ある
みんな ある
さわやかな 秋の朝
これは中村久子さんが40歳のときに書いた詩の一節です。
「ある ある ある」とは、何が「ある」というのでしょうか?
それは彼女の生き方と大きく関係しているのです。
中村久子さんは、わずか4歳のときに両手両足を切断し、
7歳で父親を失い貧乏の中で、「ない、ない、ない」ずくしの生活を余儀なくされます。
しかし20歳で、見世物小屋の住み込み芸人となって
国の援助を1円たりとも受けずに、明るくたくましく生き抜いた方です。
晩年、その生き方に感銘する人が増え
まわりから「先生」と呼ばれ、天皇陛下に拝謁するような存在になります。
1968年に72歳で亡くなられたのですが、没後40年、
いまとなっては、彼女について知る人は少ないようです。

(↑裁縫をする中村久子。「だるま娘」の芸名で見世物小屋で裁縫する姿を見せていた)
中村久子(以下敬称略)は、明治30年に岐阜高山の畳職人の長女として生まれた。
両親は裕福ではなくても、結婚11年ぶりにさずかった久子を可愛がって育てたという。
ところが3歳のとき、突発性脱疽にかかり、命を守るために4歳で両手両足を切断。
7歳のとき、久子を必死で守ってきた父が病死。母の実家で育てられることになる。
しかし両手両足がないために小学校入学もままならない。
生活のために再婚した母あやは、
「何か一生食べていけるものを身につけてやらねば」と決心する。
(以下は黒瀬昇次郎「中村久子の生涯」春秋社1989刊より、一部引用)
母あやは11歳になった久子に、着物の「ほどきもの」を言いつけた。
「どうやってほどくんですか?」途方にくれて母に聞いても、
「自分で考えてやりなさい」ととりつくしまがない。
「人間は働くために生まれてくる。できないとは何事か」と。
一本の留め糸を切るのにも気の遠くなるほどの時間に、久子はかんしゃくを起こす。
しかし母は容赦なく「やればできる」とハサミを指のないまるい手にのせた。
悪戦苦闘が何日もつづいて、ついに口にくわえたハサミで留め糸をパチンと切った。
「わあ、切れた!」涙が頬を流れた。
一人で「ほどきもの」ができる。大きな喜びだった。
自分の力の発見であった。
すると母は、
「女の子はお針がいちばん大事じゃ。なんとか、あんたも針がもてたらいいのに」
「そうだ、私の大事なお人形に着物をぬって着せてあげたい!」
お針を口で使う稽古をしようと、久子の心がはずんだ。
針の穴に糸をどう通すか、運針、結び玉をどうむすぶか、久子の工夫は毎日つづく。
「手なし、足なしに何ができるものか」周囲の心ないひやかしにも、決して屈しなかった。
そしてとうとうつばでベトベトになった小さな着物を縫いあげた。
それから7年、18歳の久子は、女物の袷(あわせ)を2日足らずでしあげるようになり
編み物は一日に毛糸8オンスは楽勝となっていたのだ。

(↑久子が縫った人形の前で。写真はいずれも黒瀬昇次郎「中村久子の生涯」から)
両手両足がないのに器用に裁縫をこなす久子に、
当時の見世物小屋の興行師たちが目をつけた。
そして久子20歳のとき、小屋住み込みの芸人となる。
久子の芸は、好奇の目で集まった客の前で、
裁縫する姿や切り紙細工を見せることだった。
いまならスカウトだが、当時は前金で年季をしばる身売りだ。
後妻となった母、そして前夫の子という自分の立場を考えての、
自立するためのやむをえない決断であったろう。
当時(大正3年頃)でも、生活困窮者や身体障害者には
「扶助料」という国家の最低保障があった。
しかし久子は受給を拒んだ。
「お上の扶助料が将来の自立のための資金になるのならいいが、
自立の見通しもたっていないままズルズルいただくなら、甘えから抜け出せなくなる」
なんとか自分の力で生きてみせる!と心に決めたと、後に出版した自伝に書いている。
親戚には警察署長もいれば教員もいて猛反対をしたが、自立の意思は堅かった。
「だるま娘」という芸名で、見世物小屋の芸人生活が始まると、
客の野次にポッと頬を赤らめ、どことなく品のある芸に人気が出て、
全国や台湾満州まで巡業するようになる。
そして24歳、身売りの年季が明ける年に大きな出来事が3つおこる。
ひとつは母あやの死去であり、
ひとつは、婦人雑誌の懸賞「前半生を語る」に応募、
一座が寝静まってから、口にくわえたペンで書いた原稿用紙80枚が一等当選する。
久子が見世物小屋の賎(いや)しい芸人ではなかったことを示すエピソードのひとつだ。
そして、このことが晩年の久子を大きく変えることになる。
さらにひとつは結婚である。
相手は何かとお世話をしてくれた実直な男、中谷雄三だった。
しかし雄三とは3年で死別するが、二人の子どもをもうける。
年季が空け自由の身になった久子は「久子一座」を率いたり、
他の興行師と組んで、2人の子どもに高等教育をするため46歳まで全国巡業をつづける。
その間に、前記の雄三の他に結婚を3回するが、病死、離婚で別れ、
9歳年下の中村敏雄と4度目の結婚、生涯を共にする。
46歳で芸人をやめた久子は、一等入選「半生記」の縁から、講演依頼が次第に増えて
夫の敏雄と次女の富子におんぶされながら全国を回るようになる。
「宿命に勝つ」「生きる力を求めて」「私の越えて来た道」を出版。
ヘレンケラーとも3度会談、
「日本のヘレンケラー、不自由を知らぬ明朗で強い二児の母」
「不具の女が口でつくった人形に感激の涙」などと大きく報道された。
以来、ラジオ番組で厚生大臣や宗教家などと対談したり活動の場が広がっていく。
65歳のときに、身体障害者の模範として厚生大臣賞受賞。
そして宮中に参内し天皇陛下からお言葉を賜る。
宮中参内のときの思い出を、久子はこう話している。
「若いときに扶助料というお金をいただかなくてほんとうに良かった、
としみじみ思いました。
そのお金いただいてもし使っていたら、天皇皇后両陛下の前に出ましても、
お顔をまともに仰ぐことはできなかったと思います。
”いただかんでよかった”
(たとえ世間から見下されるような)見世物小屋の住人でも、
働かしてもらったことは大きな幸せだった」と。
1968年72歳のとき脳溢血で倒れ自宅で死去。
両手両足がなくても、国の補助をうけず、明るくたくましく生き抜いた生涯であった。
健常者のわれわれ、
もって瞑すべしとはこのことでしょうか?
*お時間のある方、
冒頭の詩の全文と
「中村久子の生涯」の著者、黒瀬昇次郎氏について…
「ある ある ある」
さわやかな
秋の朝
「タオル取ってちょうだい」
「おーい」と答える
良人がある
「はーい」とゆう
娘がおる
歯をみがく
義歯の取り外し
かおを洗う
短いけれど
指のない
まるい
つよい手が
何でもしてくれる
断端に骨のない
やわらかい腕もある
何でもしてくれる
短い手もある
ある ある ある
みんなある
さわやかな
秋の朝
「私の越えて来た道」1955刊より
暗いニュースばかり流されて、
自分の責任でもないのに、つらい境遇におかれていると感じている方が、
さらに、これから日を追って増えてくるかもしれません。
そこで年頭にあたって、すこしでも元気が出るように
中村久子さんの強い強い生き方をご紹介しようと思います。
ちょっと長くなりますが、最後までお付き合いくだされば幸いです。
ある ある ある
みんな ある
さわやかな 秋の朝
これは中村久子さんが40歳のときに書いた詩の一節です。
「ある ある ある」とは、何が「ある」というのでしょうか?
それは彼女の生き方と大きく関係しているのです。
中村久子さんは、わずか4歳のときに両手両足を切断し、
7歳で父親を失い貧乏の中で、「ない、ない、ない」ずくしの生活を余儀なくされます。
しかし20歳で、見世物小屋の住み込み芸人となって
国の援助を1円たりとも受けずに、明るくたくましく生き抜いた方です。
晩年、その生き方に感銘する人が増え
まわりから「先生」と呼ばれ、天皇陛下に拝謁するような存在になります。
1968年に72歳で亡くなられたのですが、没後40年、
いまとなっては、彼女について知る人は少ないようです。

(↑裁縫をする中村久子。「だるま娘」の芸名で見世物小屋で裁縫する姿を見せていた)
中村久子(以下敬称略)は、明治30年に岐阜高山の畳職人の長女として生まれた。
両親は裕福ではなくても、結婚11年ぶりにさずかった久子を可愛がって育てたという。
ところが3歳のとき、突発性脱疽にかかり、命を守るために4歳で両手両足を切断。
7歳のとき、久子を必死で守ってきた父が病死。母の実家で育てられることになる。
しかし両手両足がないために小学校入学もままならない。
生活のために再婚した母あやは、
「何か一生食べていけるものを身につけてやらねば」と決心する。
(以下は黒瀬昇次郎「中村久子の生涯」春秋社1989刊より、一部引用)
母あやは11歳になった久子に、着物の「ほどきもの」を言いつけた。
「どうやってほどくんですか?」途方にくれて母に聞いても、
「自分で考えてやりなさい」ととりつくしまがない。
「人間は働くために生まれてくる。できないとは何事か」と。
一本の留め糸を切るのにも気の遠くなるほどの時間に、久子はかんしゃくを起こす。
しかし母は容赦なく「やればできる」とハサミを指のないまるい手にのせた。
悪戦苦闘が何日もつづいて、ついに口にくわえたハサミで留め糸をパチンと切った。
「わあ、切れた!」涙が頬を流れた。
一人で「ほどきもの」ができる。大きな喜びだった。
自分の力の発見であった。
すると母は、
「女の子はお針がいちばん大事じゃ。なんとか、あんたも針がもてたらいいのに」
「そうだ、私の大事なお人形に着物をぬって着せてあげたい!」
お針を口で使う稽古をしようと、久子の心がはずんだ。
針の穴に糸をどう通すか、運針、結び玉をどうむすぶか、久子の工夫は毎日つづく。
「手なし、足なしに何ができるものか」周囲の心ないひやかしにも、決して屈しなかった。
そしてとうとうつばでベトベトになった小さな着物を縫いあげた。
それから7年、18歳の久子は、女物の袷(あわせ)を2日足らずでしあげるようになり
編み物は一日に毛糸8オンスは楽勝となっていたのだ。

(↑久子が縫った人形の前で。写真はいずれも黒瀬昇次郎「中村久子の生涯」から)
両手両足がないのに器用に裁縫をこなす久子に、
当時の見世物小屋の興行師たちが目をつけた。
そして久子20歳のとき、小屋住み込みの芸人となる。
久子の芸は、好奇の目で集まった客の前で、
裁縫する姿や切り紙細工を見せることだった。
いまならスカウトだが、当時は前金で年季をしばる身売りだ。
後妻となった母、そして前夫の子という自分の立場を考えての、
自立するためのやむをえない決断であったろう。
当時(大正3年頃)でも、生活困窮者や身体障害者には
「扶助料」という国家の最低保障があった。
しかし久子は受給を拒んだ。
「お上の扶助料が将来の自立のための資金になるのならいいが、
自立の見通しもたっていないままズルズルいただくなら、甘えから抜け出せなくなる」
なんとか自分の力で生きてみせる!と心に決めたと、後に出版した自伝に書いている。
親戚には警察署長もいれば教員もいて猛反対をしたが、自立の意思は堅かった。
「だるま娘」という芸名で、見世物小屋の芸人生活が始まると、
客の野次にポッと頬を赤らめ、どことなく品のある芸に人気が出て、
全国や台湾満州まで巡業するようになる。
そして24歳、身売りの年季が明ける年に大きな出来事が3つおこる。
ひとつは母あやの死去であり、
ひとつは、婦人雑誌の懸賞「前半生を語る」に応募、
一座が寝静まってから、口にくわえたペンで書いた原稿用紙80枚が一等当選する。
久子が見世物小屋の賎(いや)しい芸人ではなかったことを示すエピソードのひとつだ。
そして、このことが晩年の久子を大きく変えることになる。
さらにひとつは結婚である。
相手は何かとお世話をしてくれた実直な男、中谷雄三だった。
しかし雄三とは3年で死別するが、二人の子どもをもうける。
年季が空け自由の身になった久子は「久子一座」を率いたり、
他の興行師と組んで、2人の子どもに高等教育をするため46歳まで全国巡業をつづける。
その間に、前記の雄三の他に結婚を3回するが、病死、離婚で別れ、
9歳年下の中村敏雄と4度目の結婚、生涯を共にする。
46歳で芸人をやめた久子は、一等入選「半生記」の縁から、講演依頼が次第に増えて
夫の敏雄と次女の富子におんぶされながら全国を回るようになる。
「宿命に勝つ」「生きる力を求めて」「私の越えて来た道」を出版。
ヘレンケラーとも3度会談、
「日本のヘレンケラー、不自由を知らぬ明朗で強い二児の母」
「不具の女が口でつくった人形に感激の涙」などと大きく報道された。
以来、ラジオ番組で厚生大臣や宗教家などと対談したり活動の場が広がっていく。
65歳のときに、身体障害者の模範として厚生大臣賞受賞。
そして宮中に参内し天皇陛下からお言葉を賜る。
宮中参内のときの思い出を、久子はこう話している。
「若いときに扶助料というお金をいただかなくてほんとうに良かった、
としみじみ思いました。
そのお金いただいてもし使っていたら、天皇皇后両陛下の前に出ましても、
お顔をまともに仰ぐことはできなかったと思います。
”いただかんでよかった”
(たとえ世間から見下されるような)見世物小屋の住人でも、
働かしてもらったことは大きな幸せだった」と。
1968年72歳のとき脳溢血で倒れ自宅で死去。
両手両足がなくても、国の補助をうけず、明るくたくましく生き抜いた生涯であった。
健常者のわれわれ、
もって瞑すべしとはこのことでしょうか?
*お時間のある方、
冒頭の詩の全文と
「中村久子の生涯」の著者、黒瀬昇次郎氏について…
「ある ある ある」
さわやかな
秋の朝
「タオル取ってちょうだい」
「おーい」と答える
良人がある
「はーい」とゆう
娘がおる
歯をみがく
義歯の取り外し
かおを洗う
短いけれど
指のない
まるい
つよい手が
何でもしてくれる
断端に骨のない
やわらかい腕もある
何でもしてくれる
短い手もある
ある ある ある
みんなある
さわやかな
秋の朝
「私の越えて来た道」1955刊より










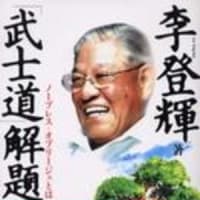

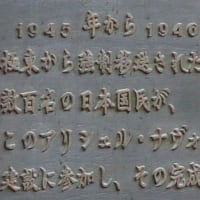




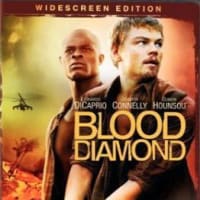
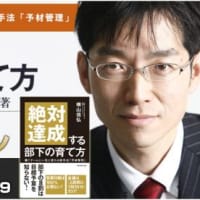
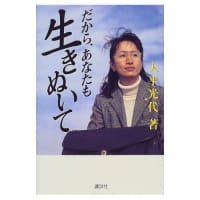
中村久子さんの生き方を
あらためて読ませていただき
生きていく強さに心うたれました。