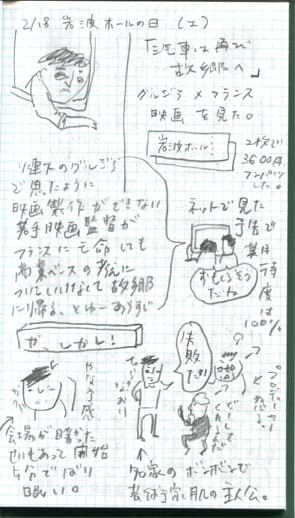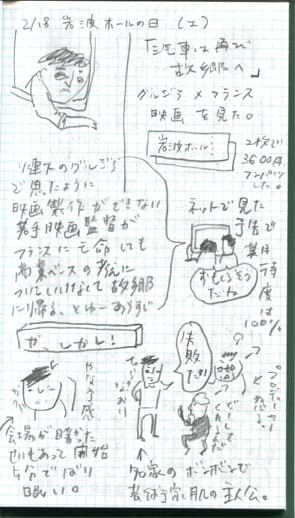最高記録ぐらい長く書いたのに、、、消えた。
すっごいショック。ショック。。。
まぁ、気を取り直して。
やっとこさエッセイが終わり、久々の更新。
で、今日はエッセイに書いたKEN LOACHという監督の、
KES(邦題少年と鷹)とSWEET SIXTEENという映画のはなし。
このken loachという監督、イギリス映画の中の社会派巨匠で、
フォーカスをいつも労働者階級や、社会的弱者にあてて映画を
撮っている人。
今回扱ったKESは69年に制作された彼の初期の作品で、
イギリス名映画7位にも(多分)ランキングされているもの。
ヨークシャーの労働者階級の15歳の男の子が、
学校でも、家庭でも理不尽な思いをしながらすごしているときに、
修道院の庭からパクってきた鷹の赤ちゃんを育て始める。
ひどい学校(先生は自分勝手で、労働者階級の生徒を見下す。
体罰も続いていて、授業も適当。生徒のケアも会ってないようなもの)
と愛のない家族(すぐ殴る炭鉱で働く兄貴と、
夕飯にフライドポテトのための小銭を渡してパブに繰り出す母親)
の間で唯一自由を感じれるのがその鷹の世話をしているときだった。
ただ、その時間も、怒った兄貴が鷹を殺したことでおわってしまう。
さらに中学校を終えた彼には炭鉱で働くという現実も待っている。
(成績が良くない限り、何か特別なスキルがない限り、
その町ではそれが当たり前となっている。)
映画はその鷹を庭に埋めるシーンでおわり、
見終わった後にはなんともいえないもどかしさが残る。
60年代のイギリスの田舎、労働者階級の生活を
見るのにはうってつけ。興味があったら是非どうぞ。
こんな理不尽でいいのか!?という憤り爆発でしょう。
ちなみに彼らが喋っているのがヨークシャーなまりの英語。
このサイトさん↓にアクセスすると本物のヨークシャー弁が聞けます。
http://www.barnsleylife.com//tonythepitpony.htm
で、もう一つがsweet sixteen。
コレもKESとおなじ15歳の労働者階級の男の子を主人公にした
KEN LOACHの近作(たしか2002年)。
舞台はスコットランドの廃れた港町。
主人公のliamは学校に行かないで9ヶ月がたち、友達の
pinballと安い煙草を売り歩いて小銭を稼ぐ。
母親は彼氏の罪をかぶって刑務所にて服役中、家にはその
薬の売人の彼氏と、実の祖父の3人くらしだが、liam はそこを追い出され、
子供と2人で住む、姉の下へ居候する。彼は母親が出所した後、
家族4人でやり直すべく、そのために川辺にあるキャラバンを買おうと計画し、
pimball といっしょに母親の彼氏から薬を盗んでさばきはじめる。
お金も集まり、キャラバンもとうとう手に入れ、
母親の出所日がきた。しかし、出所祝いパーティの翌日、母親は
彼氏の下へいってしまい、仲たがいをしたpimballはジャンキーがたまる
公営住宅で同じように薬でベロベロに。
我を忘れた彼はその彼氏をナイフで刺してしまう。
最後に逃げた海辺で姉からの電話が入る。警察も捜している。
そこで映画はおわる。
暗い。そしてろくでなしの大人ばかり。
でも今のイギリスの一面をすごく反映している作品。
人口のだいたい25パーセントが
この労働者階級に属しているといわれているんだけど、
舞台となっているスコットランドは、トレインスポッティングを
みてもわかるとおりに、薬と貧困の問題が
特にひどい。エジンバラはヨーロッパの中でHIVの感染率が一番高いし、
80年代以降、薬も南に比べて本当に蔓延している。
発展途上国の貧しさとはまたべつのもの。
ロンドンはこれほどでもないけど、やはり労働者階級って言うのは
もちろん存在していて、それは単に差別だっていうのとはまた違う。
話がややこしくなるし、私自身もまだ全然つかみきれてないので、
日本に帰ったときに(笑)日本語でちゃんと勉強したいと
思います。あはは。
まぁ、とにかく、機会があったら見てみてください。
素顔のイギリス、だと思います。
お茶の時間なんてどこへやら。