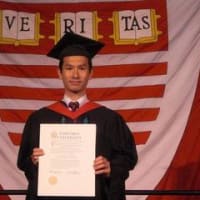「なぜ日本の市民社会(民間非営利セクター)は振るわないのか?」
「なぜ日本の民間非営利セクターに人と金が回らないのか?」。
今日の記事ではJohns Hopkins(ジョンス・ホプキンス)大学のCenter for Civil Socitey Studies(市民社会研究所)が取りまとめたレポート「Global Civil Society Overview」により改めて浮かび上がったこの課題と向き合うべく幾つかラフな仮説を立てて考えていきたいと思います。
仮説1:働きすぎな日本人
僕自身のニューオリンズでの経験や、PAE(Policy Analysis Exercise)のクライアントであるCommon Impactの提供するサービスからも見て取れるとおり、民間非営利セクターの継続的な活動を支えるのがボランティア活動。そして、日本人のボランティア活動へのコミットメントが国際的に見て極めて低い水準であることは前回、前々回の記事でも触れたとおりですが、恐らくその最大の理由は、「日本人が働きすぎなこと」ではないでしょうか?つまり、
「ボランティアもいいけど、現実問題、忙しすぎてそんな暇ないんだよね・・・」
ということ。
こちらは社会事情データ図録のサイトに掲載されていた労働時間の国際比較のグラフ。これを見ると、日本の労働時間は近年低下傾向にあり米国と同水準であるものの、ヨーロッパ諸国と比較するとまだまだ多い。しかもこれは日本の悪名高い長時間残業を含んでいません。この「働きすぎ」仮説は、日本と同様、民間非営利セクターの活動が低調な韓国が、国際的に見て極めて高い水準の労働時間を示していることから見ても、あながちずれていると言えないかもしれません。
一方で、見方を変えると、日本人の多くが好むと好まざるとに関わらず従事している長時間の残業 - しかもその中には違法である無給残業もあるはず・・・- は、ある種のボランティアといえるのではないでしょうか?
日本のサラリーマンや官僚たちは、「滅私奉公」という言葉があるとおり、私生活を犠牲にして、深夜までオフィスにこもって、あるいは営業先を一生懸命まわって、公に尽くしてきていると言えるかもしれません。
そうすると問われるべきは、
「企業や政府を通じて社会に提供される商品・サービスが、公の問題解決に本当に役立っているのか??」
という点になり、この答えがYesであるうちは、ひょっとしたら日本人の企業や政府を通じた「働きすぎ=滅私奉公」も非難されるべきことではないかもしれない。
しかし、社会が複雑さやその変化のスピードを増していく中で、政府でも市場でも解決しきれない社会問題が積みあがる中で、かつてYESだったその答えはNOに変わりつつある訳です。
政府と違ってフレキシブル且つきめ細かい地域密着型の対応ができると同時に、民間企業が市場を通じて提供する商品・サービスではカバーしきれない公の問題解決にダイレクトに関わることができる、そんな日本の民間非営利セクターを一人一人のボランティアを通じて強化していくためには、日本企業、日本政府、そして日本が慣れ親しんできたワーク・ライフバランスを見直すところから始めなければならないのかもしれません。
仮説2:硬直的な労働市場
ケネディスクールの友人たちに卒業後の進路の希望を聞いてみると、
「うーん、将来はNPOやNGOで働きたいけれど、卒業してすぐは(学費をまかなうために借りた)借金を返さなきゃならないこともあるから、コンサルティングとか、投資銀行等の民間企業にいくかな。そこでお金を稼いで、うんと力をつけて、その後、民間非営利セクターに尽くそうと思ってる。」
という回答がしばしば返ってきます。
また、僕のPAE(修士論文)のクライアントであるCommon ImpactのCEOやVice Presidentも年齢は30代後半ですが、これまでシステム関連会社や投資銀行で活躍し、そこで培ったビジネスのノウハウを民間非営利セクターのベンチャービジネスに役立てています。
あるいは、僕が夏の間本当にお世話になったインド最大のマイクロファイナンス機関BasixのCEOや重役クラスも、やはり大企業で力と金を得た後に民間非営利部門に乗り込んできたバックグラウンドを持った人が大勢いました。
つまり、民間企業-公共政策大学院/MBA-民間非営利セクター-政府といった、分野をまたいだ柔軟で開放的な労働市場が、能力のある人材を民間非営利セクターに呼び込む土壌となっているのです。
どんなにパブリック・マインドに燃え盛った人でも、社会に出てから引退するまで、ずーーーっとNPOやNGOで働き続けるのは、結婚し、子供もできることも考えれば、あまり現実的ではないでしょう。また、NPOやNGOを強化するにはビジネスの経験や政策の知識が欠かせない。
こうして見てみると、変わりつつあるとはいえ、終身雇用・年功序列賃金、あるいは採用に当たって企業や政府が設けてきた「年齢制限」の元で、政府・民間ともに転職が長らく「想定外」であった雇用慣行や社会認識が、今育ちつつある民間非営利セクターへの人材のスムーズな供給を阻んできたのかもしれません・・・
仮説はまだまだ続きます!
皆さんはどう思われますか??
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
☆ 『人気Blogランキング』に参加しています。「ケネディスクールからのメッセージ」をこれからも読みたい、と感じられた方は1クリックの応援をお願いします。
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆