Wikipediaの雨乞いの項目を見ていたら、日本各地に山頂で火を炊いて煙を起こして、鐘や太鼓を叩く雨乞いがあるらしいが、実は効果があるのではないかとさっき考えついた。水蒸気はちりや埃が凝結の核となって霧や雨になるのだが、大量に煙を高い山の山頂で立てると実際にその凝結核を増やすことになって効果があると考えたのが理由だが、本当に可能ならば、焚き火はかなり小さな現象であるのにマクロスケールで変化を起こすことができる古代人がやったこととしては画期的で驚異的な技だったのではと思われる。しかし、実際に雨をふらせるには元々雲が出ていなければならないと考えられ、雨をふらせたい地域の偏西風の風上に当たる西側の山岳地帯でなければならなかったり、いろいろ条件は選ばなければならない思われる。近年、日本で豪雨が増えているのも中国から飛んでくる凝結因子が原因である可能性とかはないのだろうかと疑うのだが、そんなことは聞いたことがなく、気象庁や地球シュミレーターの計算にも入っていないもので無視されているため、本当にないのかもしれない。
日本の三種の神器と呼ばれるものの一つに天叢雲剣というのがあるが、雨乞いが頻繁に行われたのは基本的に西日本で有り、空梅雨でしかも、最近のようにチベット高気圧が勢力が拡大している状況が連続していると西日本の瀬戸内海沿岸では旱魃が頻発するようであって、天叢雲剣というものに何らかの実用性があったとすれば、山頂あたりで燃やすアシを微妙に刈り取ることに使えたのかもしれない。三種の神器というのは昔の人から見れば神業のように思える用途に本当に使えたのかもしれず、八咫鏡も光通信したりは本当にやったかもしれないと思ったり微妙に想像が膨らむ(八尺瓊勾玉は用途がよく思いつかない)。
<object height="315" width="420"><param name="movie" value="//www.youtube-nocookie.com/v/UJi9AvQL49g?hl=ja_JP&version=3"><param name="allowFullScreen" value="true"><param name="allowscriptaccess" value="always"><embed src="//www.youtube-nocookie.com/v/UJi9AvQL49g?hl=ja_JP&version=3" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" height="315" width="420">
自分は最近、「クライマーズ・ハイ」を観た。どうしてだか自分は胃が痛くなったがほかの人はどう思うのだろうか。
1985年8月12日に起こった日航123便の墜落事故の翌日の午後に風下に当たる埼玉県内で3mmの降雨があった記録があるが関係あるかはわからない。
</object>
日本の三種の神器と呼ばれるものの一つに天叢雲剣というのがあるが、雨乞いが頻繁に行われたのは基本的に西日本で有り、空梅雨でしかも、最近のようにチベット高気圧が勢力が拡大している状況が連続していると西日本の瀬戸内海沿岸では旱魃が頻発するようであって、天叢雲剣というものに何らかの実用性があったとすれば、山頂あたりで燃やすアシを微妙に刈り取ることに使えたのかもしれない。三種の神器というのは昔の人から見れば神業のように思える用途に本当に使えたのかもしれず、八咫鏡も光通信したりは本当にやったかもしれないと思ったり微妙に想像が膨らむ(八尺瓊勾玉は用途がよく思いつかない)。
<object height="315" width="420"><param name="movie" value="//www.youtube-nocookie.com/v/UJi9AvQL49g?hl=ja_JP&version=3"><param name="allowFullScreen" value="true"><param name="allowscriptaccess" value="always"><embed src="//www.youtube-nocookie.com/v/UJi9AvQL49g?hl=ja_JP&version=3" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" height="315" width="420">
自分は最近、「クライマーズ・ハイ」を観た。どうしてだか自分は胃が痛くなったがほかの人はどう思うのだろうか。
1985年8月12日に起こった日航123便の墜落事故の翌日の午後に風下に当たる埼玉県内で3mmの降雨があった記録があるが関係あるかはわからない。
</object>











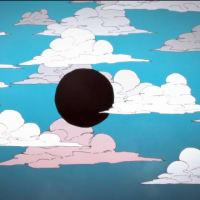
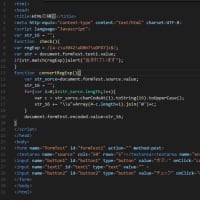







※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます