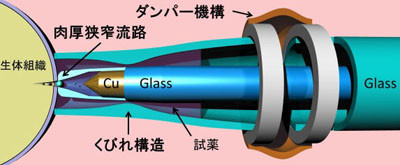今日、理研は、STAP細胞の記者会見をしている。
記者会見の詳細は、午後に明らかになる。
英国のサイエンス誌は、理研の高橋さんがiPS細胞による網膜移植手術を、今年のベスト1に選んだニュースも流れた。
今日、記者会見をしたのは、このニュースが流れることを知っていて、記者会見の対応をしたのではないかと勘繰ってしまう。
STAP細胞が再現できなかったのは、残念である。
再現できなかったのは、そもそもの細胞がなかったことになる。
捏造と言われても致しからないと考える。
この結論が出るまでは、どちらかと言うと小保方さんを応援していたので、大変残念な結果である。
科学の良さは、一定の条件下では、何度も再現できることである。
それを再現できるコツやレシピを知っている本人が再現できなかったのである。
小保方さんは、未だ若いので、一から出直して欲しい。
まず、博士論文から、博士号を取ることが大事である。
一方、一度、捏造した研究員を採用するところ(研究所・大学・企業等)があるのかは、疑問であるが。