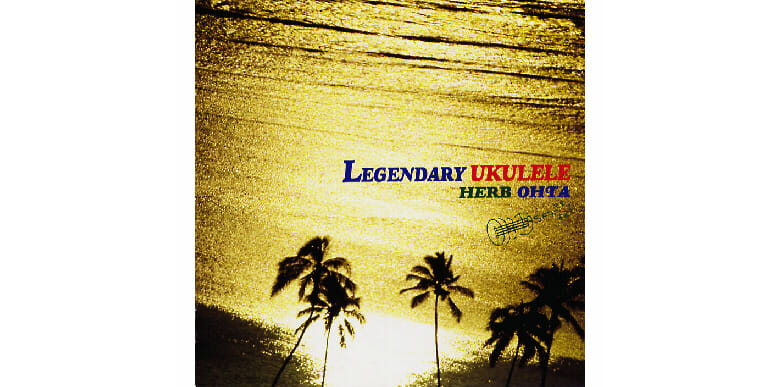
このアルバムは私が1998年にインターネットをはじめるきっかけとなったCDで、Cobaさんこと小林博さんに助けていただきながら何度も何度も改定しながらアップした思い出のアルバムです。今回ハワイアン・ウェーブ誌の「名盤セレクション」で採り上げましたので、ここにその記事と上記サイトからの曲目紹介を併せてご紹介いたします。
============================================
ウクレレ奏者たちやジャズ・ギタリストたちに衝撃を与えたアルバムレジェンダリー・ウクレレ/ハーブ・オータサン・ブレインSCCA-5 (1998.1.21.発売)
朝鮮戦争当時米海兵隊士官付きの通訳として日本や韓国に駐在していたハーブ・オータ(オータサン)が、帰国することが決まった1962年に知り合いの日本のミュージシャンたちにポリドールのスタジオに集まってもらい、リラックスした雰囲気の中でウクレレ・ソロ演奏を2時間に渡り録音いたしました。そしてこのテープをルアナ・ハワイアンズのリーダー山口軍一氏が保管していたのですが、36年後の1998年にその演奏がCDアルバム「レジェンダリー・ウクレレ」としてサン・ブレイン社からリリースされました。
録音時にはよもやアルバムでリリースされようとは思ってもいなかったようで、演奏中に話し声や足でリズムを取る音なども入っていますし、1曲を全部弾かないうちに次の曲に移る、といった場面もありましたが、2時間のテープから20曲を厳選してCDに収録したのがこのアルバムなのです。 当時のオータサンは現在メインで演奏している4弦を低くしたローG調弦ではなく、スタンダード調弦それも現在のような(4弦から)G-C-E-AではなくA-D-F#-Bという「アメリカン・チューニング」で弾いていますので演奏全体が大変軽やかに聞こえます。
現在までに100タイトル近くのアルバムをリリースするとともに、相変わらず円熟した演奏を各地で続けているオータサンですが、この「レジェンダリー・ウクレレ」はオータサンの青年時代における荒削りながら生き生きとした演奏が楽しめる数少ないアルバムと言っても過言ではないと思います。残念ながらこのアルバムは廃盤となってしまいましたが、入手方法や再発売の可能性についてのお問い合わせが依然として舞い込んでいるのは、このアルバムに感動した数多くのファンによるクチコミの影響ではないでしょうか。
収録された20曲はいずれも素晴らしい演奏ばかりですが、特に「ラヴァー」の演奏が日本のウクレレ奏者達にショックを与えました。その一人でウクレレ指導者の小林健博氏のお話では、それまでに知っていたウクレレ・ソロとは全く異なり、まるで複数の奏者が弾いているような演奏にも聴こえたので、どのようにするとこの演奏が再現できるのかと何ヶ月も考え続けたとのこと。そしてオータサン自身が有名なウクレレ奏者のペリー・バトキンの演奏するレコードを何度も何度も聴いてこの曲を自分のものにしたように、小林氏もこのCDを繰返し聴いて完全にその奏法を解明しウクレレ奏者たちに紹介されました。
実際にはペリー・バトキンのみならず、たくさんのボードビリアンたちやビーチボーイたちが以前からこういった演奏をしていたのですが、オータサンの弾くこのアルバムによってはじめて日本にもこの演奏方法が伝わったので、「ラヴァー」1曲だけを取ってもこのアルバムが日本のウクレレ奏者たちに与えた影響は極めて大きいと言えましょう。
ウクレレ奏者たちだけでなくジャズ・ギタリストたちからもこのアルバムが評価されました。彼らはギターよりも弦の少ないウクレレでまさかこれほどの多彩な演奏ができるとは思っても見なかったようで、リリースされた当時ギタリストたちがこのアルバムを競って購入したと聞かされました。 スタジオ録音のような正確な演奏ではなく、しかも話し声なども入っているので再発売は難しいかとも思われますが、やはりオータサンの青春時代における演奏の貴重な記録としていずれかのレコード会社から再発売されることを期待しております。
マット・コバヤシ
===========================================
曲目解説(上記私のサイトから転載)
1. スターダスト(D) 1927年にホーギー・カーマイケルが作曲したスタンダード。一曲めからオータサンの多彩な演奏テクニックが次々と登場するところをお楽しみください。
2.ナニ・ワイメア(D) パラダイス・セレネイダースのリーダーであり、スチール・ギター奏者としても有名であったサム・コキが1946年に作ったハワイアンの名曲。ナインスの和音を使うモダンな曲のため古くはインビテイションズから現代のパロロまでと多くのグループに愛されています。ハワイ島ワイメアにある世界最大(当時)の私有牧場の三代目当主サミュエル(ハワイ語ではカムエラとなります)・パーカーの住むワイメア村を歌ったもの。
3.インヴィテーション(Gm) ジャズのスタンダード曲で、1962年にバイブのミルト・ジャクソン・セクステットが発表したアルバム「インビテーション」(リバーサイド 9446)のタイトル・ソングとしても使われています。このアルバムには「ステラ・バイ・スターライト」等オータサン好みの曲が収録されており、メンバーもピアノのトミー・フラナガンやベースのロン・カーターという名手が参加しているので機会があったら是非聴きたい盤です。
4.マラゲーニャ(Gm) エルネスト・レクオーナがアンダルシア組曲中の一曲として1928年に作曲した名曲。オータサンの日本公演でも定番として演奏されるので、おなじみの方も多いと思います。マラガ地方の女性をマラゲーニャと呼びますが、トリオ・ロス・パンチョスの唄で有名なラ・マラゲーニャとは全く別の曲です。(こちらはエルピディオ・ラピデスの作品)
5.さくら(Gm) 誰もが知っているこの日本古謡をオータサンはお琴の演奏に似せて弾いて見せました。オータサンが自分のルーツである日本の曲を大切にしている様子は、普段のステージからもうかがえるように思えます。
6.剣の舞(Em) 最初に登場するクラシック曲はアルメニアの作曲家ハチャトリアンが1942年に発表したバレエ組曲「ガイーヌ」から「剣の舞い」です。ガイーヌというのは役人の妻の名前で、夫が不正を働いていることを告発したために夫から命を狙われます。彼女を守って夫を葬ってくれた警備隊長とのちに結婚しますが、その祝宴で奏でられるのがこの曲です。オータサンはポピュラーとかクラシックの区別なく演奏するので、この曲だけでなく沢山のクラシック音楽に親しめます。
7.バット・ビューティフル(D) 1947年にパラマウント映画Road to Rio(日本題「南米珍道中」)の主題歌としてジェームス(ジミー)・ヴァン・ホイゼンが作曲したもの。オータサンはコード奏法と単音弾きを巧みに混ぜて曲想を盛り上げています。
8.ラ・クンパルシータ(Em) アルゼンチン・タンゴの名曲で米国へ渡ってストレンジ・センセイションなどという奇妙なタイトルまで付けられたジェラルド・ロドリゲス1915年作のこの曲を、オータサンはかなり省略して演奏しています。「二つのギター」ふうのイントロのあとタンゴの特徴である歯切れの良さをウクレレで弾くところはやっぱりオータサンならではと言えましょう。
9.チワワのヘスシータ(E) ヘスシータという女性を踊りに連れ出そうと思っている若者が彼女にさかんに呼びかけているというメキシコ民謡。フランス製と思われる世界の旅シリーズCD「Escale au Mexique」(PlaysoundPS-66502)にはたしかに「Jesusita in Chihuahua」となっているのですが、同一の曲なのでしょうか。オータサンが子供の頃ザビア・クガーの演奏で覚えたそうなので、その演奏記録を探したのですが見つかっていません。
10.トロピカル(A) モートン・グールドの作品で、正式なタイトルはThe Tropicalです。オータサンは弦を弾きながらウクレレの指板や胴をリズムとして叩くという離れ業をやってのけています。ウクレレ演奏に興味のある方はいちど挑戦してみてはいかがでしょう?
11.ミュージック・マエストロ・プリーズ~アウト・オブ・ノーホエア(D) 最初の曲はMusic,Maestro,Please!日本題「音楽をどうぞ」というアリー・ウルーベル1939年の作品。メドレーで続く曲は正式にはYou Came Along From Out Of Nowhereという長いタイトルを持つ1931年のパラマウント映画Dude Ranchの主題歌としてジョニー・グリーンが作曲したもの。あまりにも長いタイトルなので、普通はうしろ半分(場合によっては前半分)で呼びます。日本の題名も「どこからともなく」とか「いずこともなく」という頼りないタイトルが付けられています。肝心の演奏ですが、2音の和音をメロディーとして弾く、これまたハイ・テクニックの連続です。
12.リトル・ロック・ゲット・アウェイ~ジョセフィーヌ(D) またまたメドレーです。最初の曲はジョー・サリヴァンが1938年に作曲した曲。次は英語読みで「ジョセフィン」のほうが近い1936年ウェイン・キングとバーク・ビバンス(ガス・カーンは作詞)の共同作品。こんどはオータサンのミュート奏法とチョーキングもご披露されますので、お楽しみ頂けると思います。オータサンが子どもの頃の記憶で演奏しているのでこの楽しい曲を弾きおえて「多分こんな具合と思うけど、よく知らないヨ」と英語で言っています。
13.インタメッツォ(A) この曲の正式タイトルはA Love Storyといい、ユナイト映画Intermezzo日本題「別離」主題歌としてハインツ・プロボストが1939年に作曲しました。勿論、後年の映画Love Story(日本題「ある愛の詩」)とは無関係です。オータサンはトレモロで美しく弾くとともに、メロディーのバックにまでトレモロでコードを付けています。
14.メディテーション(G) 正式な日本題は「タイスの瞑想曲」といい、フランスの作曲家マスネーがアナトール・フランスの小説にもとづいて1894年に発表した歌劇「タイス」の第2幕で演奏される間奏曲を指します。物語はタイスという名の娼婦に町中の男が毒されていたアレキサンドリアのとある町で、修道士のアタナエルが彼女を入信することで改心させ町を救ったが、彼女の死に際して彼女を愛するようになったため彼女の魂は天国に、そして彼の魂は地獄へ行ってしまうというもの。 オリジナルはよくバイオリン・ソロで演奏される小品ですが、オータサンはトレモロを駆使して音の持続をはかっています。
15.月の光(D) 続いて同じくフランスノ作曲家ドビュッシーが1890年に発表した小品4曲 からなる「ベルガマスク組曲」から第2曲「月の光」です。この曲は単独でも 演奏される名曲で、この録音から35年経った現在でもオータサンの重要なレパートリーとなっています。ロバート・マックスウェルのハープに匹敵する厚みを持った演奏は大変すばらしいものです。
16.恋の気分で(G) 一転して軽い気分の曲になりました。1935年パラマウント映画Every Night at Eightの主題歌としてジミー・マクヒューが作曲した「恋の気分で」です。オータサンはメロディーを弾きながら伴奏のコードもしっかりと弾いていて、まるでデュエットをしているようです。
17.ラヴァー(G) オスカ・ハマーシュタイン・ジュニアとコンビを組む前のミュージカル王リチャード・ロジャースが1932年のパラマウント映画Love Me Tonight主題歌として作曲したもの。この曲にだけ「ペリー・バトキンに捧げる」と書いてあるのは、オータサンが子どもの頃、ウクレレを弾く人は誰でもペリーの演奏を真似ていたので、ここではそれを思い出して弾いて見せたからなのです。すなわちこのスタイルだけはオータサンのアレンジとは違っています。 ご参考までに、ウォルター・クラーク監修の「ビーチ・ボーイ・パーティー」というアルバムにもペリーのスタイルで「ラヴァー」が演奏されています。
18.ジャスト・ワン・オブ・ゾーズ・シングス(B) ビギン・ザ・ビギンを始めとしてたくさんのポピュラー曲の作曲者コール・ポーターがJubileeの主題歌として1935年に作詞・作曲したもので、日本題は英語のまま「ジャスト・ワン・オブ・ゾーズ・シングス」と呼ばれています。オータサンは早いストロークのコード奏法で、この曲を軽快に演奏しています。
19.10番街の殺人(B) 17曲めと同じリチャード・ロジャースとローレンツ・ハート(詞)のコンビで作った1936年のミュージカルOn Your Toesの主題歌。エレキ・グループのベンチャーズが演奏し、1964年のヒット・チャートにもランクされて日本でもお馴染みになった曲です。 もともとピアノで演奏される曲で、オータサンはこの曲を何とかマスターしたいと12歳の頃から16歳頃まで研究していたにもかかわらず、大変難しくてどうやっても弾けませんでしたが、なんと19歳のときにちょっとしたきっかけで弾けるようになったそうです。新曲の楽譜を貰って2~3回弾いてみて「とても手に負えない」などと言って投げ出してしまう自分を省みて、つくづく修行の足らなさを感じました。
20.ティコ・ティコ(Em) 原タイトルはポルトガル語でTico-Tico No Fubáといい、1941年にツェキーナ・アブリューによって作られ、1943年のRKO・ディズニー映画「ラテン・アメリカの旅」Saludos Amigosの主題歌として使われました。この広い音域を持った曲をオータサンが何の苦も無く演奏しているのには只々感嘆するばかりです。
----------------------------------------------------------
以上、タイトルのうしろに付けたキー(調子)でおわかり頂けるように、私たちが最も弾きやすいCのキーが全くありません。別にオータサンがわざと難しいキーを選んで弾いている訳ではなく、この録音に使ったウクレレの調弦が当時一般的であったアメリカン・チューニングすなわちA-D-F#-Bになっていただけに過ぎません。

















ご無沙汰しています!
私もこのアルバムでシビレタ一人です。
何年前か忘れてしまいましたが、購入した当初は、感激のあまり、どこに行くにもこのCDを持っていき、皆に聞かせていたような気がします。
(そのせいかどうか分かりませんが、現在行方不明です。(^_^;)
すべての曲が圧巻でしたが、やはり特にLoverはド肝を抜かれ、当時楽譜を探し回りました。
近年カマテツさんのジャカソロ本で見つけた時は、長年の思いが叶い、言葉で表現できないくらい感激しました!
3月末くらいまでにモノにしたいと思っていますので、今後ともよろしくお願い申し上げます!!
文中に書きました小林健博さん(白鳥さん)も先日つくづくそのときの衝撃を語っておられました。
カマテツさんの演奏も白鳥さんの解析がベースとなっていますので、その意味でもこのアルバムが日本のウクレレ界に与えた影響は大きかったと思います。