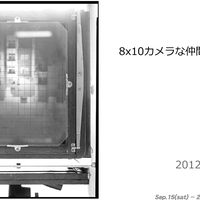わたしの母方の、亡くなった祖父が馬喰(ばくろう)で、叔父が牛市場の獣医をしていた。祖父の大きな家は、街道筋の、牛市場の近くにあった。羽振りのいい時に、旅館を買い取ったものらしい。玄関の間口はさほど広くないが、二階建ての町屋風の造りで、奥行きが非常に長く、一番奥まった所に、祖父母が生活する部屋と牛を繋ぐ納屋があった。その裏は道を挟んで川である。
祖父は、ニッカボッカに、鳥打ち帽という出で立ちがトレードマークであった。われわれは、畑で鎌を使ってれんげを刈ったり、納屋で大きな押し切りで藁を切りったりする祖父の後を追いかかけて、幼年期の大半を過ごした。
きれいに洗われた牛の首筋に触ると、短く、柔らかい毛並みをしていて、そっと頬を当てて見ると、気持ちよかった。しかしちょっと油断をすると、滝のような小水を浴びせられるし、糞の山に足を滑らせ、腹を汚れた後足で蹴られるという憂き目にも遭うのであった。
牛市場が立つと、町は賑やかになり、楽しかった。たくさんの牛が集まって、品評会に掛けられ、ローマのコロッセウムを何百分の一かにしたような、階段つくりの、円形の建物で、セリが行われるのを見物した。
いい牛には、赤や黄の、きれいな布が掛けられ、品評会で入賞すると、首にぴかぴか光る、重いメダルが掛けられた。そのメダルは、われわれ悪ガキのこころを惹き付けて止まなかった。なんとかして、それを自分でも、首に掛けてみたいと思いつめた。
牛が高く売れると、祖父は上機嫌で、自ら牛鍋を作り、昼間から、弱い酒で顔を赤くしているのが常だった。概して祖父は陽気で、冗談ばかり言っている男で、孫たちには人気があった。われわれは祖父のハゲ頭を木魚のように叩きながら、「ハゲ頭の歌」を唄うのだった。
客の多い家で、いつもどこからか仲間の年寄りがやってきては、式台に腰掛けて、渋い茶と、固い羊羹、キセルたばこを振る舞われていた。祖母はその隣で、いつも着物の仕立て直しをしていた。わたしもここで渋い茶の味を刷り込まれた。
祖父は、どこかから雌犬のボクサーを手に入れ、かけ合わせて、出産をさせた。小学校から帰ると、わたしは狂喜乱舞して、祖父の所へ飛んで行った。われわれの幼年時代の大事件であった。生まれたばかりの小犬を飽かず、眺めた。
ボクサーの名前は、ジャッキーであった。JFKの演説をテープで繰り返し聞いていた、英語の好きな従兄が、そう名付けたのだ。ジャクリーヌ・ケネディには、似ても似つかぬボクサー犬であったが、そう呼んでいるうちに、本人(犬)もその気になり、われわれも何の不思議にも思わなくなった。牛には名前を付けなかったはずである。牛飼いの家がみんなそうだったのかどうかは知らない。
名付けといえば、祖父は、自分の息子たちに、歌舞伎の「蘇我物語」の兄弟に因んで、十郎、五郎と名前を付けた。この辺が、どうも遊技気分であって、われわれシロート筋と違う男であったといつも感じるところだ。
祖父は納屋の二階から転落して、腰を悪くし、その後、心臓の発作で亡くなった。牛市場も跡形もなく消えてしまった。馬喰の生活を知る者も、もはや多くないだろう。
ふと「土佐源氏」の馬喰の語りは、あれは土佐弁ではないのではなかろうか、という疑問が頭に浮かんだ。なんとなくわれわれが知っている、坂本龍馬が喋るいさましい土佐部とは違う感じがするのだ。宮本の生まれ故郷の山口県の言葉のようでもある。
茶屋谷の竜王生まれのタクシーの運転手さんに乗り合わせたが、「あの辺の人は、愛媛の言葉に近い言葉の人もいますよ」と云っていたのを思い出した。モデルの山本鎚造翁は愛媛の生まれで、檮原へ流れて来た馬喰だ。伊予弁なのかどうかも、方言の知識がなくて、はっきり分からないが、中国地方の生まれのわたしにも、「土佐源氏」の語りは、その言いまわしやイントネーションに至るまで、ほぼ完全に、耳の奥に再現できる。これは不思議なことだ。
俳優の坂本長利さんの一人芝居の「土佐源氏」は、もう三十年以上続いているらしい。十年以上前にチケットを取ろうとしたことがあったが、人気が高くて観られなかった。力演で、評価も高いようだ。でも観なくてもいいやという気もしている。
わたし自身は、「土佐源氏」という作品に、失われた祖父の言葉が蘇って来るような気がしているからだ。
祖父は、ニッカボッカに、鳥打ち帽という出で立ちがトレードマークであった。われわれは、畑で鎌を使ってれんげを刈ったり、納屋で大きな押し切りで藁を切りったりする祖父の後を追いかかけて、幼年期の大半を過ごした。
きれいに洗われた牛の首筋に触ると、短く、柔らかい毛並みをしていて、そっと頬を当てて見ると、気持ちよかった。しかしちょっと油断をすると、滝のような小水を浴びせられるし、糞の山に足を滑らせ、腹を汚れた後足で蹴られるという憂き目にも遭うのであった。
牛市場が立つと、町は賑やかになり、楽しかった。たくさんの牛が集まって、品評会に掛けられ、ローマのコロッセウムを何百分の一かにしたような、階段つくりの、円形の建物で、セリが行われるのを見物した。
いい牛には、赤や黄の、きれいな布が掛けられ、品評会で入賞すると、首にぴかぴか光る、重いメダルが掛けられた。そのメダルは、われわれ悪ガキのこころを惹き付けて止まなかった。なんとかして、それを自分でも、首に掛けてみたいと思いつめた。
牛が高く売れると、祖父は上機嫌で、自ら牛鍋を作り、昼間から、弱い酒で顔を赤くしているのが常だった。概して祖父は陽気で、冗談ばかり言っている男で、孫たちには人気があった。われわれは祖父のハゲ頭を木魚のように叩きながら、「ハゲ頭の歌」を唄うのだった。
客の多い家で、いつもどこからか仲間の年寄りがやってきては、式台に腰掛けて、渋い茶と、固い羊羹、キセルたばこを振る舞われていた。祖母はその隣で、いつも着物の仕立て直しをしていた。わたしもここで渋い茶の味を刷り込まれた。
祖父は、どこかから雌犬のボクサーを手に入れ、かけ合わせて、出産をさせた。小学校から帰ると、わたしは狂喜乱舞して、祖父の所へ飛んで行った。われわれの幼年時代の大事件であった。生まれたばかりの小犬を飽かず、眺めた。
ボクサーの名前は、ジャッキーであった。JFKの演説をテープで繰り返し聞いていた、英語の好きな従兄が、そう名付けたのだ。ジャクリーヌ・ケネディには、似ても似つかぬボクサー犬であったが、そう呼んでいるうちに、本人(犬)もその気になり、われわれも何の不思議にも思わなくなった。牛には名前を付けなかったはずである。牛飼いの家がみんなそうだったのかどうかは知らない。
名付けといえば、祖父は、自分の息子たちに、歌舞伎の「蘇我物語」の兄弟に因んで、十郎、五郎と名前を付けた。この辺が、どうも遊技気分であって、われわれシロート筋と違う男であったといつも感じるところだ。
祖父は納屋の二階から転落して、腰を悪くし、その後、心臓の発作で亡くなった。牛市場も跡形もなく消えてしまった。馬喰の生活を知る者も、もはや多くないだろう。
ふと「土佐源氏」の馬喰の語りは、あれは土佐弁ではないのではなかろうか、という疑問が頭に浮かんだ。なんとなくわれわれが知っている、坂本龍馬が喋るいさましい土佐部とは違う感じがするのだ。宮本の生まれ故郷の山口県の言葉のようでもある。
茶屋谷の竜王生まれのタクシーの運転手さんに乗り合わせたが、「あの辺の人は、愛媛の言葉に近い言葉の人もいますよ」と云っていたのを思い出した。モデルの山本鎚造翁は愛媛の生まれで、檮原へ流れて来た馬喰だ。伊予弁なのかどうかも、方言の知識がなくて、はっきり分からないが、中国地方の生まれのわたしにも、「土佐源氏」の語りは、その言いまわしやイントネーションに至るまで、ほぼ完全に、耳の奥に再現できる。これは不思議なことだ。
俳優の坂本長利さんの一人芝居の「土佐源氏」は、もう三十年以上続いているらしい。十年以上前にチケットを取ろうとしたことがあったが、人気が高くて観られなかった。力演で、評価も高いようだ。でも観なくてもいいやという気もしている。
わたし自身は、「土佐源氏」という作品に、失われた祖父の言葉が蘇って来るような気がしているからだ。