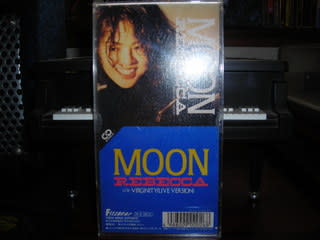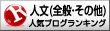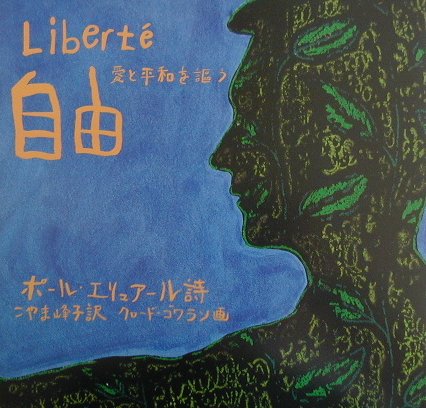長い間REBECCAを聞いていた時期がありました。
ボーカリストNOKKOの書く詩が潜在的に私を、
捉えていたのだと思います。
でないと、
彼女のあのかん高い声と、
少しうるさい楽曲が
心地よく私には届いていなかったと思います。
数多くの曲があり、甲乙つけ難いですが、
私にとっての思い入れの一曲は「MOON」です。
MOON
昔ママがまだ若くて 小さなあたしを抱いていた
月が もっと遠くにあった頃
工場は黒い煙を はきだして
町は激しく この娘が大きくなるのを祈ってた
娘は13になって 盗みの味覚えて
黒いリストに 名前を残した
MOON あなたは 知ってるの
MOON あなたは 何もかも
初めて歩いた日のことも
月曜日が 嫌いと言って 心のすべてを
閉ざしてしまった娘は
初めての 恋におちた日
思い出ひとつ持たずに 家を飛び出して
戻らなくなった
こわしてしまうのは 一瞬でできるから
大切に生きてと 彼女は泣いた
(NOKKO作詞:部分引用)
この曲は英語バージョンでも出ていて
作詞は他の方ですが、
参考までに、一部引用しておきます。
また違ったニュアンスが味わえると思います。
勉強にもなります。

英語バージョンの「MOON」が入っているCDです
MOON
In the night your light comes creeping
around my bed
Stirring up memories
Taking me back to the times we shared
when we were childhood friends
Seems like yesterday
the world was full of innocence
Moon you seemed so far away
on the night that you shined on my first kiss
( PEGGY STANZIALE 詩:一部引用)
You can choose two type of the "MOON".
http://www.youtube.com/watch?v=Zp5WjyaK-CU&feature=related (PV)