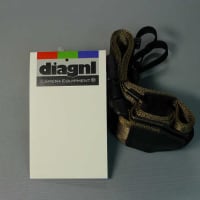| どん底<普及版>東宝このアイテムの詳細を見る |
NHK・BS2で『どん底』を鑑賞しました。概要等はウィキペディアでご確認下さい。
ゴーリキーの「どん底」を翻案した作品なんですが、見る者の視点により、解釈が大きく変わってしまうだろうなと思いました。江戸の掃きだめ、文字通り「どん底」に位置する長屋が舞台となり、そこに棲む(「住む」というより「棲む」の方がしっくりくる)連中の悲惨な生活が描かれているのですが、彼ら最底辺の人々の生き様を虚無・デカダンと見るか、それとも人情の「希望の火」を読み取るか、それによって随分解釈が分かれるように感じたのです。
「どん底」の暮らしの中で、酒に溺れ、人の悲しみを茶化して喜ぶようなポーズを取る長屋の住人達が、いざという時には「連帯」してことに当たる姿が随所に見られました。確かに、鋳掛屋の女房が衰弱死したときなど、長屋の住民が吐いた言葉は、どれもきつくてむごいものでしたが、それは「極貧」を受け入れざるを得ない境遇が言わせた「弔い」の言葉と見ることは出来ないでしょうか。「極貧」からはい出る術がない以上、その境遇を受け入れる覚悟を持って生きてゆく… そんな強い意志をいろいろな場面で見せてくれたように思います。ラストシーンでは「辛い日常を蹴散らすように踊り歌う」長屋の面々が、更に「どん底」に突き落とされてしまうわけですが、私には、見る者を滅入らせる終わり方だとは思えませんでした。そう、落語のオチのような余韻を感じたと申しましょうか… 彼らは「どっこい生きてゆく」のだろう、と。
役者さんたちは、どなたもいい味を出しています
 左ト全の巡礼もいいし、山田五十鈴の悪女もいい!でも、個人的にはまったのは藤原釜足の役者ですね
左ト全の巡礼もいいし、山田五十鈴の悪女もいい!でも、個人的にはまったのは藤原釜足の役者ですね アル中で、おつむもやられた男を、ユーモア&ペーソス溢れる演技で見せてくれます。
アル中で、おつむもやられた男を、ユーモア&ペーソス溢れる演技で見せてくれます。