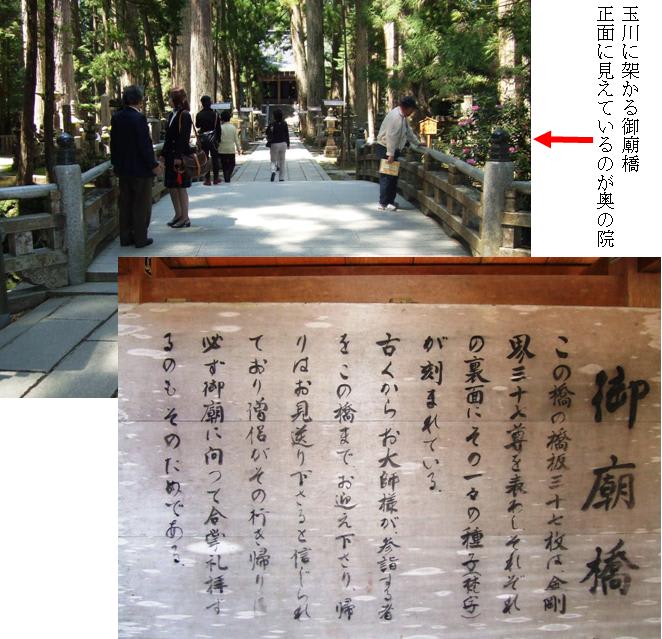自宅から奈良へは1時間弱、近い事もあり、年に1,2回は訪れる。
四季折々の趣があり、いつ来ても癒される。
この日は近鉄奈良駅から真っ直ぐ東へ東大寺へむかう。


近鉄奈良の地下駅を上がればすぐに奈良公園、東大寺仁向かう道の車道を挟んだ左側は奈良県庁他官庁街、右側が写真の奈良公園。兎に角奈良公園は鹿だらけ,フンだらけ、芝生に座る時も気をつけねばフンの上に座ることになる。

近鉄奈良駅からぶらぶら写真を撮りながら30分ほどで東大寺南大門、ここをくぐって大仏殿に向かう。

写真右下正面が大仏殿回廊、その向こうに大仏殿がある。
鹿のせんべいはヌカでつくられている。観光客がせんべいを買うと鹿が付いてまわってはなれない、小さい子供には危険な時がある。不思議な事に売店に並べられているせんべいは取りに行かない、観光客が買うまでまっている。


大仏殿から少し登った所にお水取りで有名な二月堂がある、ここの舞台からは奈良の町が一望でき、平城京跡から生駒山、信貴山も遠望できる。
円高とインフルエンザのせいか、この日は観光客も少なく、いつもは韓国、中国、台湾などアジアの人が多いのに、白人さんが多かった。
あちこちに人力車が駐車していたが、不景気のせいか乗せて走っているのは見なかった。
東大寺詳しくはここをクリック
東大寺もっともっと詳しくはここをクリック