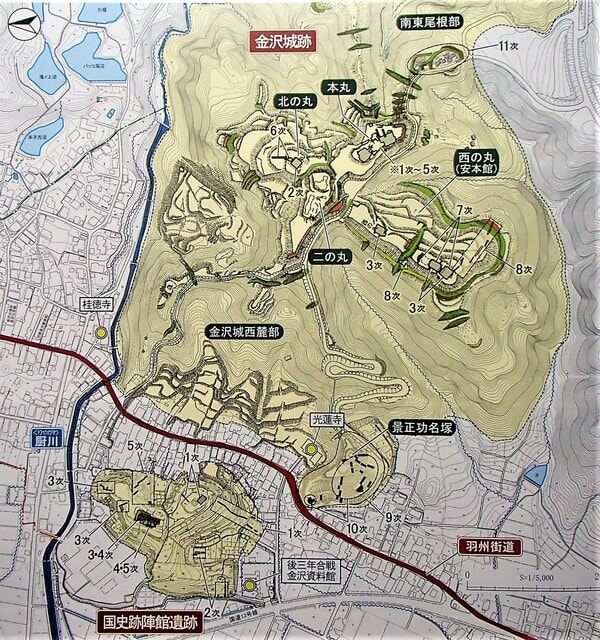角館城跡。秋田県仙北市角館町古城山。
2023年6月3日(土)。
10時40分ごろ乳頭温泉鶴の湯を出て往路を戻り、角館城跡へ向かった。角館は1970年代ディスカバー・ジャパンの時代に小京都ともてはやされた。1980年代前半に旅行で訪れ、武家屋敷群を見学し、稲庭うどんを食べた。なので、再訪することはせず、山川歴史散歩で興味を引かれた角館城跡のみ見学することにした。


山頂の本丸跡。
11時45分頃、古城山の麓にある古城山公園の駐車場に到着。雨の中、舗装された管理車道を歩いて登ると12時頃に山頂の平場に着いた。

石碑と石塔。


戸沢氏の家紋。丸に輪貫九曜。

姥杉。

山頂南端から角館武家屋敷方面。桧木内川沿いに桜並木がある。駐車場からの登城歩道の途中、曲輪跡に東屋が設けられている。

山頂南端から角館武家屋敷方面。
角館城は、戦国時代の山城で、角館の武家屋敷町の北側に位置する標高166m(比高100 m)の独立丘陵上にあった。かつては姫小松が多く茂っていたことから小松山城ともよばれていた。
築城年代、築城者ははっきりしないが、秋田氏(安東氏)や小野寺氏と戦いながら勢力を拡大した出羽国の戦国大名で、江戸時代に山形新庄藩主となった戸沢氏が本拠としていた城である。
戸沢氏は1424年(応永31)に北浦郡の門屋城(仙北市西木町)から、この城に本拠を移したとされる。戸沢氏重臣で小松山城主の角館能登守が上浦郡の小野寺氏と通じて謀叛を起こしたので、戸沢家盛がこれを討って小松山城を開城させ、後に居城を移転したという。天正年間に活躍した当主戸沢盛安は、「鬼九郎」(夜叉九郎)の異名で呼ばれた。
戸沢氏の頃は、山の上に館を置き、北麓に城下町を造り、軍事的機能を優先した町づくりが行われた。戸沢氏は、戦国末期には織田信長や豊臣秀吉と誼を通じて領国経営を安定させた。戸沢氏は関ヶ原の戦いでは東軍方だったが、1602年(慶長7)に減封の上、常陸国松岡へ国替えとなった。
代わりに角館に入ったのが佐竹氏の一族の蘆名義広(盛重)である。その後、1615年(元和1)に一国一城令が発令され、これに伴い、角館城は1620年(元和6)に城郭が破却された。
蘆名氏は、この山を軸として戸沢氏時代とは正反対に南麓に城下町の縄張りが行われ、館も南麓に移した。
その後、蘆名氏が断絶したことから、1656年(明暦2)に紫島城(むらさきしまじょう)(大仙市長野)の佐竹義隣(佐竹北家)が角館に入部し、以後、11代2百余年にわたり明治維新まで佐竹北家がこの一帯を治めた。
城跡は現在、古城山公園として整備されており、主郭をはじめとする郭跡の平場が残っている。なお、この公園は角館の街並みを一望できる桜の名所として知られている。
古城山公園は、2023年7月6日にクマによる人身事故が発生し、当面の間、立ち入り禁止となっている。
戸沢氏は、桓武平氏貞盛流と称す。大和国三輪に居住し、源頼朝に臣従し奥州合戦での活躍が認められ、奥州磐手郡滴石庄(岩手県雫石町)に下向し鎌倉幕府御家人となったという。滴石庄の戸沢邑に居を構えたことから「戸沢氏」と称した。1206年、戸沢兼盛は南部氏から攻められ、滴石から門屋小館(秋田県仙北市西木町)に移る。1220年に門屋小館から門屋へ移り、1228年門屋城を築城したという。
南北朝時代、戸沢氏は南朝に属した。興国二年(1341年)の合戦は北畠顕家の敗戦に終わり、顕家は滴石城に入城した後、出羽国へ去っていった。この時に滴石の兵も従ったとある。興国二年の合戦以後、南部氏が北朝方に寝返ったことと、北陸奥における足利氏勢力が増大したことが契機となり、この時に戸沢氏が仙北地方に移ったと推測される。
戸沢氏は、その後、本拠地を門屋から角館に移し、門屋地方からさらに、仙北三郡の内、北浦郡全域への支配拡大を目指した。角館に本拠を移転した時期については諸説あるが、室町時代中期とされる。

応仁2年(1468年)、南部氏が小野寺氏との抗争に敗れ、仙北三郡から撤退する。戸沢氏は北浦郡の統一に成功し、仙北三郡の覇権を巡り小野寺氏さらには安東氏との抗争を開始する。元亀元年(1570年)には、北浦郡全域と仙北中郡、旧仙北郡の大部分を平定する。
戸沢盛安は、永禄9年(1566年)に生まれ、「鬼九郎」の異名を取り、北奥随一の名将と謳われた。盛安は小野寺氏や安東氏を破って勢力を拡大し、仙北三郡の完全平定に成功。戸沢氏の全盛期を出現させる。中央の動静にも絶えず注目し、豊臣秀吉の小田原征伐には東北地方の戦国大名の中ではいち早く参陣して秀吉の賞賛を受け、所領を安堵された。しかし盛安は参陣中に突然病死した。
盛安の死後、弟の戸沢光盛が家督を継ぐ。奥州仕置の後、戸沢氏の支配地域は盛安の死と惣無事令の問題もあり、北浦郡4万5千石のみ安堵され、残りの地域に関しては太閤蔵入地の代官としての権限を与えられた。
光盛は朝鮮出兵の途上、播磨国姫路城で病死した。光盛の死後、盛安の子戸沢政盛が家督を相続する。秀吉の死後、政盛は鳥居忠政の娘と縁戚を結び、徳川方へ急速に接近していく。
関ヶ原の戦いでは東軍に属し、最上氏と共に上杉氏と戦う。しかし上杉討伐で秋田氏の勢力が増大することを恐れ、消極策に終始した。戦後、この行動が咎められて、常陸国松岡へ減転封された。

蘆名義広(1575~1631年)は、蘆名(あしな)氏第20代当主で、常陸の戦国大名・佐竹義重の次男として生まれた。
蘆名氏は、文治5年(1189年)、奥州合戦の功により、三浦義明の七男・佐原義連に会津が与えられたことに始まる。蘆名姓を名乗るのは、義連の息子盛連の四男光盛の代になってからである。室町時代には京都扶持衆として、自らを「会津守護」と称していた。
戦国時代、蘆名盛氏の時代に最盛期を迎えたが、一族猪苗代氏をはじめとする家臣の統制に苦慮し、さらに盛氏の晩年には後継者問題も発生して、天正8年(1580年)、盛氏の死とともに蘆名氏は次第に衰え始める。
蘆名氏は当主・蘆名盛隆が大庭三左衛門により殺害されたことで、混乱を迎えた。盛隆の子亀王丸が生後1ヶ月で蘆名氏の第19代当主となるが、度重なる当主交代に混乱する蘆名氏の家臣団は上杉氏や伊達氏の調略を受け、その勢力を削がれていった。
天正13年(1585年)5月、伊達政宗が蘆名氏と開戦。11月に佐竹氏および蘆名氏らの南奥諸大名の連合軍と伊達氏の間で人取橋の戦いが起こり、蘆名氏は佐竹義重率いる連合軍の一員として勝利した。
この頃、当主の亀王丸が夭折したため、家中は養子を巡って、伊達小次郎を推す伊達派勢力と義広を推す佐竹派勢力とに二分された。後継者争いは義広派が勝利し、天正15年(1587年)、盛隆の養女と結婚して蘆名義広と名乗り、蘆名氏当主となる。
しかし他家からの養子であることに加え、後継者争いでの紛糾や、当人の年齢も若かったことから、家臣団を掌握することができずにいた。
天正17年(1589年)6月伊達政宗との間に起こった総力会戦ともいえる摺上原の戦いで大敗した。義広とその近臣は戦場を逃れたが、もはや本拠の黒川城を守備する兵力を維持することは不可能で、実家佐竹氏の領国である常陸に逃れた。こうして奥州の戦国大名としての蘆名氏はその支配地域を失い滅亡した。
しかしこれらは豊臣秀吉が天正15年(1587年12月)に関東・奥州に対して発令した私戦を禁止する「惣無事令」以降のことであったため、その後の天正18年(1590年)の秀吉の小田原征伐の際、秀吉に恭順した政宗は、奪い取った蘆名領を全て没収された。蘆名領は蒲生氏郷に与えられ、義広への返還はなされなかったが、秀吉から佐竹氏与力として、佐竹氏の領国に近い常陸の龍ヶ崎に4万石、次いで江戸崎に4万5000石を与えられ、大名としての蘆名氏は一応復興した。
慶長5年(1600年)、関ヶ原の戦いで兄の佐竹義宣が西軍に与したため、連座して所領を没収された。
慶長7年(1602年)、義重・義宣とともに秋田領に入り、名を義勝(よしかつ)と改め、仙北郡角館に1万6000石を与えられた。
義勝は、それまでの城下が河川の氾濫や火災にしばしば悩まされていたところから、元和6年(1620年)古城山の南側に新たに町割を起こし、城下を移転させた。これが今日の角館城下町の始まりである。
道路の幅員を広げるとともに見通しを避ける工夫をこらし、下水を整備し、火事対策を施して武家地、町人地、寺社を配置した。当初は古城山の中腹に館を構えたが、義勝夫人が城中で妖怪を視たため居館を麓に移したという伝承がある。角館に随従した蘆名家家臣には、稲葉家、河原田家、岩橋家、青柳家などがあり、総勢は200名程度だったといわれる。
死後、息子が相次いで病死、最後の当主・蘆名千鶴丸も3歳で事故死したために家系は断絶して蘆名氏は滅亡した。
佐竹義隣(よしちか。1619~1702年)は、佐竹氏一門の佐竹北家8代当主で、角館初代所預(城代)である。権大納言・高倉永慶の次男として誕生した。母は佐竹義宣の妹である。
佐竹氏は、清和源氏の源義光の孫昌義が常陸国久慈郡佐竹郷に土着し、佐竹氏を称したことに始まる。平安時代末に平家に属して源頼朝に抵抗したので勢力を落としたが、鎌倉幕府滅亡後は足利氏に属して常陸守護職に補任され勢力を回復。戦国時代には常陸国・下野国から陸奥国にまで勢力をのばし、北関東最大の大名として後北条氏や伊達氏と争った。豊臣秀吉からは水戸54万石を安堵されたが、関ヶ原の戦いで西軍に属したことで1602年に秋田20万石に減封された。戊辰戦争では官軍に属して戦い、維新後には侯爵に列せられた。
佐竹北家は、常陸守護で太田城主の佐竹氏第14代当主・佐竹義治の四男佐竹義信(1476~1533年)が分家したことに始まる。天文年間に太田城の北に屋敷を構えたため、北家と呼ばれるようになった。佐竹東家と後に成立した佐竹南家とともに宗家の家政を支えた。
関ケ原の合戦で西軍に付いた佐竹氏が出羽国久保田藩(秋田藩)に減転封された後、元和7年(1621年)に当主申若丸(佐竹義直)が宗家の養子となったため一時絶家したが、寛永5年(1628年)に公家高倉家出身の義隣を養子に迎えて再興された。明暦2年(1656年)から角館を領するようになり、3600石を領した。義隣は、故郷を懐かしんで、京に似た地形の角館の山河に「小倉山」、「加茂川」などと命名した。
角館家ともよばれ、家禄は1万石。
21代目の当主である佐竹敬久は、2009年に秋田県知事に初当選し、現在4期目である。
このあと、角館武家屋敷群の通りを通り抜け、大仙市の秋田県埋蔵文化財センターおよび国史跡・払田柵跡へ向かった。