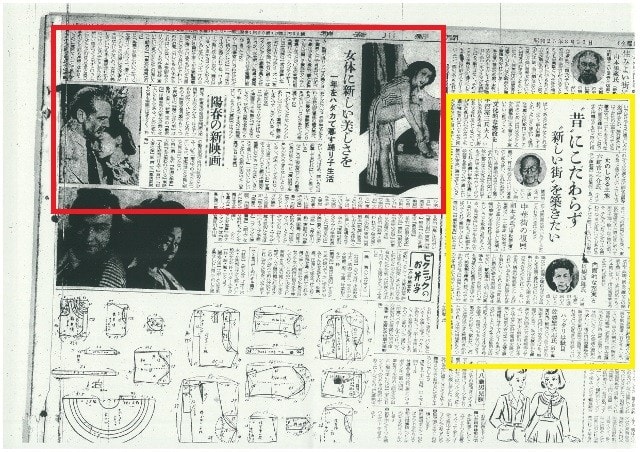
| ここ数年、私は時間を見つけては横浜市中央図書館や県立図書館に通っている。目的は、初期の美空ひばりのことを調べるためだ。それには昔の新聞を片っ端から見ていくしかない。 中央図書館はマイクロリーダーで、県立図書館は大型の複製版でと、それぞれ方法は異なるが、どちらも原寸の文字サイズが小さいうえに、活字が潰れていたり、ピンボケであまり鮮明でなかったりして、いちいち拡大したり元のサイズに戻したりしなければならない。 30分もこんなことをやっていると、しだいに自分の眼のピントの方が合わなくなってくる。そんなとき、疲れを癒してくれるのが、こんな記事なのである。 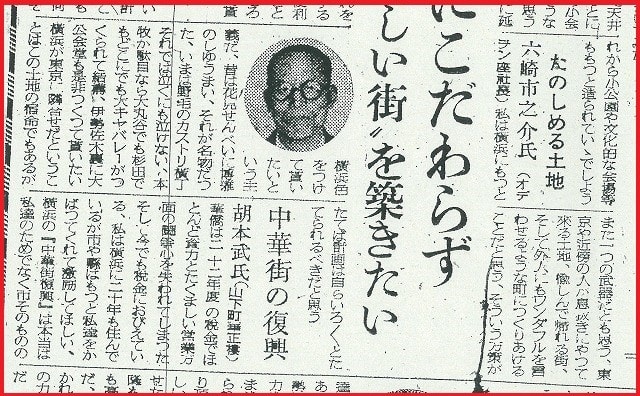 黄色の枠で囲った部分。戦争が終わり4年半経った横浜中華街の現状を、華正樓の胡本武さんが語っている。 市や県はもっと自分たちのことを激励してほしい、中華街の復興は横浜市や市民のためになるのだから…というような内容である。 その記事の上では、オデヲン座の六崎市之介さんが面白いことを喋っている。 「むかしは花見煎餅に博雅のしうまいが名物だったのに、今は野毛のカストリ横丁、それでは泣くに泣けない…」 ここから分かることは、戦前の伊勢佐木名物といえば花見煎餅と博雅の焼売だっとことだ。 そしてもう一つ、昭和25年でもまだカストリ横丁があったということ。 六崎さんは続けて、こんなことも言っている。 「本牧がだめなら、大丸谷でも杉田でも、どこでも大キャバレーをつくられて結構…」 戦前、本牧や大丸谷にはチャブ屋があって、外国人や日本人で賑わっていた。戦後はそれを懐しみ、同様の施設を復活させろ、なんていう人たちが多かったと聞く。 しかし、なんで「杉田」という地名が出てきたんだろう? これも調べなければいけなくなってしまった……。  もう一つ、気になった記事はコチラ  拡大して読みたい方は、下のサムネイル画像をクリックしてね。ハズキルーペなしでも読めるから。  ↑ クリック!  冒頭の新聞記事と同じ日に掲載された劇場案内。 オペラ館が横浜セントラル劇場に改称されたことが分かる。 もう一つ、分かったこと。 それはこの時代でもまだ、京急のことを「湘南」と呼んでいた事実。昭和6年に湘南電気鉄道(浦賀~黄金町)と京浜電気鉄道(品川~日ノ出町)が接続して、その後、両者が合併(吸収?)して京浜急行ができているのだが、戦後になっても「湘南黄金町駅」なんて言い方が残っていたんだぁ。 参考:はげまる氏の記事1 記事2  ←素晴らしき横浜中華街にクリックしてね ←素晴らしき横浜中華街にクリックしてね |

















焼売は、大人になってから上大岡の京急デパ地下で再会し子供の頃と同じ味に大変感激したのですが・・・
博雅のコメント、ありがとうございます。
<伊勢佐木町の有隣堂本店の馬車道寄り、今は丸井の跡地のパチ屋の付近>
そうですね。最後はものすごく小さい店になっていました。
中華街に同名の売店があったのですが、その素性を調べる前に閉店してしまい、残念に思っています。
学生時代バイトで新聞の縮刷版をコピーしたり、マイクロフィルムをスクロールした思い出が蘇ってきました。若い頃は文字が小さくてもへいちゃらだったのですけれど、今はどうかなぁ。そもそも図書館に行かなくなりました。
因みに20代の息子は図書館愛用者で、彼は滅多に本を買わず、買うときは古本です。最近の若者は内容重視で新品には拘らないようです。
閑話休題。「中華街復興は本当は私たちのためではなく市のため」という思いが、現在につながっているのですね。お洒落な元町やレンガ倉庫、雑多な魅力溢れる中華街、「港町」という言葉に伴う異国情緒、さまざまな顔をもつ横浜は他県の者にとって常に憧れの街ですが、憧れの対象には、それを維持するためのたゆまない努力があるわけで、まさにローマは1日にしてならず、ということなのでしょう。
ますます横浜が好きになります。記事のご紹介、有難うございます。
中央図書館には旧式のマイクロリーダーと、
新型のがありますが、
やっぱり旧式の方がいいですね。
新型は見え方がきれいですが、疲れます。
中華街は新しく参入してきた方々が儲ける街になってしまったような気が…
街の若い人たちに頑張ってほしいです。