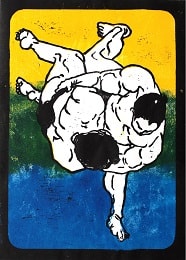歌 川 国 芳 夕 霞(団扇絵)

民芸家具・・暮らしに息づく美しさ、長く使われてきたからこそ、美しい。今も使われているからこそ、美しい。
日本の民芸運動の「用の美」を求める心、目指すのは、安らぎとぬくもりに包まれた潤いのある暮らし。天然木と手作り感にこだわりながら、 生活空間の中で長く愛される家具
福 島 民 芸 家 具

書類、封書、整理タンス



小物入れ(腕時計、指輪、貴金属、その他)



帳場硯箱(算盤、筆、印象、和紙)



以前から欲しくても、なかなか手に入らなかった福島民芸家具(小型タンス)
ついに我がコレクションに収蔵、見た目には六個の引出しですが、参個の隠し引出しの
有る優れもの、職人の技が光る作品・・・望みを持ち続ければ叶う日が来るものと思う今日此の頃・・・ 写 楽 老 人

民芸家具・・暮らしに息づく美しさ、長く使われてきたからこそ、美しい。今も使われているからこそ、美しい。
日本の民芸運動の「用の美」を求める心、目指すのは、安らぎとぬくもりに包まれた潤いのある暮らし。天然木と手作り感にこだわりながら、 生活空間の中で長く愛される家具
福 島 民 芸 家 具

書類、封書、整理タンス



小物入れ(腕時計、指輪、貴金属、その他)



帳場硯箱(算盤、筆、印象、和紙)



以前から欲しくても、なかなか手に入らなかった福島民芸家具(小型タンス)
ついに我がコレクションに収蔵、見た目には六個の引出しですが、参個の隠し引出しの
有る優れもの、職人の技が光る作品・・・望みを持ち続ければ叶う日が来るものと思う今日此の頃・・・ 写 楽 老 人