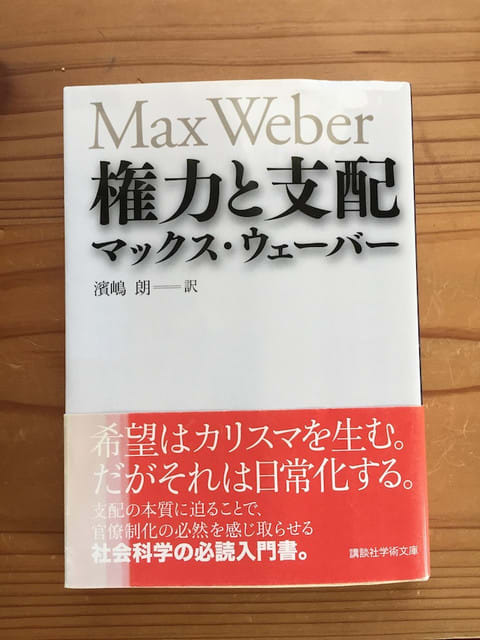今井絵理子氏はともかく、山尾しおり氏は不倫を連想させる
週刊誌の絶好のネタの標的になって政治生命も危ういことになっている
山尾氏の肩を持つわけではないが、少しもったいない
政治家が不倫騒動で政治能力とは関係なく世間的に資格を失うようになることは
この手の事柄が歴史的にもよく見かける出来事だけに少し考えてしまう
これがフランスなら、政治能力と個人生活は違う、、といった扱いで
大した問題になっていないとか(本当のところは知らないが)
損得を考えた時、今井氏も山尾氏も「今の楽しい時間」と「将来どのような事態を招くか」
の適切な判断ができなかったといえるが、実際のところコントロールしきれない感情の存在が
人というものの一面で、そうした感情を味わったことがなく、常に冷静な判断で白黒つけるようなのは
一見正しそうだが、弱い人に対する洞察力や優しい眼差し(どうしようもない存在としての)を
軽視してしまいそうで、自分のような横着者には何処か住みにくそうな世界を連想させる
でも世間的には、あかん、、以外の答えは、公には発しにくい雰囲気
今読みつつある「選択の科学」

この本のなかにとても興味深いエピソードがあった
「選択を左右するもの」の章に小さな子どもに対して行った「マシュマロテスト」がある
マシュマロ・テストとは、目の前の美味しそうなお菓子が並ぶなかで一番好きなお菓子マシュマロを選んだ
子どもに対して行われた、少し意地悪な心理学的なテスト
ある部屋にいる子どもは大好きなマシュマロを一つ手にしている
意地悪な試験管は「おじさんは別の部屋で大事な仕事がある。このマシュマロは君のものだけど
まだ食べちゃダメだよ。もしおじさんが戻ってくるまで待てたらご褒美にもう一つあげる。
でもどうしても食べたくなってしまったら、ベルを鳴らしなさい。直ぐ戻ってくるからね。
でもそうしたらマシュマロは一個しか食べられないよ。わかったかな、約束だよ」
少し待てば(いつまではわからない)マシュマロは2つ食べられる
そのほうが得だという気持ちと、いつまでかわからない不安と食べたいという気持ちで
パニックになった子どものとる行動は、、、
4歳児の試練と苦行はそれほど長くは続かず、子どもたちは平均すると3分しか待たずにベルを鳴らした
だがこの数分間、少年少女たちは自分が今すぐ欲しいものと、全体としてみれば自分のためになると
わかっていることの間で、激しい葛藤と戦わなければならなかった。4歳児の葛藤は、大人の目には
苦しみというより微笑ましいものに映るかもしれないが、誘惑と闘うことがどれだけストレスの溜まることか
誰でも知っている」
これは子どものお話だが、つづいて次のような問が大人に対して行われる
「今から1ヶ月後に100ドルもらうのと、2ヶ月後に120ドルもらうのとでは、どちらを選びますか?」
「今100ドルもらうのと、120ドルをもらうのとでは、どちらを選びますか?」
このテストを行うと最初の問ではほとんどの人が20ドル余分にもらう方を選んだが
二番目の問では1ヶ月待つよりも、少ない金額を今もらう方を選んだ人がほとんどだった
となったとのこと(なんとなく分かる)
結局のところ、大人も子どもも今楽しいことへの誘惑にはかなり弱い(不倫もそんなところ)
この本では選択にたいする「自動システム」と「熟慮システム」の概念が紹介される
自動システムは、すばやく、たやすく無意識のうちに作用する。そして感覚情報を分析し
迅速に反応して感情や行動を始動させる常時作動している「隠れた」プログラム
一方「熟慮システム」は未加工の感覚情報ではなく、論理や理性である
熟慮的な思考のおかげで、極めて複雑な選択に対処できることになるが
この処理は自動システムよりは遅く、骨が折れるために、それなりの意欲と努力が必要とされる
この自動システムと熟慮システムの選択が同じ場合は問題はないが、ほとんどの場合それは異なるため問題となる
一見正しい判断をしそうな熟慮システムも、それゆえに間違いを起こす可能性もあるのだそうだ
政治的な専門家の判断が、何も知らない素人の判断と比較して、その的中率はうわまることはないという結果が
でたことがあったそうだ
専門家は専門家ゆえに多くの情報を集める、しかしそこに自分がこうだと思う傾向の情報を集めて
しまい、それでもって自分を納得させてしまうというのだ
(なるほど、インターネットの世界ではいろんな意見を収集できるというが、結局自分とあう
情報を手にしやすいから、ここのところは理解できる)
少しばかり軽薄で批判の多そうな「自動システム」だが無意識の選択は実はなかなか捨てがたい面もある
経験により「嘘を言っている」と感じ取る能力は、必ずしも「理性の力」のおかげではないし
付き合うことになったカップルのきっかけは「無意識」の好感で、それはどういうわけかあまり
間違いがない との報告もある
結局のところ選択というのは難しい
熟慮システムに従うべきだが、どうしても我慢できない衝動が存在しうる人という存在
将来よりもついつい今を選んでしまう人の気持ち
秋に行われる新城市の選挙
「熟慮システム」に従って投票する人が多いか、
それとも直感的な「自動システム」に従って投票する人が多いか、、、
(熟慮システムと言っても、結局は自分の意見を正当化するような熟慮がされがちな気がするが)
おまけ
無意識という点では、フロイトやユングのややこしいお話よりは数年前読んだ
「意識は傍観者である」(デイヴィット・イーグルマン)が本当に面白かった
人は自分で思っているほど理性的ではないことがよく分かるし、無意識の凄さも知ることとなった
実はショーペンハウエルも「意志と表象としての世界」でこの手のことは何やらごちゃごちゃ言ってるし
メルロ=ポンティも身体を通しての(判断に至る)認識論には詳細な考察をしてる(と思う しっかり読んでないからわからないが)
それから仏教の認識論も「空即是色」だし
そう思うと、人間社会ってのは案外アバウトなところで成り立っているんだと実感する
それにしても適切な選択 やっぱり難しい
必要なのは選んでしまった者の、開き直った「覚悟」かなと思ったりする