ドイツ軍占領下のオランダ
オランダは、早い時期から植民地経営を行い、その莫大な収益によって悠々自適な生活を享受できる階級の人々が多かった。このことが、第一次世界大戦で植民地を失い、インフレに悩むドイツにとってはうらやましい存在だった。オランダには、戦前から反ヒットラー、反ナチの気運が高く、多くの防空壕を作ったりしてドイツ軍の侵攻に備えていた。
1940年のある日、晃は家族と夕食をとっていた。その時、突然電話が鳴った。
「鳥沢さんですか。」と、日本語が響いた。
「はい、そうです。どちらさまですか。」
「東京の読売新聞の記者です。」
「何でしょうか。」
「オランダ女王が、内閣のメンバーと共にイギリスに亡命したという噂を聞いたのだが、本当ですか。」
「えっ、女王はオランダにいらっしゃいますよ。こちらは平穏そのものです。」
そう、晃は返答した。不思議な話である。不可解な気持ちで就寝すると、午前3時ごろ、けたたましい飛行機の音に目が覚めた。ラジオでは、数え切れないくらいの飛行機が来襲しており、落下傘部隊がオランダ全土に降下してきているとのことだった。日本からの電話の意味がやっと理解できた。実は、ドイツ軍のオランダ侵攻は、数日前には日本軍当局に知らされていた。その情報が、新聞記者に漏れたのだ。
日本の大使館員が引き上げた後、オランダに残った唯一の日本人である晃のもとに情報の確認をしてきたのだ。ドイツ軍のオランダ占拠はあっという間に完了した。ドイツ陸軍将校および兵卒は、英国に攻め入る準備として、一般公共施設を徴用した。ただ、オランダ人の反ナチ感情が強いことから、安全のため民間人の家は徴用しなかった。
一方、日本人である晃の四階建ての家には、複数の高級将校が強制的に寄宿した。そのうちの一人は、英国の10シリング紙幣を見せて、英国に上陸したらすぐにこの紙幣を使うのだと嘯いた。
占領下のオランダでは、一般人がラジオの短波放送を聴取することは禁じられていた。ところが、晃はそれを許されており、米の配給も受けていた。これは、晃が枢軸国の国民であったことによるものだと理解していた。したがって、日本陸海空軍の侵攻に関する華々しい大本営発表が、英米からの発表と異なっていることを知っていた。戦線は、次第に緊迫の度合いを高めており、晃の家族にも決断の時が迫っていた。
つづく











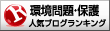

 Michio Kumagai @KumasanHakken
Michio Kumagai @KumasanHakken




