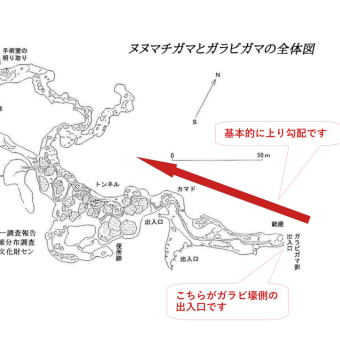「土俵を間違えた人」第1回②
前回の続きです。
「赤松元大尉は、手りゅう弾は、防衛隊員が勝手に住民に渡したのであって、自分は知らぬといったようだが、防衛隊員が、どういう理由で、自分の意思で、同じ島の住民である非戦闘員に手りゅう弾を渡すのか、その動機や理由が理解できないし、防衛隊員も、また、大切な武器である手りゅう弾を上官の許可なく他人に渡したりすると、軍規上、厳しい処罰を受けるおそれがあることを知らなかったはずはないのである」
「赤松大尉の命令または暗黙の許可がなければ、手りゅう弾は住民の手に渡らなかったと考えるのが妥当である」
上記の引用は太田氏の執筆した「沖縄戦に「神話」はない」からのものです。
太田氏は今回の再反論でも一貫して「鉄の暴風」は事実であること、赤松大尉の「自決命令」の根拠として、「厳重に管理されていた」はずの手榴弾が、非戦闘員である住民にまで配られた、という事実があることを挙げております。
つまり、軍規や軍律といった精神的な拘束で「厳重に管理」されており、なおかつ「高度な防御陣地」(「沖縄戦に「神話」ない」の7回目で言及)では、武器庫のような物理的な設備によって「厳重に管理」されていた手榴弾が、支給された防衛隊員のみならず非戦闘員の住民にまで行き届いたということは、そこに「赤松大尉の命令または暗黙の許可」が介在しているに違いない、ということになると思われます。
精神的、物理的なものによって厳重に管理された手榴弾ということになるのですが、こういった太田氏の解釈には、個人的見解として無理があるのではないかと思います。
それは「厳重に管理されていた可能性が低い」という仮説を提示できるからです。
そもそも太田氏は防衛隊員たちが住民と合流した意味について、意図的かどうかはわかりませんがあまり言及していません。
これはおそらくですが、自らも軍隊経験がある太田氏は、その経験則から「防衛隊員は命令や指示がない限り、住民と合流することは絶対にありえない」という、ある種の固定観念というか、あるいは前提条件に固執している結果ではないかと思われます。
しかし太田氏のように断定・断言できるのでしょうか。それを検証するため、かなり長いものになってしまいますが、興味深い事実もありますので以下に引用いたします。
「防衛隊員で生き残った人たちの証言記録を見て目をひくのは、いわゆる戦線離脱(軍からの脱走)がきわめて多く、また上官の命令の拒否や本土出身の正規兵への反抗などもみられることである。また自らすすんで米軍に投降することもあった」(藤原彰編「沖縄戦と天皇制」立風書房 1987年)
「沖縄戦史家の大城将保さんによると、約2万5000人が防衛召集を受け、そのうち約1万3000人が戦死したという。
米軍上陸前は、飛行場建設や陣地構築などが主な任務だった。防衛隊員は自分たちのことを自嘲気味に、「棒兵(ボーヒー)隊」、「苦力(クーリー)隊」「みのかさ部隊」と呼んだ。
米軍上陸後、戦闘が激しくなると、防衛隊員は、守備軍の正規兵が壕の奥深くに身を潜めているときも、弾薬・食糧運搬、夜間斬り込みの案内など、危険な仕事を割り当てられることが多くなった。(中略)
「ボーヒー隊どぅ、やるむんぬ、ひんぎーしる、ましやる」(どうせ棒兵隊なんだから、逃げて家族のもとに行ったほうがいいさ)。
家族を残して召集された防衛隊員の中には戦線を離脱し、家族のいる壕に駆け込む人が少なくなかった」(沖縄タイムス社説 「戦後70年〔地に刻む沖縄戦〕防衛隊 ひんぎーしる ましやる」2015年3月17日)
「急に騒がしい足音がして、数人の者が、壕内に駆け込んできた。部下の防召兵達(防衛隊員──引用者注)だった。「弾が激しくて集合時間に遅れてしまった。元気を出して一緒に出かけよう」と遅参をわびるように平良教頭が云うと、隊員達は、「もう行く必要がありません。集まった連中は、そのまま前線に出されました。ひどいことをしやがる。鉄砲の射ち方もしらない連中を兵隊より先に前線へ送るなんて、余りに馬鹿臭いので僕たちは逃げてきました」と答えた」(沖縄タイムス社編 「鉄の暴風」 沖縄タイムス社 1950年)
防衛隊員が自主的に部隊から離脱しているという状況は、沖縄戦全体における周知の事実であることがうかがわれます。この論争がおこなわれた1985年当時も同じで、特に隠された事実というものではありませんし、そういった行為を批判・批難するつもりはございません。
この防衛隊員が部隊や戦線から離脱する件については、様々な地域・様々な境遇の様々な証言が数多く存在しているのです。
その中からあえて「鉄の暴風」やその編集・出版元である沖縄タイムスの社説と、集団自決や従軍慰安婦は「日本軍に強制された」というスタンスを堅持する大学教授(2020年現在)でもある、林博文氏が執筆を担当した「沖縄戦と天皇制」を引用いたしました。
また、渡嘉敷島の防衛隊員の証言にも、自主的に部隊から離脱したというものがありました。これは当ブログ「沖縄戦に「神話」はない──「ある神話の背景」反論 第5回と第6回④」にて既に言及しておりますので、ここでは重複を避けるために引用いたしません。
以上のような事実があるというのならば、渡嘉敷島の防衛隊員も太田氏の主張する軍の命令や指示・意思ではなく、家族の元へなどといった様々な理由から自主判断で部隊から離脱し、様々なルートで集合を指示された住民と合流した可能性が高いという、太田氏の主張とは真逆の仮説が浮上してくるのです。
この件をさらに補完する好例として、以前にも取り上げた集団自決のキーパーソンとなる、元渡嘉敷村長の証言があります。
元渡嘉敷村長については当ブログ「「沖縄戦」から未来に向かって 第2回②」にて言及しております。それを要約すると、防衛隊員が合流したのは軍の命令によるもの「かもしれない」あるいは、「あったに違いない」といった個人的な推測のみで、実際に命令があったのかは「分からない」というものです。
なぜ元村長は防衛隊員に合流した理由を聞かなかったのか、常識的に考えれば疑問に思うかもしれません。しかし元村長は故人でありますから、直接質問することはできませんし、何かを聞いたとしても、何らかの理由で黙したままだったのかもしれません。それゆえにこれ以上の考察は無理と思われます。
軍の命令や指示で防衛隊員が合流したという証言はありません。なおかつ、命令や指示で合流したと「聞いた」という住民の証言もありません。キーパーソンである元村長も防衛隊員から「命令があった」と聞いたのなら、そういった内容を包み隠さず証言する可能性が高いのですが、「命令があったのかどうかは分からない」というような証言しか得られていません。
以上のような事実を列挙した場合、太田氏の主張に説得力や妥当性はあるのでしょうか。
防衛隊が住民と合流し手榴弾が住民に渡されたその理由に、軍の命令や意思があったのだと断言できるのでしょうか。渡嘉敷島だけは特別に軍規・軍律が厳しく統制されていたのでしょうか。
そもそも太田氏は、防衛隊が自主的に部隊からの離脱をしている事実を把握していたのでしょうか。それともあえて無視していたのでしょうか。
ここで確実なことは、「鉄の暴風」が発行された1950年頃から既に自主的に部隊や戦線を離脱していた防衛隊員がいたということが、少なからず知れ渡っているということです。
今回は軍規や軍律といった精神的な拘束で「厳重に管理」されていた可能性は低い、という理由を提示しました。次は物理的な設備等によって「厳重に管理」されていたかどうかについてです。
次回以降に続きます。