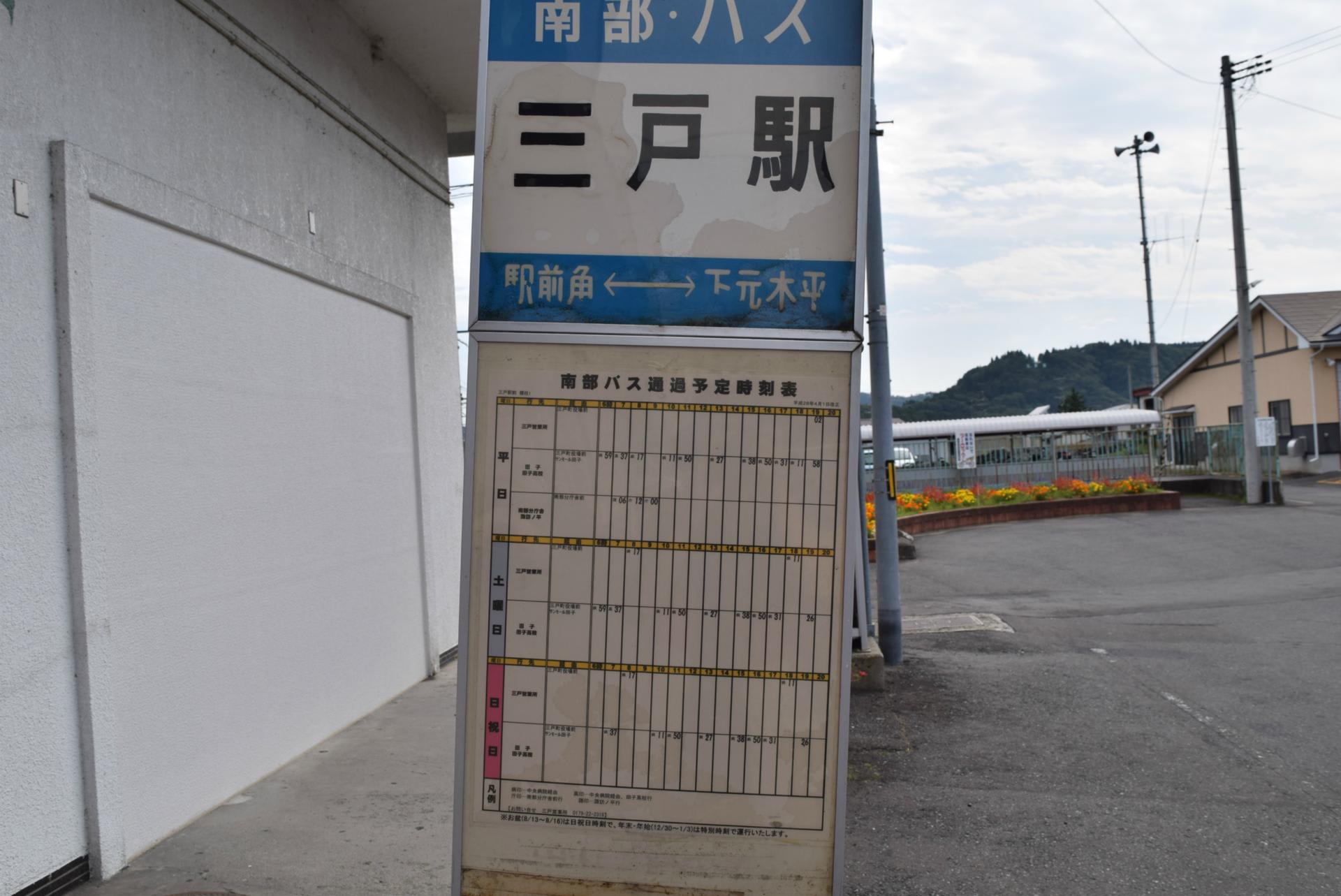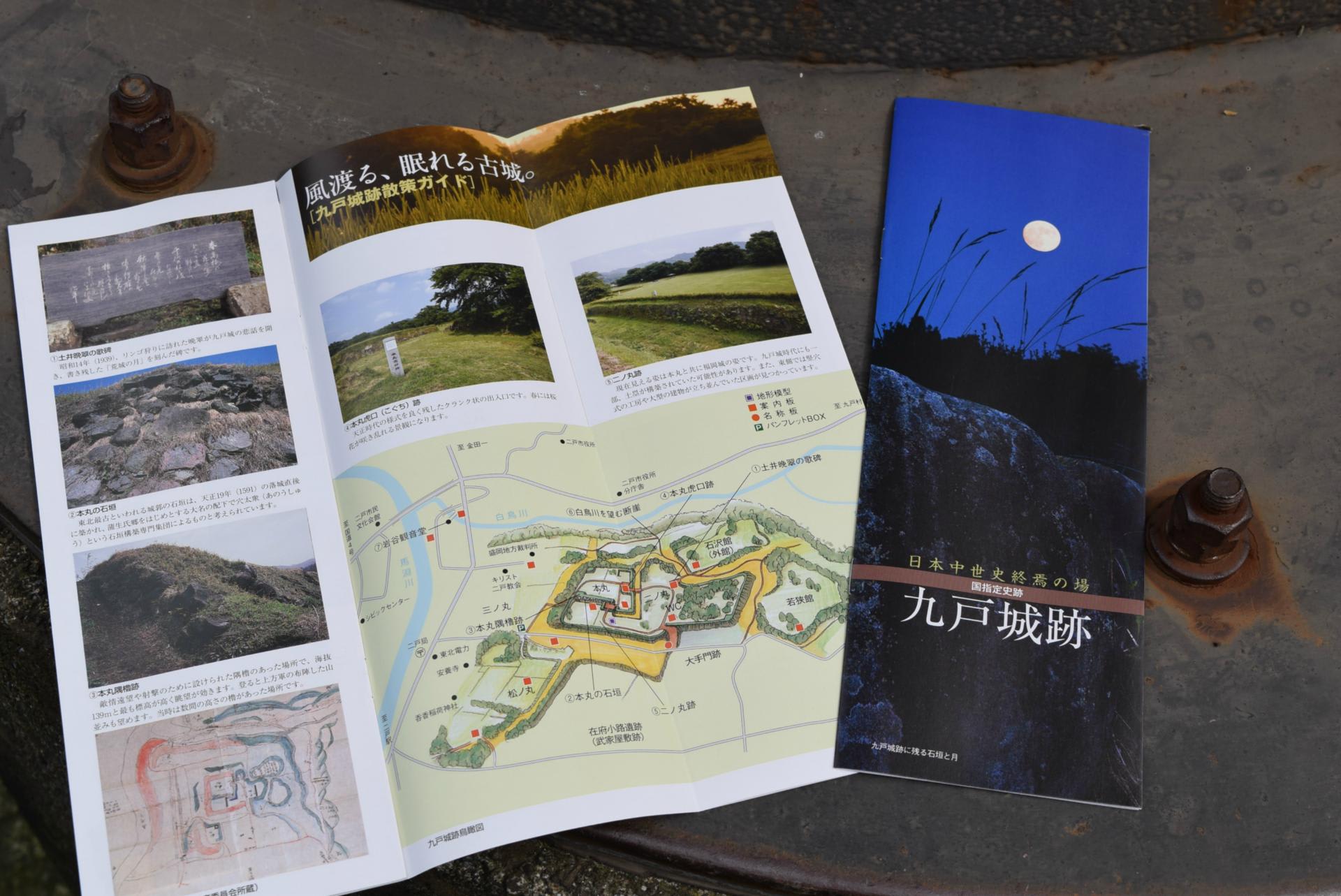弘前市は歴史的建築物の宝庫ともいえる町です。明治期に弘前城の石垣修復工事を担当した大工棟梁・堀江佐吉による旧弘前市立図書館、旧青森銀行本店など、日本の近代建築の第一人者・前川國男の市立病院、市民会館、市立博物館など8つの建築物、他にも洋館、教会、レンガ造りの各種建築物が市の各所にあります。

青森銀行記念館(旧青森銀行本店。重要文化財)、堀江佐吉の建築です。堀江佐吉はもともとは津軽藩のお抱えの大工でしたが、明治初期に函館で西洋建築を学び、弘前に帰って数々の西洋建築物を設計・建築しました。

現在の青森銀行本店

安寿と厨子王と母、3人の像。安寿と厨子王の像がなぜ弘前にあるのか調べましたが、母子の出身地は奥羽、陸奥のどこかは不明のようです。伝説、小説の上の話です。福島県いわき市にも母子の像はありました。

旧市立図書館。堀江佐吉建築

平面図



旧図書館の内部

現在の市立図書館

岩木山



旧東奥義塾外人教師館。堀江佐吉建築

外人教師館内の喫茶室。弘前はコーヒーが日本で初めて普及した町だそうです。幕末に蝦夷地防備に赴いた津軽藩士が病気の予防薬として珈琲を常用し、函館から珈琲を持ち帰って飲用として普及させたとのことです。


外人教師館の裏手の弘前ミニチュア歴史的建築物群。東武ワールドスクエアです。


前川國男建築の弘前市庁舎。手前は弘前城の外濠

青森の有力地方紙・東奥日報の本社。普通のビルです。

旧第八師団長官官舎。現在は弘前市長公舎。堀江佐吉の長男の設計


城内の弘前市民会館。前川國男の設計


市民会館のすぐ裏手の弘前市立博物館。前川國男の設計


博物館の前庭の植栽。頑丈な作りの雪囲い。さすが雪国、豪雪地帯です。



城内の緑の相談所。前川國男の設計

県立弘前中央高校の講堂。前川國男の設計

藩祖・津軽為信の像

弘前城の三の丸を見渡せる位置にあるライオンズマンション。宝くじが当たったらこのマンションに住みたい。

三上ビル(旧弘前無尽社屋)。初期の鉄筋コンクリート造り

田中屋。津軽塗りの店

斜陽館のような和風建築の旅館

宿泊したホテル・ドーミーイン。ビジネスホテルなのに温泉大浴場があるのはうれしい。設備も最新です。


弘南鉄道の中央弘前駅。大鰐温泉へいきます。

中央弘前の駅舎

中央弘前駅前のショッピングモール・ルネスアベニュー。スイスのシオン城のような建物です。

弘前昇天教会。ジェームス・ガーディナーの設計。ガーディナーは立教女学校(築地居留地)、明治学院、遺愛学院(函館)、フランス大使館、オランダ大使館などを設計したアメリカ人建築家です。



えきどてプロムナード

JR弘前駅


裏側の弘南鉄道弘前駅。黒石へいきます。

紀伊國屋書店

青森県の老舗デパート・中三。中三は五所川原で創業した老舗デパート。一時は青森、弘前、秋田、盛岡、五所川原、二戸に店舗を構えていたが経営破綻し、今は青森、弘前の2店舗で再建途上です。北海道の丸井今井も棒二森屋も五番館もすべて自力経営は頓挫しています。五番館は消滅しました。地方の老舗デパートには厳しい冬が続きますね。
【後記】後日、中三弘前店は毛綱毅曠の建築だということを知りました。不覚です。もっと詳しく見ればよかった。毛綱毅曠は釧路出身の建築家で、2001年に他界しました。有名なのは釧路フィッシャーマンズ・ワーフや釧路湿原展望台など。毛綱毅曠の建築物は出身地の釧路に多く、本州には数ヵ所しかありません。その希少な一つです。

蓬莱橋付近の土淵川


弘前市立病院。前川國男の設計

夕食を食べた洋食店「磊」。「みついし」と読むそうです。
弘前市内に前川國男の建築物が8つあります。市民会館、市立博物館、市立病院、緑の相談所、市役所、弘前中央高校講堂の6つの建物を今回撮影しました。残りの木村産業研究所と弘前市斎場は今回は見送り。
前川國男はパリへ留学しル・コルビュジェに学び、帰国後のデビュー作が木村産業研究所です。なぜ前川作品は弘前に多いのか? 前川國男は新潟の出身ですが、母親がこの弘前の出身で、母親の縁で弘前で建築設計のデビューをし、その後も弘前との良好な関係が続いたようです。
堀江佐吉といい前川國男といい、弘前に今も建築物が残っているのは嬉しい限りですね。弘前市には「趣のある建物」を指定する制度があって、歴史的建築物の保存維持に積極的な活動を続けている成果です。
【後記】毛綱毅曠設計の中三弘前店も「趣のある建物」に指定してほしいですね。