私の哲学史(1)──ルソー(自由について)
|
私がルソーを読むようになったのは、いわゆる自我の目覚めのとき、中学生から高校生に至るときである。ルソーには社会思想家、教育思想 家として、『社会契約論』や『エミール』などの作品がある。だが、当時の私には、そのような著作は十分に理解する力はなかったし、ルソーにそのような作品 があることも知らなかった。私が出会いもっぱら読んだのは『告白録』である。一種の小説や伝記のように、青少年にも読みやすかったからだと思う。だから、 私のルソーの理解は、文学的なものだった。 ルソーはスイスのジュネーブに時計職人の子として生まれ、フランスに渡り、そこで初恋の人であるヴァラン男爵夫人に庇護されな がら独学で学問の素養を蓄えた。そして「文明は人間性を向上させたかどうか」というアカデミーから提出されたテーマの懸賞論文に『学問芸術論』で応募して 入選し、それを背景に『人間不平等起源論』を書いた。そこから、ディドロやダランベールといった学者との交流が生まれ、思想家としての生涯が始まる。下層 階級の子供として生まれ育ったルソーだったが、運命の経緯から上流階級の世界で生活することになり、そこで疎外と階級矛盾を体験する。それは、ちょうどル ソーの死後、わずか11年にして起きたフランス革命という歴史的な事件の社会的な前兆を反映している。
私が高校生のころは、1960年代の後半にあたり、日本がいわゆる高度経済成長期のピークを迎えつつあるころだった。東京オリンピック が開催され、東海道新幹線も走るようになった。新幹線のいわゆる新幹線ブルーとアイボリーのツートンカラーの優雅な車体は、その頃の私たち中高生の目にも 新鮮だった。阪急京都線の電車の車窓から眺める外の景色も日々刻々に変化し、見る見るうちに田畑は埋め立てられ、新興住宅地に変わっていった。しかし、そ こには統一ある都市政策や都市計画などの片鱗も見られず、アジア的な無秩序で乱雑な郊外の風景が現れた。 お隣の中国では毛沢東が紅衛兵を使って文化大革命をはじめた。冷戦の構造はいささかの揺るぎも見られなかった。アメリカはベト ナムで北爆を開始した。ベトナム戦争の泥沼化はまだ始まっていなかった。街にはビートルズの音楽があふれ、彼らが来日したときには、大勢の女性ファンが羽 田空港に押し寄せた。 ルソーの『告白録』では年上の女性であるヴァラン男爵夫人に愛される場面などに惹かれた。学校では中学高校とも男女共学だった が、徐々に生まれつつあった異性に対する関心は同級生にではなく、宝塚歌劇の再演を文化祭で演じた上級の女子生徒や、また、通学の電車の中で時折出会う美 しい女性に惹かれた。近所に住んでいるきれいな既婚婦人が家の前を通り過ぎるのを窓から眺めたりもしていた。まだ女性に幻滅も失望も持たなかった時代であ る。 上流階級との生活の中で、やがてヴァラン夫人の寵愛も失い、彼自身の出身階級を自覚させられたルソーは、次第に民衆の階級に自 己のアイデンティティーを見い出すようになる。ルソーは下着や服装なども、豪奢な貴族階級のものから、質素で素朴な庶民のものに着替えはじめる。当時の隣 国の中国でも、周恩来や毛沢東たちの指導者たちは、人民服をまとい、民衆といっしょに貨車を引いたりしていた。江青や王洪文たちが毛沢東の支持を受けて権勢 を振るっていた。当時の朝日新聞やいわゆる進歩的な知識人は、それらを理想社会実現の試みとして評価する者も少なくなかった。 プロレタリア階級の独裁を目指していた共産主義革命は、フランス革命にひとつの模範を見ていた。そして、フランス革命はルソー の『社会契約論』などに現れた思想の影響を受けている。ルソーはそこで「全体の意思だけが国民全員の幸福のために国家権力を行使できる」という思想を明ら かにした。ヘーゲルはこの「全体の意思」を単なる多数意思ではなく、概念として理解しなかったことがルソーの限界であるといっている。 いずれにせよ、ルソーは「全体の意思」が「共同体の意思」となり、それが国民の個々の意思と一致しない限り自由はないことを明 らかにして、民主主義が国民の自由と不可分であることを明らかにしたのである。こうしたルソーの民主主義思想は、日本国民にどれだけ自覚されているか否か はとにかく、国民主権の思想となって現代の日本国憲法の原理にもなって流れている。民主主義とは、国民全体の意思が、市民共同体や国家の意思となることで ある。ルソーの思想に民主主義の淵源を見ることができる。 しかし、ルソーは英国流の代議制民主主義の限界にも気づいていた。国民は政治家を選挙することによって、代議士に自分たちの意 思を代弁させていると一見自負している。しかし、それは一時的なものである。やがて、政治家代議士は、国民の利害から離反し、さらには特権階級化して対立 するまでに至る。 日本の場合には、国民によって選挙された政治家が、職業的行政家である官僚を、支配することも管理することもできないでいる。 そうして彼らは選挙されずに行政権を手にしている。それは、政治家のみならず、官僚の(国民主権を標榜する日本国には「官僚」は存在せず「公務員」が存在 するのみであるはずであるが。)特権化をも許すことになっている。「統治される国民が、同時に統治する者でもある」という、治者と被治者の一致にこそ、国 民の自由があるとすれば、日本国民はまだ真の自由を手に入れていないといえる。不幸な国民は、自分たちの政治家や「官僚」を自由に入れ替える能力をまだ完 全には手にしてはいない。 それにしても、ルソー流の「自由」は、まだ、自由の真の概念を尽くすものではない。その自由と民主主義の思想には、嫉妬や怨恨 からの自由はない。それは基本的に否定の自由であって、肯定の自由ではない。だからこそ、フランス革命も、中国文化革命も、後期においてはその自由は、剥 き出しの凶暴性を発揮することになった。ここにルソー流の民主主義の限界を現実に見ることができる。 そのもっとも象徴的な事件が、連合赤軍などに属する若者たちによって引き起こされた、浅間山荘事件や日航機ハイジャック事件などの一連の事件だった。それらは当時の学生運動の論理的な帰結としておきたものである。ルソーの思想と深いところでつながっている。 晩年のルソーは、植物採集などに慰めを見出しながら『告白録』を完成させ、また、『孤独な散歩者の夢想』を書いて、後年のロマ ン主義文学に影響を残した。また、その自由と民主主義の関する思想はカントなどにも影響を与えている。わが国においては、植木枝盛などの自由民権論者に、 また中江兆民などのフランス系学者を通じて、幸徳秋水や大杉栄などの社会主義者、無政府主義者たちに影響を及ぼしている。 |





















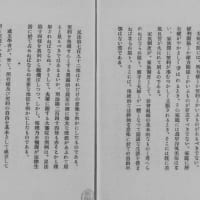







※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます