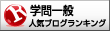日本国憲法論メモノート1
X(ツイッター)@soratineと@myenzyklo に投稿したメモを、このブログの方にも記録しておきます。
昔のツイッターとブログのGOOとが連携できていた頃は、ツイッターに投稿した記事も自動的にブログにも保存できていたので便利でした。
Twitter が X に変わってから、確かに言論の検閲はなくなったかもしれないけれど、新しくX に変わってから多くの点で使い勝手が悪くなったようです。
①
樋口陽一氏の憲法学は、日本国憲法の「護憲」的解釈を強く支持し、特に 立憲主義 と 憲法の平和主義 に重点を置いています。そのため、日本国をイギリスやアメリカ、イスラエルのような普通の主権国家へ改革する際の大きな障害となる点がいくつかあります。
②
樋口陽一氏の憲法解釈においては 「立憲主義=国家権力の制限」 という視点が強調されるため、国家が自己防衛のために持つべき 「積極的主権」(軍事的・経済的な主権行使)が制約される方向に議論が進みます。その結果、国家が 自律自律的に外交・防衛政策を決定する能力 を持つことが否定されます。
③
普通の主権国家は、自国の防衛や外交政策を自律的に決定する権限を持ちます。しかし樋口憲法学の枠組みでは、国家主権を制限すること自体が「立憲的」だと正当化されています。日本国の独立国家としての正当な国家主権の行使さえ制限され、日本国の主体性を回復する上での大きな障害となっています。
④
樋口憲法学では 憲法9条の平和主義 を絶対視し、憲法改正や防衛力強化に対して否定的な立場を取っています。 彼は日本国憲法9条を、「戦後日本の根本原理」 と捉え、軍事力を国家主権の不可欠な要素として位置づけることに強く反対しています。
そのため、自衛隊の存在や集団的自衛権の行使についても、極めて消極的であり、憲法改正論議に対しては基本的に「護憲」の立場から反対しています。
⑥
現実には、イギリス・アメリカ・イスラエルのような国家は、すべて強固な軍事力を持ち、それを国家主権の基礎としています。しかし、樋口氏の憲法解釈では、日本は「武力を放棄すること」が憲法の本質とするために、日本国の普通の主権国家としての在り方を否定することにつながっています。
⑦
もし、日本が普通の主権国家としての性格を取り戻すのであれば、安全保障政策を憲法の制約から解放し、国際環境に適応する形での国家戦略を立案できるようにすることが不可欠ですが、 しかし、樋口憲法学の枠組みでは、憲法の理念が優先され、国家の生存戦略が二の次にされてしまっています。
ヘーゲル『哲学入門』 第一篇 存在 第一部 質 第九節[存在、無、生成]
A. Sein, Nichts, Werden
A.存在、無、生成
§9
Das Sein(※1) ist die einfache inhaltslose Unmittelbarkeit, die ihren Gegensatz an dem reinen Nichts(※2) hat, und deren Vereinung das Werden(※3) ist: als Übergehen von Nichts in Sein das Entstehen, umgekehrt das Vergehen.
(Der gesunde Menschenverstand(※4), die einseitige Abstraktion sich oft selbst nennt, leugnet die Vereinung von Sein und Nichts. Entweder ist das Sein oder es ist nicht. Es gibt kein Drittes. Was ist, fängt nicht an. Was nicht ist, auch nicht. Er behauptet daher die Unmöglichkeit des Anfangs .)
第九節
存在 とは、単純で内容をもたない直接性であり、それは純粋な無を対立物としてもち、そして存在と無との合一が生成 である。無から存在への移行が発生(Entstehen)であり、その逆が消滅(Vergehen)である。
(いわゆる「健全な常識」は、それ自体が一面的な抽象化をしばしば行うように、存在と無の合一を否定する。「存在している」か「存在していない」かのいずれかであって、「第三のもの」はない 。「存在するもの」には始まりはなく、「存在しないもの」も始まりはない。したがって、常識は「始まり」は不可能であると主張する。)
※1
「存在(Sein)」はもっとも抽象的な思考のはじまりである。
※2
はじめの「存在」はあまりに空疎であるため、「無」と区別がつかない。
※3
抽象的な「存在」と「無」という静止的な概念は初めから「動き」をはらんでおり、その移行、運動による合一から「生成」という概念が成立する。「生成」は存在と無という対立する二者をそのうち含む。思考の弁証法的な運動がここからはじまる。無から存在への過程は発生であり、存在から無への過程は消滅である。これら「存在」「無」「生成」の三つの契機は、思考の弁証法的な運動の基本形でもある。ここから論理学が始まる。
※4
「いわゆる健全なる人間の理解」(常識)は、「存在」と「無」を絶対的に分けて、「あるかないか」「白か黒か」的にしか考えられない。これはのちに「悟性的思考」として、その限界が指摘される。
弁証法的な思考は動的に捉える。これは「アナログ」と「デジタル」との関係と同じで、たとえば磁石の陽極と陰極のように、常識、悟性は、両者を分断してとらえるが、実際には陽極と陰極との間には明確な境界はない。ヘーゲルはいわゆる「常識」をここで皮肉っている。
ヘーゲル『哲学入門』 第一篇 存在 第一部 質 第八節[質]
Erster Teil. Das Sein.
第一篇 存在
Erster Abschnitt Qualität
第一部 質
§8
Die Qualität (※1)ist die unmittelbare Bestimmtheit(※2), deren Veränderung (※3)das Übergehen(※4) in ein Entgegengesetztes ist.
第八節
質は直接的な規定性であり、その変化は対立物への移行である。
※1
質(Qualität)とは、「あるものが何であるか」ということ。
※2
質は「直接的な規定性(unmittelbare Bestimmtheit)」と定義される。つまり、媒介されておらず、存在に直に結び付いており、その質が失われればその存在そのものが消滅する。
※3
質の変化(Veränderung)とは、あるものが、対立する他のものへと変化することである。たとえば、生から死ヘ、歓びから悲しみへ。また、水は、0℃以下で氷に変化する。
※4
Übergehen(転化・移行)は、存在するものが、自己を否定することによって他者へと変化する動きのこと。「存在」するものは、有限であるゆえに否定性を含み、その限界を超えると自己を否定して「他なるもの」「対立物へ(in ein Entgegengesetztes)」と転化する。
ヘーゲル『哲学入門』 第一篇 存在 第一部 質 第八節[質]
Erster Teil. Das Sein.
第一篇 存在
Erster Abschnitt Qualität
第一部 質
§8
Die Qualität (※1)ist die unmittelbare Bestimmtheit(※2), deren Veränderung (※3)das Übergehen(※4) in ein Entgegengesetztes ist.
第八節
質は直接的な規定性であり、その変化は対立物への移行である。
※1
質(Qualität)とは、「あるものが何であるか」ということ。
※2
質は「直接的な規定性(unmittelbare Bestimmtheit)」と定義される。つまり、媒介されておらず、存在に直に結び付いており、その質が失われればその存在そのものが消滅する。
※3
質の変化(Veränderung)とは、あるものが、対立する他のものへと変化することである。たとえば、生から死ヘ、歓びから悲しみへ。また、水は、0℃以下で氷に変化する。
※4
Übergehen(転化・移行)は、存在するものが、自己を否定することによって他者へと変化する動きのこと。「存在」するものは、有限であるゆえに否定性を含み、その限界を超えると自己を否定して「他なるもの」「対立物へ(in ein Entgegengesetztes)」と転化する。
ヘーゲル『哲学入門』 第二篇 論理学 第七節 [論理学と真理]
§7
Die Wissenschaft setzt voraus, dass die Trennung seiner selbst und der Wahrheit bereits aufgehoben ist oder der Geist nicht mehr, wie er in der Lehre vom Bewusstsein betrachtet wird, der Erscheinung angehört. (※1)
第七節 [論理学と真理]
科学としての論理学は、自己自身と真理との分離がすでに止揚されていること、すなわち精神がもはや『意識の学(精神現象学)』において考察されるような仕方で〈現象〉に属していないことを前提としている。
Die Gewissheit seiner selbst umfasst Alles, was dem Bewusstsein Gegenstand ist, es sei äußerliches Ding oder auch aus dem Geist hervorgebrachter Gedanke, insofern es nicht alle Momente des An- und Fürsichseins in sich enthält: (※2)
自己自身の確信(自己のうちにある確実性)は、意識にとってのすべての対象を、すなわち外的な事物であれ、精神から生み出された思考であれ――を含んでいる。ただし、それが〈それ自体であること〉(Ansichsein)と〈それ自身にとってあること〉(Fürsichsein)のすべての契機を内に含んでいる限りにおいて、である。
an sich zu sein oder einfache Gleichheit mit sich selbst; Dasein oder Bestimmtheit zu haben. Sein für Anderes; und für sich sein, in dem Anderssein einfach in sich zurückgekehrt und bei sich zu sein. (※3)
Die Wissenschaft sucht nicht die Wahrheit, sondern ist in der Wahrheit und die Wahrheit selbst.(※4)
すなわち、「それ自体である」とは、自己と単純に一致していること、「現存在」や「規定性」をもっていること、「他なるものに対して存在していること」、そして「それ自身にとって存在すること」――これは、他なるもののなかにあっても、それが単純に自己へと立ち返り、自己のもとにあることである。
論理学は真理を 探し求める のではない。論理学は真理のなかにあり、それ自体が真理なのである。
※1
「論理学(Wissenschaft)」とは、ヘーゲル哲学においては体系的な自己展開を行う思考のことである。「Trennung(分離)」は、以前の段階(『精神現象学』)で「意識=主体」と「真理=対象」との対立構造にあったものが、それが「aufgehoben(止揚された)」ことによって、両者が弁証法的に克服されて、精神が自己自身のうちに真理をもつ段階に入ったことを意味する。
「現象(Erscheinung)」に属さない、ということは、現象界の背後にある理念的・概念的な真理の場に到達しているということ。
※2
〈それ自体であること〉(Ansichsein)とは、あるものが、それ自身であり、内在的に規定されている状態で、他者との関係性を持たない「存在そのもの」、客観的存在。
〈それ自身にとってあること〉(Fürsichsein)とは、主体が、自分を他者から区別して、自己を自己として意識している状態であり、自己意識や主体性、自律性を意味している。
Gewissheit seiner selbst(自己確信)とは、『精神現象学』でいう「自己意識(Selbstbewusstsein)」のことで、自己を「知っている」という主観的な確信・信念であり、そこにはあらゆる対象が含まれているが、それだけでは不十分であり、ここで主観と客観が統合されて「真に自己である存在(an und für sich)」であるときにはじめて「真理」となる。
※3
単なる「存在」ではなく、「他なるものとの関係性」を経て、「自分自身に戻ること(=自己同一の再獲得)」という理念の構造が予告的に述べられている。「客観(an sich)」→「主観(für sich)」→「統合・絶対(an und für sich)」というヘーゲル弁証法の三段階の構造が端的に説明されている。これは「理念(Idee)」のダイナミズムでもある。
※4
ヘーゲルはここで「思考(主観)と存在(客観)の一致」をあきらかにし、論理学とは真理の展開に他ならないという。カント以前の哲学では、真理は「対象を発見する」ものであったが、ヘーゲルにおいては、真理とは概念(Begriff)そのものの自己運動である。この前提の上に、その論理は、存在論ー→本質論ー→概念論ー→理念論 へと展開していく。
下に、小室直樹『日本人のための憲法原論』への感想を追記しました。
追記※20250707(月)
上記の本で小室の展開している議論は、ホッブス、ジョン・ロック、ルソー流の「社会契約論」を基盤としており、国家とは国民の自由意志の契約によって成立する人工的な構築物であるという理解に立脚しています。しかし、ヘーゲルはこのような契約論的国家観を「抽象的」かつ「恣意的」として明確に批判しています。国家とは単なる合意の産物ではなく、制度的・倫理的実体として理念的に自己展開していくものです。契約による国家は、一時的・不安定であり、理念国家の持つ内的必然性を欠きます。
小室のこの本で展開している議論は確かに「博識」にもとづいていますが、ヘラクレイトスの箴言を踏まえてヘーゲルは「博識は科学ではない」とも言っています。小室は科学として必然性を追求する意識もみられません。ヘーゲルの『法の哲学』を勉強しなかった彼は理解もできませんでしたから、ヘーゲルが『法の哲学』の中で、ホッブス、ジョン・ロック、ルソー流の「社会契約論」をその意義と限界を指摘してアウフへーベンして論証していることも知りません。だから、恥ずかしげもなく、こんなところでも『契約論的国家観』を繰り返し、日本国民に低劣な「契約論的国家観」を宣伝することになるのです。
また、小室の提案する「個人主義的人権理念の徹底」は、結局のところ「抽象的個人主義」に収束していくことになります。このことによって、個人は、国家の民族的な、歴史的な文脈のなかに位置付けられずに、単なる個人の権利の仲裁装置と化した国家のなかで生きていくことになってしまいます。
たとえば、憲法学者の樋口陽一氏のように、日本国憲法の「第一三条 すべて国民は、個人として尊重される。」という規定を、フランス流の抽象的な個人主義として持ち込み、「個人主義的人権理念の徹底」として我が国の憲法の中に持ち込むと、個人は日本国の歴史的な民族的な文脈から切り離されてしまいます。
国民は抽象的な個人として、民族的な気質や歴史的な人格形成の文脈からも切り離され、その結果として、国民は群衆の一人として、国家としての日本に帰属意識もアイデンティティーも持たない、根無草の国民が増えることになります。家族や会社や学校や地域社会のなかで日本に帰属意識もアイデンティティーも持たない、そうした根無草になった群衆の一人一人が、果たして「夢」や「仲間意識」や利己主義でない「倫理観」をもった国民になるでしょうか。
小室直樹氏は、日本国憲法の問題を、日本人が西洋的な憲法理念を十分に理解・共有していないことに求めています。それは、「憲法の理念」が日本社会に対して外から導入された単なる規範であること、すなわち外在的な観念であることを前提にしています。
しかし、このような憲法理念を外在的な基準として位置づける理解そのものが誤りだと思います。ヘーゲルの『法の哲学』の立場においては、「国家理念」はあくまで内在的に展開する実体として捉えられます。国家とは、民族・文化・歴史が倫理的な実体として自己展開していくことによって初めて形成されるものです。
したがって、小室がいうような「理念の不在」を、日本社会にとって外的な理論や思想を単に「理解」し「取り込む」ことによって解決すべき問題とするのは、国家理念の真の本質を見誤っています。
小室の議論は、ルソー流の「社会契約論」を基礎としています。この立場では、国家とは「国民の自由な意志による合意・契約」によって成立し、その合意の理念的な理解が欠けているため憲法が機能していないと考えています。
これに対して、ヘーゲル哲学の立場では、国家を「合意」や「契約」に還元する見方については明確に批判しています。ヘーゲルによれば、国家は個人の恣意的な契約によって人工的に作られるのではなく、個人が倫理的な実体(家族や市民社会)を経て普遍的な理性と統合されていく有機的な実体としてとらえられます。
小室のモデルでは、理念については、あくまで「意識的に選択された規範」として理解されていますが、ヘーゲルの「法の哲学」の立場からすれば、真の国家理念は、意識以前の共同体的生活や制度的な枠組みそのものに内在しています。理念を「同意の不足」程度の問題としてとらえる限り、真の国家理念には到達できないでしょう。
小室が指摘する「理念の不在」においては、結局「個人主義的な人権観」や「民主的参加の理念」を十分浸透させるべき、という思想に還元されてしまうでしょう。この考えは「抽象的な個人主義」の理念の段階にとどまってしまい、歴史や民族、共同体的な連帯という具体的な倫理的実体を軽視するか、無視することになってしまいます。
ヘーゲルの立場からすれば、「抽象的個人主義」は理念国家形成を阻害することになります。なぜなら、国家は単なる個人の利益の調整機関ではなく、個人が国家の普遍的理念に内在的に結びつき、自己をその中で具体的に実現していくものであるからです。小室のいう「理念の不在」は、実際には抽象的な個人主義を強化する方向に向かうため、理念国家の視点、立場からはかえって国家の理念的な実現を妨げる要因になり得ます。
国家が実際に機能するためには、法律や制度が市民の道徳感情や、家族、職業など倫理的生活(Sittlichkeit)と内的につながる必要があります。小室の「理念の不在」論は、この倫理的実体としての制度や慣習を考慮せず、理念を外的な観念に還元しまい、単純に個々人の理念の無理解や契約同意の問題として矮小化することになります。
国家理念が実効性を持つためには、人々の生活と制度が理念と有機的に結びついていなければなりません。ヘーゲルの視点からは、国家理念の問題を「理解不足」や「教育不足」といった啓蒙的課題として片付ける小室の議論では根本的に不十分です。
小室が「理念の不在」として批判するのは、国民の憲法に対する理解の不足ですが、これは法の本質を個人の「恣意的な理解」に委ねる危険性を伴います。ヘーゲルは法の本質を「理性の自己展開」と捉え、法の妥当性をたんなる主観的同意に還元することを厳しく批判します。
法や制度の妥当性とは、主観的な理解や合意ではなく、理性的・論理的必然性に裏打ちされるべきであるとヘーゲルは主張しています。小室のように法の妥当性を「同意」や「理解」に還元すれば、結局、法は国民感情や政治的な都合によって容易に恣意的に変容しうる脆弱なものとなります。小室は「法の支配」の真意をとらえきれないでいます。
以上のように、小室が本書で主張する「理念不在論」は、国家理念を外的基準によって理解し、契約的合意という個人主義的な枠組みに還元してしまう限界を持っています。これに対しヘーゲルの理念国家論からすれば、理念とは外的理解や同意ではなく、民族的・歴史的制度の内的必然的な展開そのものです。
2025(令和7)年06月03日(火)雨。聖書とヘーゲル哲学
久しぶりに終日雨が降り続いた。
X(ツイッター)@myenzyklo でノートを取りながら、ヘーゲルの宗教哲学の最終章「第三部 絶対宗教 Ⅲ 3一般的現実性への精神的なものの実現」(木場深定訳)の個所を久しぶりに再読する。
「問題はただ、感情の内容が真理であるかどうか、それは思考において真実の内容として証示されうるかどうか、ということだけである。哲学は主観そのものが感じるところのものを思考し、そして感情と折り合うことを主観に委ねる。このように感情は哲学によって拒否されはしない。むしろそれはただ哲学によって真実の内容を得るのである。
しかし思考が具体的なものに対して対立し始める限り、思考の過程はこの対立を克服して、これを宥和に到達させることである。この宥和が哲学である。哲学はその限り神学である。それは神の自己自身との、また自然との宥和を提示する。すなわちそれは、自然・他在そのものが神的であり、そして有限精神が一部は自己自身において自己を宥和に高め、一部は世界史においてこの宥和に達することを示すのである。」
聖書の研究のためにヘーゲル哲学に入ったことは正しかったとあらためて思う。ヘーゲル哲学は聖書の真理の論証である。宗教と同じく、あるいはそれ以上に哲学もまた深い精神的な充足をもたらす。聖書が先でヘーゲル哲学は後だ。ヘーゲル哲学はなくても聖書はあるが、その逆はない。