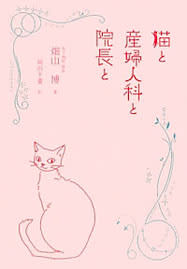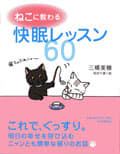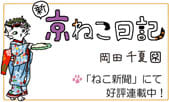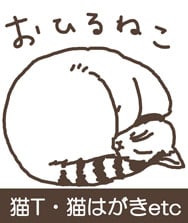ねこ絵描き岡田千夏のねこまんが、ねこイラスト、時々エッセイ
猫と千夏とエトセトラ
カレンダー
| 2025年8月 | ||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
| 1 | 2 | |||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| 31 | ||||||||
|
||||||||
本が出ました
| イラスト(431) |
| 猫マンガ(118) |
| 猫じゃないマンガ(2) |
| 猫(512) |
| 虫(49) |
| 魚(11) |
| works(75) |
| 鳥(20) |
| その他の動物(18) |
| Weblog(389) |
| 猫が訪ねる京都(5) |
| 猫マンガ「中華街のミケ」(105) |
| GIFアニメーション(4) |
最新の投稿
最新のコメント
| 千夏/春のお茶会 |
| an/春のお茶会 |
| 千夏/節分 |
| タマちゃん/節分 |
| Chinatsu/銀閣寺~椿の回廊2024 |
| WhatsApp Plus/銀閣寺~椿の回廊2024 |
| 千夏/残暑 |
| タマちゃん/残暑 |
| 千夏/「豊穣」 |
| タマちゃん/「豊穣」 |
最新のトラックバック
ブックマーク
|
アトリエおひるねこ
岡田千夏のWEBサイト |
| それでも愛シテ |
| 手作り雑貨みみずく |
| くろうめこうめ |
| 忘れられぬテリトリー |
| 猫飯屋の女将 |
| 雲の中の猫町 |
| イカスモン |
| タマちゃんのスケッチブック |
| あなたをみつめて。。 |
| 眠っていることに、起きている。 |
| ノースグリーンの森 |
プロフィール
| goo ID | |
amoryoryo |
|
| 性別 | |
| 都道府県 | |
| 自己紹介 | |
| ねこのまんが、絵を描いています。
ねこ家族はみゆちゃん、ふくちゃん、まる、ぼん、ロナ。お仕事のご依頼はohiruneko4@gmail.comへお願いいたします。 |
|
検索
gooおすすめリンク
| URLをメールで送信する | |
| (for PC & MOBILE) | |

夏のシロクマ

シロクマ、シロクマと言っているけれど、正式な名前はホッキョクグマである。この極寒の地に住むシロクマが、かき氷とかアイスキャンディーとかエアコンのマークになって、日本の夏にはよく見られる。
子供だった昔、ある夏の日に、祖母とデパートへ行ったことがあった。白い日差しが照りつけるバス停でバスを待っていると、やがて、陽炎が立ち昇りそうな夏の一本道の向こうに小さくバスが見え、車の流れに見え隠れしながら少しずつ近づいてきた。祖母が目を凝らし、「よかった、シロクマのマークや。シロクマのバスは冷房がかかっているのん」と教えてくれた。今でこそ京都の市バスはすべてエアコン完備だけれど、昔は真夏でも窓を開けて走っていたのがあった。それ以来、私はバスが通るたびに、シロクマのマークがついているか確かめるようになった。
そのあと、祖母とシロクマのバスに乗ってデパートへ行ったはずなのだが、デパートで何を買ってもらったとか、そんな記憶は一切ない。覚えているのは、ただシロクマのバスが近づいてくる場面だけである。
クヌート君から連想して、そんなシロクマを思い出した。
コメント ( 6 ) | Trackback ( 0 )
パンダにハマる

きっかけはというと、一歳の息子が、パンダの形の小さなクリップで遊んでいたことだ。パンダをぴょこぴょこと動かして、「にゃあにゃあ」と言うので、「パンダはにゃあにゃあとは鳴かないよ」というと、今度は「わんわん」と言う。「わんわんとも鳴かないなあ」と言いながら、パンダが本当はなんと鳴くのか、聞いたことがないと思った。そこでネットで調べてみると、同じように、パンダの鳴き声を子供に尋ねられて困っているお母さんからの質問への回答の中に、パンダの声が聞けるサイトを紹介しているものが見つかった。さっそく聞いてみると、ちょっとカタカナでは表記できないような声である。馬と羊の中間くらいというコメントもあったが、無理に書くと「めひぃぃん」という感じだろうか。
別の回答には、パンダのライブ映像が見られるサイトが載せてあった。クリックすると、アメリカのスミソニアン動物園のページである。あ、パンダ!パンダが、岩や木のあいだをうろうろしている。時間は朝の7時頃。動物園は開園前で静かである。自動追跡カメラのようで、パンダの動きにあわせて向きを変えたり、いくつかのカメラに切り替わったり、ズームされたりする。
しばらくして、ふたたび接続してみると、あちらの時刻は8時頃。パンダは両足を投げ出すようにどしりとすわって、笹の葉をむしゃむしゃと食べている。ご飯の時間らしい。
以来、パンダは今なにをしているだろうと、海の向こうのパンダの様子が気になって、ついつい開いて見てしまう。なにしろ、かわいい。いったいどういう進化の都合で、あんなに愛嬌のある模様をしているのか。パンダの生息している場所にはこれといった天敵がいないというようなことを聞いたことがあるけれど、あの緊迫感の感じられないもたもたとした仕草も、それゆえなのだろうか。
お昼頃には、動物園にやってきた子供たちの歓声をいっぱいに浴びてのしりのしりと歩き回り、夜には、岩の上にどてっと横になって、ころころした背中をこちらに見せている。あの黒い目の奥でいったい何を考えているのか、パンダはいつもマイペースである。
異国のパンダの毎日を24時間リアルタイムで見ることができる。まさにネットの恩恵である。
コメント ( 8 ) | Trackback ( 0 )
眠れない熊たち

えさをとることが難しい冬の山でクマたちは冬眠するのだから、毎食きっちり与えられる動物園のクマは冬眠する必要がないにちがいない。
だがこの冬は、野山に住むクマも眠れずにいるらしい。例年では真冬にクマの姿を見ることのない地域で、クマの目撃情報が相次いでいるという。専門家のあいだでは、暖冬のため冬でもえさが豊富にあるから冬眠する必要がないのだという意見と、反対にえさが不足していて冬眠できるだけの栄養を蓄えることができなかったのだという意見に分かれているらしい。
理由はどうであれ、山の住み家をはなれて人の前に姿を現し捕獲されたクマは、その9割が殺処分されている。殺すという方法が一番低コストなのだろうけど、世の中には無駄金があふれている。動物たちの命を救うために使うお金がもう少しあったっていいと思う。
暖冬余波?冬眠できず親と離れ…民家の床下に子グマ(読売新聞) - goo ニュース
コメント ( 2 ) | Trackback ( 0 )
ニシキヘビのタマコ

ビルマニシキヘビは、いつ見ても横腹をガラスに押しつけ、眠っているのかじっと微動だにしないので、私は珍しく思い、急いで見に行った。
浅く水の張ったプールの上で、確かにニシキヘビはこちらに首を突きつけ、舌をちろちろやっている。
名前はタマコ。週に一度ウサギを食べて、月に一度うんちをする。
ヘビといえば、このあいだ、子供番組の人形劇にツチノコの話が出てきて、懐かしく思ったところである。幻のヘビと言われるツチノコは、ヘビだけれど胴体はずんぐり、ジャンプ力がすごいとか、動きが早いとかいう特徴がある。子供の頃に持っていた、いるかいないかわからないような生き物ばかりを集めた図鑑に載っていて、ネッシーとかイッシーとか雪男とかにくらべると、まだいそうな部類であった。その頃はテレビでもツチノコを見たとか何とか、ときどきやっていたように思うが、今ではさっぱり聞かない。
その図鑑を見た父が、前に山を歩いていたとき、突然横から飛び出してきてくるぶしあたりにぶつかり、またすごい速さで茂みの中に消えていった生き物があって、なんだかよくわからなかったのだけれど、あれはもしかしたらツチノコだったのかな、などと言っていた。
人形劇に出てきたツチノコの正体は、大根を丸呑みしたヘビであった。父の足首にぶつかったのも、何かを呑んだばかりのへびだったかもしれない。
動物園の爬虫類館では、ヘビの飼育室の前に、「さわって確かめてみよう」と、ヘビたちが脱ぎ捨てた抜け殻が箱に入れられている。おじいちゃんと一緒にいた女の子が、恐る恐るながら、箱の中の抜け殻に手を伸ばそうとしたとき、「そんなもの触ったら、絶対抱っこしないからね!」とおばあちゃんがぴしゃりと言った。
手を引っ込めてしまった女の子を見て、彼女の可能性がひとつ失われてしまったようで、私は残念に思った。
コメント ( 8 ) | Trackback ( 0 )
イルカショーのイルカたち
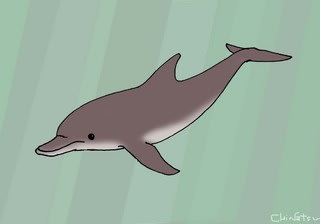
今年のお正月は鳥羽の方へ行って、水族館でイルカショーやアシカショーを見た。こういうショーを見るたびに思うことは、そこで飼われているイルカやアシカたちが、幸せだろうかということである。映画「グラン・ブルー」では、主人公がショーのイルカを夜中海に連れ出して、自由に泳がせてやるという場面があった。野生動物は野生の状態が一番いいのだという人は多いと思う。しかし野生はとても厳しい。釣り針のかかった魚を知らずに飲み込んでしまうことだってあるだろう。
かつてはショーの動物たちが劣悪な環境で飼育され酷使されて問題になったということもあったように思うが、遅れがちな日本の動物愛護もようやく広まってきたのか、最近そういう話題は聞かない。自由奔放に生きることはできないけれど、えさの心配もなく、健康も管理され、もしかすると遊び好きのイルカたちはショーを楽しんでいるかもしれない。
ネパールのある寺院では、諸々の事情で保護した何頭ものトラを、野性に返すことなく寺院で世話している。野生にこだわる必要はない、トラたちが幸せならそれでよいのだと、寺院の僧侶に迷いはない。
野生で生きるか、人の手の中で生きるか。そのどちらが幸せかは、動物に直接聞いてみることができない以上、知るすべはない。だけどそれぞれに良し悪しがあって、はっきり野性がいいのだとかそうではないとか、断定することはできないだろう。
猫を室内で飼うか外飼いにするかという選択も同じだ。我が家では室内で飼うことを選択した以上、その範囲内でみゆちゃんが最大限幸せな「猫生」を送れるよう心を尽くすばかりである。
コメント ( 2 ) | Trackback ( 0 )
動物園干支さがし(2)~カバ

このあいだ動物園へ行くと、いつもは水中にいて顔の一部だけしか見えないカバが、運動場に出て飼育係の人におやつをもらっていた。それまでカバは不細工だというイメージを持っていたが、このように全身をよく見ると、なかなか愛嬌のある動物である。
飼育係の人がカバにエサを見せると、カバはその特徴的な大きな口をあんぐりと開けた。
「ね、大きな口でしょう」係りの人が、カバの口にエサを投げ入れる。私はすごい、と同意した。
「でも、よだれがね」次のエサをねだってカバがまた大口を開けると、上あごと下あごのあいだに粘っこいよだれが数本糸を引いた。大いに同意。係りの人は、よだれが手につかないようにエサをカバの口に放り込んだ。
飼育係りの人がカバのエサを手に取らせて見せてくれた。手のひらに入るくらいの巨大なドッグフードという感じである。薄緑色の円筒形で堅い。よく見ると草の筋のようなものが混じっている。
「干草ですか」
「そう、干草を固めたものです。カバにはカバ用、ゾウにはゾウ用と、それぞれの動物専用のエサがあります。これで終わりだよ」最後のエサを口に入れてもらうと、カバはあごを上へそらして、こちらにのどのあたりを伸ばして見せた。掻いてほしいのである。飼育係の人は、ごしごしと大きなストロークでカバののどを掻いてやった。カバもこんなに馴れるものだとは。
確かに、カバの体型がブタに似ているといわれるとそんなふうにも見える。また、温和そうに見えるカバだが、その性格はなかなか獰猛であるらしい。しかしのんきにあごを上げてのどを掻いてもらうカバを見ていると、猪突猛進の語源であるイノシシと同じ仲間だというのは、やはり不思議な感じである。
コメント ( 12 ) | Trackback ( 0 )
動物園干支さがし(1)~ミニブタ
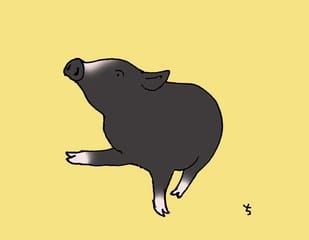
が、今はいない。どうしていなくなったのかはわからないが、イノシシのいなくなった動物園で、ほかに干支に近いものはなにかと言うと、ミニブタがいる。ブタはイノシシを家畜化したものだ。また日本では干支に入るイノシシだが、ほかの東アジアや東南アジアの国々ではブタが干支の最後だという。
動物園のミニブタは、「おとぎの国」という動物たちと触れ合えるスペースにいる。大きさは中型犬くらい、黒毛のこのブタは、おすわり、お手、回れなど、犬のような芸ができる。ブタが芸を披露するたびに、こどもたちは拍手喝采。飼育係りのおじさんは得意顔だ。
しかし芸をするブタなんて珍しいと思ったら、意外といるらしい。ロシアではブタオリンピックなるものが開催され、ブタたちが水泳や球技を行うという。
さらには、麻薬豚というのもいた。ブタの嗅覚は犬よりも優れているそうで、それを生かして麻薬捜査に使うという試みが外国の空港でなされたが、麻薬よりも食べ物に反応してしまい断念されたというからブタらしい。
ブタでも芸や仕事をするというのに、われらの猫はやはり何もしない。まあ、猫はそれでいいのだけれど。
コメント ( 6 ) | Trackback ( 0 )
ともに暮らせば顔も似る
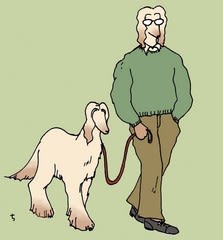
シマウマを見に行くとちょうどおやつの時間で、箱の中に青草の束ねたものが並べてあった。そばについていた飼育係の人に勧められて青草を手に取ると、すぐにシマウマが柵の向こうから駆けてきて、差し出した手からあっという間に草の束をくわえ取った。
シマウマの係の人は面長で愛想のいい男の人だったが、動物園の飼育係の人はみな、それぞれが担当している動物にどことなく雰囲気が似ている。カバの係りの人はおっとりした感じの人であるし、トラやライオンの担当の人には精悍な雰囲気が漂って、笑うと八重歯がちらりと見える。もともと似ているからその動物の係を選んだのか、担当しているうちに似通うようになったのか。
ペットは飼い主に似ると言うが、飼い主がペットに似るのとどっちだろう。子供の頃、家にシェットランドシープドッグがいたが、その犬と父が似ていると散歩で出会う人がよく言った。また、近所にアフガンハウンドを飼っている家があって、そこのご主人も犬とそっくりである。
私も愛猫みゆちゃんに似ることができるなら、これほどうれしいことはない。しかし残念ながら、いまだかつて似ているねと言われたことはない。
コメント ( 4 ) | Trackback ( 0 )
| 次ページ » |