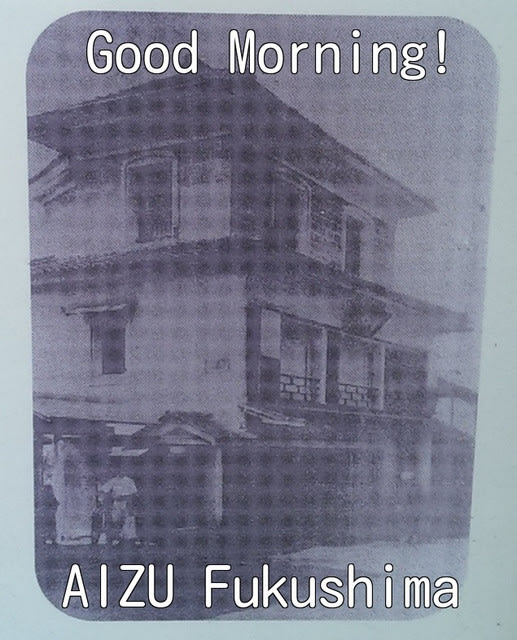おはようございます。旅人宿 会津野 宿主の長谷川洋一です。
「域内調達率」という言葉があります。
販売される最終商品の原材料や加工工程が、どの程度地域内で行われるかということを言います。
さらに「域際収支」という言葉もあります。
これは地域内の生産額のうち地域外に販売しているものと、地域外から流入した生産物の差を言います。国と国とでは、貿易額と呼ぶものと同じものです。
ちなみにこの「域際収支」。福島県によると、会津地域の域際収支は、移輸出額7876億円に対し、移輸入額8480億円で、年間603億円の赤字となっています。つまり、会津は他地域からモノを買ってばかりいる赤字体質な地域であるということになります。
さて、先日、観光に関する講演を聴く機会がありました。
そこで得た知識に、「観光経済波及効果」=「旅行客数」×「客単価」×「域内調達率」という式がありました。
「旅行客数」と「客単価」は簡単に分かるけれど、「域内調達率」については、あまり創造がつきません。
そこで、宿屋視点で考えてみたいと思います。
宿屋という職業は、仕入としては食料品が大きな部分を占め、次に水道光熱費、人件費が主な調達物品です。
まず食料品から見てきましょう。
参考として、「これからの地域再生」(飯田泰之編)からデータを引いてみます。
ここで取り上げられていた山口市の品目別出荷先割合によると、市内の調達率は以下のようになっていました。
肉 0%
麦 0%
花 3%
野菜 5%
果物 16%
米 74%
ここでは、市内に直売所があるにも関わらず、市民の多くが食品を調達するスーパーマーケットなどで取り扱う品物の多くが、外から調達されていることにより、このような数字が現実として示されていました。
わが町会津美里町のことも、近いうちに調べてみたいと思いますが、感覚として大きくかけ離れているとはあまり思えません。
山口市では、この実状を把握したうえで、3つのことを実行したそうです。
1つは地元スーパーのバイヤーと生産者の商談の場の設定すること。山口市では、スーパーと商談すると買いたたかれると思っていた生産者が大半だったものの、バイヤーは市場から仕入れる額を熟知しており、かけ離れた買値を要求することはなかったと言います。
2つめは、生産者とスーパーの相互視察。スーパーも生産者も、市場取引で要求される途中の状態である野菜の箱詰めなどを必要としないことに気づき、スーパーのバックヤードで実施した方が良いことと、生産者側で実施した方が良いことなどの、流通過程での課題解決を図ったところ、両者にとってより良い方法を構築できたとのことです。
3つめは、定番商品の開発と市内生産および物流網の構築。市内の標高差などを利用し、長い期間、市内で生産・販売できる体制を考えたり、時間差の収穫スケジュールを設定することにより、収穫工程ばかりを行う収穫屋さんが収穫機械などを効率よく使えるようにしたり、また、収穫物を運ぶトラックなどの機材も効率性が増したりしました。生産コストの低下に大きな貢献を達成し、利益額が増す結果を得ました。このような地域に最適な生産工程と物流を考えることです。
これらにより、生産者としては、生産コストを下げることができるし、消費者としては、新たな出費なしに、地域の生産品を日々食卓で味わうことができるようになりました。
これは観光分野の話ではありませんが、域外から買っていたものが少なくなることで、地域の域際収支にも貢献するし、地域の豊かさが向上し、「住みたい」と思う層の流入に貢献をしていることがわかるものです。
観光にとっても、こういう改革は域内調達率を相当向上させる効果があり、観光によるまちづくりに大きな貢献をします。
山口市の例では、さらに世帯ごとの食料品消費額(年あたり)も示されていました。
米 18,795円
大豆製品 26,147円
パン・めん等小麦製品 95,840円
生鮮野菜 150,753円
畜産・酪農品 272,480円
山口市の方だけが「畜産・酪農品」を好むとは到底思われないので、これも全国的にほぼ同じような結果になると思います。
なんと米の15倍もの額を、畜産・酪農品に支出しているのです。
畜産・酪農品は、生産過程で家畜が食べるエサがどうかと言うことが問題となります。
地域の生産物を食べて育っていればよいですが、ほとんどが域外からの調達飼料というのが実際です。
山口市では、空き農地でトウモロコシを主とした飼料栽培に取り組み、域内調達率と域際収支の向上に役立てる取組も開始しています。
このように、域内調達率と域際収支からモノゴトを考えると、人・もの・カネを域内で流通させることを考えることが、地域を豊かにする王道であるようです。
次に、水道光熱費のことを考えてみましょう。
水道は、川から流れてくる水を取水したものが元ですので、これはほぼ域内調達と言ってよいでしょう。
暖房用の石油やガスについては、ほぼ100%が輸入品です。ここは、木材などの地域バイオマス資源への転換が域内調達に大きく貢献すると思われます。
電気は、地域内の再生可能エネルギーへの転換が、域内調達に大きな貢献があるだろう。
人件費については、ほぼ域内調達と言ってよいでしょう。
観光だけではなく、すべてのことについて「域内調達率」と「域際収支」を考えることは、地域のまちづくりにおおいに関係がありそうです。
「これからの地域再生」では、この取り組みをあらわす言葉として「山口市ファースト」という言葉が使われていました。
会津美里では、「美里ファースト」を掲げ、観光DMO組織を立ち上げたいなと思う今日この頃です。
※コメントは、旅人宿会津野Facebookにて承ります。
※ご予約は、旅人宿会津野ホームページにて承ります。