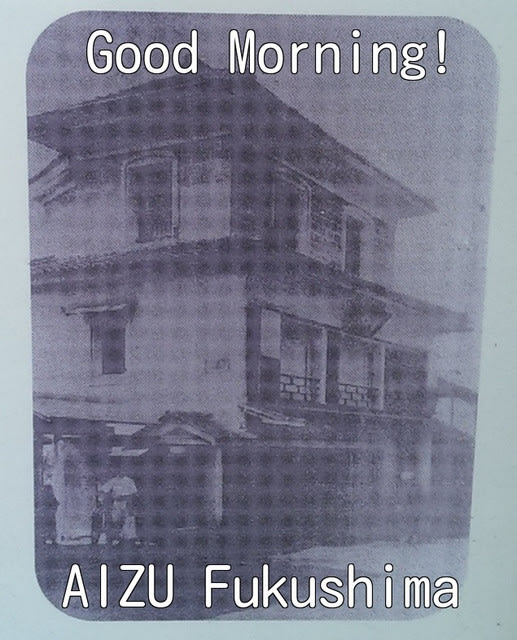おはようございます。旅人宿 会津野 宿主の長谷川洋一です。
昨日のエントリー【会津野】ショック・ドクトリン で、下巻を早く読みたいと言ったにもかかわらず、並行して読んでいた「キッズ・ファイヤー・ドットコム」(海猫沢めろん著)を、つい読んでしまいました。
この本は小説なので、現実で起きていることとは違うものの、社会で起きていることをとてもよく観察し、よく考え、物語を作成している様子が強く伝わってくる作品でした。
一番心に残ったのは、「チルドレンファースト」という言葉。明らかに「都民ファースト」から創造したものだと思いますが、物語では、主人公が東京都知事に就任し、子育て向けの政策をどんどんと実行します。2020年に予定されているオリンピックを中止し、子育て予算に振り向けます。さらに、建設中の新国立競技場も工事を中止し、巨大保育園へと転用してしまう。
この話の背景には、既得権益と富の大半を持つ高齢者から、子育てをする資金を寄付形式で移転させるクラウドファンディングサイト「kids-fire.com」を通じる話が前段にあります。そこには2014年にベストセラーとなった「その問題、経済学で解決できます」(ウリ・ニーズィー、ジョン・A・リスト共著)が示した、「一度寄付いただければ、もう2度と寄付のお願いはしません」という寄付形式を取れば、そうしない場合より多くの寄付が集まるという経済学の実験結果が盛り込まれていたりします。
実際にアカデミックで研究されていることが、かなり盛り込まれているのです。
経済学と言えば、先日、「収穫逓増」と「収穫逓減」という概念を知りました。
収穫逓増とは、たとえば、ある自動車工場で生産量を増大させればさせるほど一台あたりの生産コストが低下していく、つまりは有利になっていくというとき、この工場は生産規模に関して収穫逓増であると言います。
一方、収穫逓減とは、ある一定の農地で働く人が多くなればなるほど、一人あたりの収穫量が減少する、つまりは不利になっていくというとき、この農地は労働投入に関して収穫逓減であると言います。
これは、ある一定のインフラがあり活用の余地がある場合には、人口増加により地域経済が成長するけれど、耕作面積のように頭打ちのインフラの場合は、人工が増加するとむしろ経済活動が低下する議論に出てくるものです。
これを高齢者の働き手に応用すると、定年延長や働き方改革で働く期間を長くすることは、収穫逓増で経済成長するか、それとも、若年者の労働を奪い収穫逓減するかということを考えさせられるものです。
収穫逓増する場合は、高齢者も若年者もハッピーですが、収穫逓減する場合は、高齢者を支える年金の担い手が払えなくなることになり、高齢者も若年者もアンハッピーなことになります。
なので、収穫逓増を目指すしかないのですが、ほとんど経済成長しない時代が長く続いている現実を見ると、収穫逓増を目指すことは無理なのではないか?と、多くの人が感じているのも実際でしょう。
そういう社会状況のなか、新たな妙手として映るのがこの作品であり、現実的に不可能ではないなと思うところも多々あることに感心しました。
人口減少社会に生きるいま、収穫逓減を味方につけるようなことも考えなければと思わされる作品です。
今日も素敵な一日を過ごしましょう。
※コメントは、旅人宿会津野Facebookにて承ります。
※ご予約は、旅人宿会津野ホームページにて承ります。