米国勢調査局の『世界人口時計』によれば、地球上の人口は2月25日午後7時16分(米国東部標準時)に65億人を突破するという。
http://www.census.gov/ipc/www/popclockworld.html
人口増加がいずれ食料生産を上回るだろうと予測したことで知られる
18世紀の経済学者、トーマス・マルサスがこの数字を聞けば
仰天するに違いない。
マルサスが、主著『人口論』[邦訳中央公論新社刊]を執筆した
1798年当時、地上を歩き回るホモサピエンスはわずか10億人程度に
過ぎなかった。 それが今や、生きて呼吸をする人間が65億人という
空前の数字に達しようとしている。
「マルサスが驚くのは人口の多さだけではないはずだ。
全体の約5分の1が裕福に暮らし、半数以上が平均的な豊かさを手に
していることにも目を見張るだろう」と、ロックフェラー大学と
コロンビア大学で人口統計学を研究するジョエル・コーエン教授は語る。
http://www.census.gov/ipc/www/popclockworld.html
「一方で、人口の4分の1ないし3分の1の貧困層が苦しい生活にあえいでいる
事実については、それほど驚かないはずだ」
絶え間なく増えつづける世界人口時計の数字は、毎秒4.1人の
赤ん坊が誕生し、1.8人が死亡しているとして計算されている。
実際の世界人口を正確に数え続けることがいかに難しいかを考えれば
この時計の数字が推測値に過ぎず、誤差があるのもいたしかたない。
しかし、世界時計が示す重要な傾向は、人口統計学者たちの
共通認識に符合する。 (人口は増加の一途をたどっているが
数十年前と比較して人口増加率は低下している)
コーエン教授の推計によると、世界人口の年平均増加率は、1965年から
1970年にかけて2.1%のピークに達した後、現在の1.1%まで
大幅に低下したという。
「驚くべき低下だ」と語るコーエン教授は、著書『新「人口論」
生態学的アプローチ』[邦訳農山漁村文化協会刊]の中で
地球は人口増加に耐えられるかという問いを探求した
(答えを一言で表すなら、「状況次第」)。
現在、世界人口の相当数を占める人が暮らす多くの国で、出生率が
1人の女性が一生の間に生む子の平均数が2人を割っている状態
「置換水準以下」になっている。
こうした少子化国に属するのは、旧ソ連諸国、日本、ヨーロッパの
大半の国々だ。
人口統計学者は人口増加率低下の原因として、避妊方法の普及と
先進国の人々が子どもを生まなくなった点を挙げる。
しかし一方では、1人の女性が一生の間に平均7人もの子を生む
イエメンなど、出生率の高い国もある。
人口増加率がとくに高い国は、アフリカ、中東、南アジアの
最貧地域にかたまっている。
米国の人口も、移民の増加を背景に、一貫して増えつづけている。
今年の後半には3億人に達する見通しだ。
国勢調査局の予想では、世界人口は2012年に70億人に到達するという。
『ポピュレーション・レファレンス・ビューロー』の人口統計学者
カール・ホーブ氏は、一般に都市部の方が地方よりも出生率が
低いことから、都市化が人口増加率の低下の一因と見ている。
1950年当時、都市とみなされていた地域に住んでいたのは、人口の
30%にも満たなかった。 国連の予測によると、来年には世界人口の
半分以上が都市部で暮らすようになる。
人口増加が進む中、研究者たちの間では、地球が実際にどのくらいの
人口を養えるのか(マルサスの時代から変わらぬ議論)について
諸説が飛び交っている。
バングラデシュやルワンダなどの国は、明らかに人口過密と判断できると
ホーブ氏は指摘する。 しかし、インドなど他の地域で、人口過密が
貧困にどの程度影響しているのかを見極めるのは、他にも
社会的要因や経済的要因などが考えられるため、それほど簡単ではない。
維持可能な人口の上限を試算する数学的モデルを考案する動きもある。
国勢調査局の人口時計を模して作成されたあるモデルは、世界の人口と
限りある耕作可能な土地の広さを計測して比較している。
いっぽうコーエン教授の試算では、地球上に年間9000立方キロメートルの
淡水の供給があるとして、それによって育てた小麦で世界中の人間に
毎日3500カロリーを与えると仮定すると、地球上で約50億人しか
暮らせないという。
しかし、こうした試算のための数式は、さまざまな要因によって
変わってくる。 農法の変化、淡水化技術の効率化といった要因によって
地球が養える人口が増加する可能性もある。
生活習慣の変化(たとえば、安価に生産できる新たな食料源を
受け入れること)にも似たような効果があると、コーエン教授は指摘する。
「こうした試算はたいてい、文化の役割を無視している。
小麦は食料とみなすが、たとえば、培養した単細胞藻類は食料ではないと
定義したうえでの話なのだ」と、コーエン教授は語った。
[日本語版:佐藤純子/岩坂 彰]














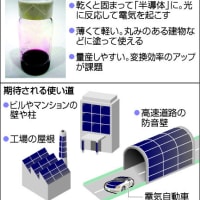

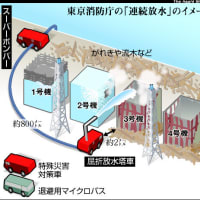



※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます