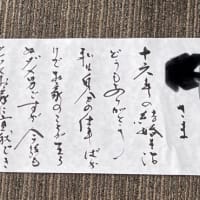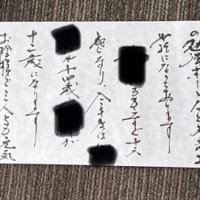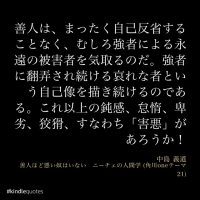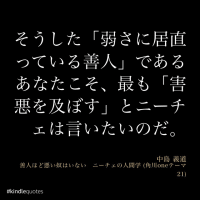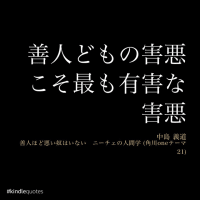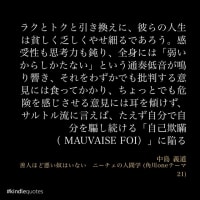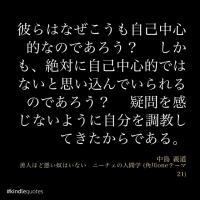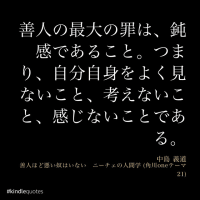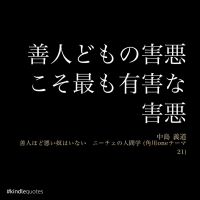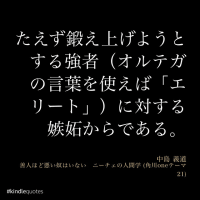【執筆原稿から抜粋】
タイトル:コンプライアンスとインテグリティの歴史
インテグリティというと日本人には新しい用語に聞こえますが、聖書訳にも使われるような古い言葉です。
He is a man of integrityという表現は、昔から英語圏では最高の褒め言葉です。和訳すると「彼は人格者だ」に近いです。
コンプライアンスがアメリカで盛んになる前、企業の不祥事防止対策として、インテグリティとコンプライアンスは拮抗していました。
組織の理想に向かう過程の中で悪い点を治す「太陽」のようなインテグリティ戦略と、悪い点をピンポイントで治す「北風」のようなコンプライアンス戦略の両者があったのです(2021年刊行拙著『インテグリティ』52頁)。
ところが、1991年にアメリカで連邦量刑ガイドラインが制定され、取締役がコンプライアンスプログラムを導入すれば株主代表訴訟から免責されることになりました。
そのため、訴訟社会アメリカの取締役の保身に好都合なコンプライアンスが、世界に広がりました。
しかし、取締役の保身は会社法で手当できるようになり(2002年商法改正における役員の責任軽減)、株主代表訴訟も少ない他国では、コンプライアンスの意義は薄れています。
むしろ、コロナ禍を経てテレワークが広がり、組織風土を消極的で他責的にするコンプライアンスのデメリットがより強く認識されるようになりました。
そこで、インテグリティの意義が再認識されています。
特にプライム上場企業では「インテグリティを知らなければ恥ずかしい」と認識されるようになりました。