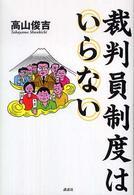
裁判員制度では、検察側、弁護側が、裁判官が行った質問に対する裁判員候補者の回答を聞いたうえで、理由を示すことなく、その裁判員を失格させるシステムが導入される。このこと自体、偏見に満ちた選択をする可能性があるため、問題だと思うが、何と、さらに、考えられないような問題をはらんでいることが社民党・保坂議員の質問の結果、明らかとなった。
警察官が証人として出廷することが予定されている時に、裁判所に対して裁判員候補に対して「警察の捜査は特に信用できると思うような事情、あるいは逆に、特に信用できないと思うような事情がありますか」と質問させることができ、この質問に対する答えについても、理由を示すことなく、裁判員として失格させることができるというのだ。
この点の質問の経過について、保坂議員は、自らのブログで次のように紹介している。
■■引用開始■■
保坂 法務省刑事局長に聞きたいのですが、今のような捜査官が証人として出てくる場合には、おそらく自白はしている、しかし、その後に否認に転じて、「自白調書」の任意性に疑いがある場合、こういうことが多いんではないかと思います。裁判所が設問していますよね。「警察官の捜査等にどれだけ信用性を置いているかどうか」と。「私は全然信用していないんだ。最近は相当密室でおかしいと思う」と面接で言っていたら、検察官はこの裁判員候補者を忌避出来るんですね。忌避する理由になりますか。
(そんな事が出来るのか? と与党席からの声。「忌避出来るんですよ。理由を示さずに4人まで忌避出来るんです。警察官はどうかなあという人に対して検察側がどう判断するかどうか」と保坂議場の与党議員に説明)
小津法務省刑事局長 この件、検察官がどのような場合に理由を示さないで忌避するかどうかということは、私どもで何も具体的に検討しているわけではないわけで、個々の事件における検察官の判断ということになろうかと思います。
■■引用終了■■
これは、大変なことだ。警察官の捜査に対して、批判的な気持ちを持っている人は、裁判からはずしてしまう。少しくらい、警察官が行きすぎたことをしていても、まぁ、悪いことをした奴を自白させるには手荒いこともしないとねって許してしまう人ばかりが、裁判員になるかもしれないということだ。
質問自体は、「警察の捜査は特に信用できると思うような事情、あるいは逆に、特に信用できないと思うような事情がありますか」という一見公平なものであるから、問題ないのではないか、という反論がありそうだが、「特に信用できると思うような事情」がある人なんているだろうか?やはり、具体的には、「特に信用できないと思うような事情」が問題になるケース、例えば、自分の身内が警察の取調で酷い目にあったから信用できない、などというケースがほとんどだろう。
その場合、検察は、裁判員から外してしまうことができるのだ…。あきれはてる。警察を信用する人によってしか裁判ができない、しかも、その裁判は、まさに警察官が証人として採用され、その証人の信用性が問題になろうとしているものばかりというのだ。刑事裁判が市民にさらされ、警察の不適切な捜査が市民によって問題化されることを恐れているのだろう。このような質問を用意すること自体、毛札は信用できないと自白しているようなもんだ。
陪審制を採用している米国でも裁判官の質問制度はあるが、このようなアホな質問は許されない。
例えば、マサチューセッツ州では、①事件の当事者・証人・弁護士を知っているか、②その事件について個人的に知っていたか、又はテレビ・ラジオ、新聞等から知っているか、③当該事件及びこの種の事件に意見を発表したり、又まとめたことがあるか、④どちらかに何らかの先入観又は偏見を持っているか、⑤当該事件に個人的興味・関心を持っているか、⑥その他当該事件に公正に対処できない何らかの事情があるかどうかの6問である(「陪審制度」第一法規)。
まさに、その具体的な事件について、不公平な裁判をするかどうかが、問題とされているのであって、それ以外の政治信条について聞くことはない。
なお、裁判員制度に伴うこの質問制度の問題点は、以上のことだけではない。
死刑の適用が問題となる事件については、「起訴されてる●●罪について法律は、『死刑または無期懲役または●年以上の懲役に処す』と定めています。今回の事件で有罪とされた場合は、この刑を前提に量刑を判断できますか」という質問を裁判官にさせることができる。そのうえ、「できない」と答えた場合、「証拠によってどのような事実が明らかになったとしても、絶対に死刑を選択しないと決めていますか」と聞くというのだ。
はぁ、それじゃあ、死刑積極論者しか残らないではないか!
この質問がもし許されるとしたら、反対の質問として、「人を殺したら原則死刑にするべきだと思うか」という質問をして、するべきだと答えたら、排除する制度がある場合のみだろう(このような質問自体が許されないと考えるが…)。
変な裁判員制度…。
★「憎しみはダークサイドへの道、苦しみと痛みへの道なのじゃ」(マスター・ヨーダ)
★「政策を決めるのはその国の指導者です。そして,国民は,つねにその指導者のいいなりになるように仕向けられます。方法は簡単です。一般的な国民に向かっては,われわれは攻撃されかかっているのだと伝え,戦意を煽ります。平和主義者に対しては,愛国心が欠けていると非難すればいいのです。このやりかたはどんな国でも有効です」(ヒトラーの側近ヘルマン・ゲーリング。ナチスドイツを裁いたニュルンベルグ裁判にて)
※このブログのトップページへはここ←をクリックして下さい。過去記事はENTRY ARCHIVE・過去の記事,分野別で読むにはCATEGORY・カテゴリからそれぞれ選択して下さい。
また,このブログの趣旨の紹介及びTB&コメントの際のお願いはこちら(←クリック)まで。転載、引用大歓迎です。なお、安倍辞任までの間、字数が許す限り、タイトルに安倍辞任要求を盛り込むようにしています(ここ←参照下さい)。
警察官が証人として出廷することが予定されている時に、裁判所に対して裁判員候補に対して「警察の捜査は特に信用できると思うような事情、あるいは逆に、特に信用できないと思うような事情がありますか」と質問させることができ、この質問に対する答えについても、理由を示すことなく、裁判員として失格させることができるというのだ。
この点の質問の経過について、保坂議員は、自らのブログで次のように紹介している。
■■引用開始■■
保坂 法務省刑事局長に聞きたいのですが、今のような捜査官が証人として出てくる場合には、おそらく自白はしている、しかし、その後に否認に転じて、「自白調書」の任意性に疑いがある場合、こういうことが多いんではないかと思います。裁判所が設問していますよね。「警察官の捜査等にどれだけ信用性を置いているかどうか」と。「私は全然信用していないんだ。最近は相当密室でおかしいと思う」と面接で言っていたら、検察官はこの裁判員候補者を忌避出来るんですね。忌避する理由になりますか。
(そんな事が出来るのか? と与党席からの声。「忌避出来るんですよ。理由を示さずに4人まで忌避出来るんです。警察官はどうかなあという人に対して検察側がどう判断するかどうか」と保坂議場の与党議員に説明)
小津法務省刑事局長 この件、検察官がどのような場合に理由を示さないで忌避するかどうかということは、私どもで何も具体的に検討しているわけではないわけで、個々の事件における検察官の判断ということになろうかと思います。
■■引用終了■■
これは、大変なことだ。警察官の捜査に対して、批判的な気持ちを持っている人は、裁判からはずしてしまう。少しくらい、警察官が行きすぎたことをしていても、まぁ、悪いことをした奴を自白させるには手荒いこともしないとねって許してしまう人ばかりが、裁判員になるかもしれないということだ。
質問自体は、「警察の捜査は特に信用できると思うような事情、あるいは逆に、特に信用できないと思うような事情がありますか」という一見公平なものであるから、問題ないのではないか、という反論がありそうだが、「特に信用できると思うような事情」がある人なんているだろうか?やはり、具体的には、「特に信用できないと思うような事情」が問題になるケース、例えば、自分の身内が警察の取調で酷い目にあったから信用できない、などというケースがほとんどだろう。
その場合、検察は、裁判員から外してしまうことができるのだ…。あきれはてる。警察を信用する人によってしか裁判ができない、しかも、その裁判は、まさに警察官が証人として採用され、その証人の信用性が問題になろうとしているものばかりというのだ。刑事裁判が市民にさらされ、警察の不適切な捜査が市民によって問題化されることを恐れているのだろう。このような質問を用意すること自体、毛札は信用できないと自白しているようなもんだ。
陪審制を採用している米国でも裁判官の質問制度はあるが、このようなアホな質問は許されない。
例えば、マサチューセッツ州では、①事件の当事者・証人・弁護士を知っているか、②その事件について個人的に知っていたか、又はテレビ・ラジオ、新聞等から知っているか、③当該事件及びこの種の事件に意見を発表したり、又まとめたことがあるか、④どちらかに何らかの先入観又は偏見を持っているか、⑤当該事件に個人的興味・関心を持っているか、⑥その他当該事件に公正に対処できない何らかの事情があるかどうかの6問である(「陪審制度」第一法規)。
まさに、その具体的な事件について、不公平な裁判をするかどうかが、問題とされているのであって、それ以外の政治信条について聞くことはない。
なお、裁判員制度に伴うこの質問制度の問題点は、以上のことだけではない。
死刑の適用が問題となる事件については、「起訴されてる●●罪について法律は、『死刑または無期懲役または●年以上の懲役に処す』と定めています。今回の事件で有罪とされた場合は、この刑を前提に量刑を判断できますか」という質問を裁判官にさせることができる。そのうえ、「できない」と答えた場合、「証拠によってどのような事実が明らかになったとしても、絶対に死刑を選択しないと決めていますか」と聞くというのだ。
はぁ、それじゃあ、死刑積極論者しか残らないではないか!
この質問がもし許されるとしたら、反対の質問として、「人を殺したら原則死刑にするべきだと思うか」という質問をして、するべきだと答えたら、排除する制度がある場合のみだろう(このような質問自体が許されないと考えるが…)。
変な裁判員制度…。
★「憎しみはダークサイドへの道、苦しみと痛みへの道なのじゃ」(マスター・ヨーダ)
★「政策を決めるのはその国の指導者です。そして,国民は,つねにその指導者のいいなりになるように仕向けられます。方法は簡単です。一般的な国民に向かっては,われわれは攻撃されかかっているのだと伝え,戦意を煽ります。平和主義者に対しては,愛国心が欠けていると非難すればいいのです。このやりかたはどんな国でも有効です」(ヒトラーの側近ヘルマン・ゲーリング。ナチスドイツを裁いたニュルンベルグ裁判にて)
※このブログのトップページへはここ←をクリックして下さい。過去記事はENTRY ARCHIVE・過去の記事,分野別で読むにはCATEGORY・カテゴリからそれぞれ選択して下さい。
また,このブログの趣旨の紹介及びTB&コメントの際のお願いはこちら(←クリック)まで。転載、引用大歓迎です。なお、安倍辞任までの間、字数が許す限り、タイトルに安倍辞任要求を盛り込むようにしています(ここ←参照下さい)。










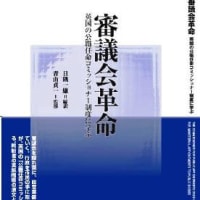
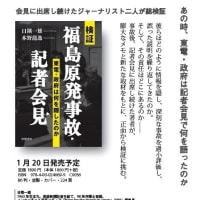
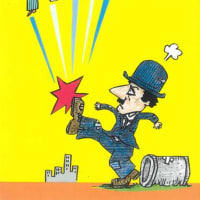
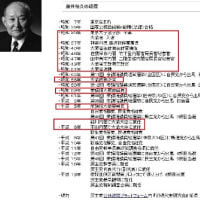
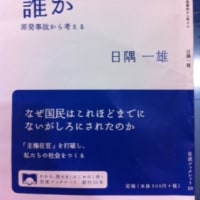
なんか司法も腐ってきましたね。
気持ち悪ぅ・・・。
裁判員選定は危ないと思っています。私がそう思う根拠は法律にある、「選定の過程は公表しない」と言う文章です。
エントリーにある裁判員の忌避権は弁護人にもあります。しかし、そこに至るまでの選定にも不正が入り込む余地は山ほどあると思います。
危険、危険・・・・・ですね。
ありがとうございます。
こんかいはあつかわないんですか?
あつかってくださいよ
くちだけじゃないんでしょ
ここは他のサイトでも注目されてるんですから
姿勢をみせていただきたい
コメントまちますね!よろしく
『検察側が「警察官」を証人として出廷される時に、裁判所に対して裁判員候補に対して「あなたは警察官の捜査を信用していますか」と質問させることが出来る。』
といっているが、根拠法はどれなんだ?
それと、弁護側も同じような質問が出来るの
か?
もし出来るのなら、検察側・被告側に同じ権利が認められているわけだから問題ない。
保坂議員はそこを示さないと!
ただのミスリードになりかねない。
またぞろ日本人の恥部がおおでをふるって出てきたわけだ。
取調べの可視化についても、警察や検察の都合のいい部分のつぎはぎなら、害あって益無し。
国民、ここまで舐められて、まだ気づかない?すくなくともこのサイトに好意的な人は気づいているのだが。
【もし出来るのなら、検察側・被告側に同じ権利が認められているわけだから問題ない】とはいえないことを、記事中で示したつもりですが…。この質問は弁護側にとって有利なものにはならないでしょう。