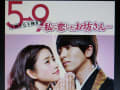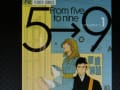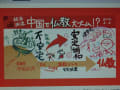5月20日(土)の午後、閩江大学卒業生の王さんと、彼の彼女の甘さんに誘われて、久しぶりに福州市内の古刹「西禅寺」に行くこととなった。この「西禅寺」には、福州市の中心部に近く、数年前までに5〜6回は行ったことがあった。大伽藍の古刹「西禅寺」の創建は867年の唐の時代。
1960年代後半から1970年代前半の約10年間、中国国内の文化大革命時代、この「西禅寺」もまた、仏像や法器は徹底的に破壊された。また、僧侶たちは迫害に遭って、やむなく還俗(げんぞく)[僧侶をやめること]させられた。文化大革命が終わり、1978年から改革開放政策に政治を大転換した中国で、この「西禅寺」は1983年に国家重点寺院の一つに認定されることとなった。
20元(340円)の入館料を払って境内に入る。以前来た時とは違って、たくさんの若い人たちがこの寺を訪れていた。王さんが、「最近、中国では、寺院が若い人たちに大人気なんですよ」と話す。そういえば、境内のいたるところに、10代後半、20代・30代の若い人たちの姿がとても多く、8割方がその年齢層の人たちの参拝者だった。中には、漢服(中国古代の服装)を着て参拝している人もぽつぽつと見られる。
広い大伽藍の境内には、5箇所ほどに線香を立てて祈る所がある。各箇所にはそれぞれ三つの大きな線香を立てるものが置かれ、一つの線香台には3本の線香を立てて、祈り願う。(つまり、一箇所で9本の線香を使う。) この赤く長太い線香だが、無料なのだということを、王さんに初めて教えてもらった。20元の拝観料金に線香代金も入っているのだそうだ。若い人たちが、熱心に線香を立てて、願い事を祈っている。
そういえば、中国の道教の寺院では、願い事を祈り、そして広げた手に入る二枚の木切れを、床に落として、表と表が出れば願い事が遠からずかなうというものがある。人々は、表と表が出るまで、繰り返し行う。日本では、主に神道の神社に行って願い事と祈りをするが、中国では仏教や道教の寺院に行く。
境内には、泰山木(たいざんぼく)の白く高貴な香りの漂う花が開花していた。宋時代(960年~1276年)に植えられたというライチの古木があると、王さんと甘さんに教えられ、そこに行くと、ライチの実が少し大きくなり始めていた。
福州市内の歴史的建造物としては最も大きくて立派な建物と石塔が建っている。建物の方は「五百羅漢堂」で、建物内部には青く少し不気味な、さまざまな表情の五百体もの羅漢たちが置かれている。
そして、「報恩塔」と名前のある石塔には圧倒される。何階(何層)あるか見上げて数えてみると二十層超あった。この寺院には、禅宗に関係のある達磨(だるま)像もあるが、観音菩薩像など、さまざまなタイプの仏像のオンパレード的な感がする。まあ、「西禅寺」と名前があり、お坊さんたちの作務衣も禅宗的なので「禅宗系」の寺院なのだろうとは思う。(※「禅宗」の「禅」とは、「心静まった状態」という意味。)
■中国で現在、公認されている宗教は、「カトリック・プロテスタント・イスラム教・仏教・道教」の五つだ。プロテスタントやカトリックなどのキリスト教は「耶蘇教(やそきょう)」と中国語では書かれる。宗教活動が認められるのは、教会内や寺院内、モスク内の敷地のみで、敷地外のありとあらゆる活動は禁止されていて、講演や募金、福祉活動なども宗教活動としては行えない。
2015年~2018年の4年間ほど、中国全土津々浦々で「防犯邪教・邪教撲滅大キャンペーン」が大規模に、そして徹底的に繰り広げられた。(「邪教」とは、「法輪功、統一教会、モルモン教、エホバ」など。)
■中国の宗教信仰で最も信仰人口が多いのは「道教」。次いで「仏教」で、2億2000万人余りの信仰人口があるとされる。そして、三番目が「キリスト教」で、信仰人口は1億3000万人余り。仏教には、チベットや東北三省や内モンゴルなどでは、「ラマ教(チベット仏教)」なども含まれる。(※「儒教」は宗教ではない。)
2015年10月~12月、日本のテレビドラマで「5➡9 (5時から9時まで) 私に恋したお坊さん」が放映された(石原さとみ・山下智久主演)。このドラマは、中国の若い人たちの間でも人気をよび、大学の日本語学科の学生たちも熱心に視聴していた。ある日、学生に、「先生、日本のお坊さんは結婚してもいいんですか。中国では、お坊さんは結婚してはいけないんですが‥」と質問された。その時、私は初めて、中国の僧侶は結婚はできないということを知った。
■日本のNHK番組「クローズアップ現代」。現在のキャスターは桑子真帆さんだが、かっては国谷裕子キャスターが長らくこの番組を担当していた。この番組で2016年4月、「経済減速―中国で仏教大ブーム!?」ど題されて報道された。この時のキャスターは、中国事情にも詳しい鎌倉千秋キャスターで、コメンテーターは中国事情の専門家の一人・興梠一郎氏(神田外国語大学教授)だった。「かって全ての宗教が否定された中国で、いま、仏教を信仰するエリートが急増している。"金に目がくらんで豹変した人がどれだけいるか‥‥" "私たちはどこに向かえばいのか‥‥" 頭を丸め出家した名門大学の学生たちが声をふり絞る。経済が減速する中、目標を失い、さまよう人々の心。番組は、中国の若者たちの出家の現場に密着。彼等を信仰へと駆り立てる中国社会を見つめる。」と、銘打たれた番組内容だった。
■さて、現在(今)の中国の若い人たちの「お寺人気」とは、いったい何なのだろうか。どんなことがその背景にあるのだろうか…。私が知る限り、3年ほど前の中国では、若い人たちのお寺参拝人気はあまりなかったように思う。なぜ、それから3年間が経過した今、若い人たちの「寺院参拝人気」が高まっているのだろうか…。そのことについては、また、中国の若い学生たちにも聞いてみたいと思っている。(※ここ5年ほど前から、漢服を着る若い女性がよく見られるようになった。中国でも、伝統の良さが見直され始め、観光地でも伝統的な建造物地区への人気も高まっている。このような中国人の伝統文化への回帰というか、見直し評価が、この「仏教寺院人気」とも関係しているとは思う。)