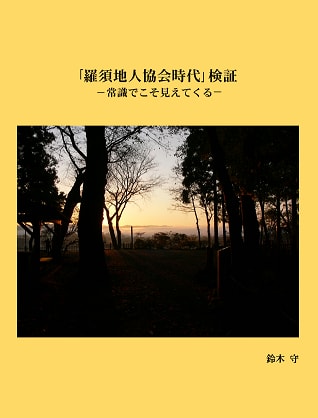


 次へ。
次へ。前へ
 。
。 “『「羅須地人協会時代」検証―常識でこそ見えてくる―』の目次”へ。
“『「羅須地人協会時代」検証―常識でこそ見えてくる―』の目次”へ。 〝渉猟「本当の賢治」(鈴木守の賢治関連主な著作)〟へ。
〝渉猟「本当の賢治」(鈴木守の賢治関連主な著作)〟へ。 ”みちのくの山野草”のトップに戻る。
”みちのくの山野草”のトップに戻る。 。
。********************************** なお、以下は今回投稿分のテキスト形式版である。**************************
大正15年4月1日の新聞報道の不自然さ
さてよく知られているように、大正15年4月1日付『岩手日報』には、「新しい農村の建設に努力する/花巻農學校を辞した宮澤先生」という見出しの新聞記事、
花巻川口町宮澤政治郎( (ママ) )氏長男賢治(二八( (ママ)))氏は今囘縣立花巻農学校の教諭を辞職し花巻川口町下根子に同志二十餘名と新しき農村の建設に努力することになつたきのふ宮澤氏を訪ねると
現代の農村はたしかに経済的にも種々行きつまつてゐるやうに考へられます、そこで少し東京と仙台の大學あたりで自分の不足であった『農村経済』について少し研究したいと思ってゐます そして半年ぐらゐはこの花巻で耕作にも従事し生活即ち藝術の生がいを送りたいものです、そこで幻燈會の如きはまい週のやうに開さいするし、レコードコンサートも月一囘位もよほしたいとおもつてゐます幸同志の方が二十名ばかりありますので自分がひたいにあせした努力でつくりあげた農作ぶつの物々交換をおこないしづかな生活をつづけて行く考えです
と語つてゐた
<『岩手日報』(大正15年4月1日付)>
が載った。
だが、賢治の花巻農学校の辞め方は退任式等さえも行われなかったという唐突なおかしいものであったということを知った今は、この報道のされ方についてもまたちょっとおかしいぞと訝ってしまう。それは、賢治が花巻農学校を突然辞めるという私的な行為が、なぜ『岩手日報』という公器に間髪を入れずに載ったのだろうかということがである。
前掲の菊池信一の証言等からすれば、賢治が花巻農学校を辞めることが公的に知られ出したのは、早くとも国民高等学校の終了式の行われた日(大正15年3月27日)であろう。一方、この新聞報道は大正15年4月1日だし、記者は「きのふ宮澤氏を訪ねると」と書いているから、賢治が取材を受けたのは3月31日だと推測できる。とすれば、その期間は
3月28日、29日、30日
のたった3日間しかないこととなる。
ましてこの時期は年度末だから、あちこちで人事異動が数多ある中、この短期間の間に当時のマスコミが単なる個人的な退職を知り、なおかつそれをわざわざ新聞報道をするほどのニュースバリューがこの賢治の退職にあったとは常識的には考えられない。かなり不自然なことである。すると考えられる可能性は次のいずれかであろう。
(1) まずは、実は賢治が積極的に『岩手日報』に取材を働き掛けたという可能性である。というのは、年度が改まっての花巻農学校の入学式の日に、「私は、今後この学校には来ません」という賢治自筆の紙が廊下と講堂の入口に貼ってあったという小田島留一の証言がある(板垣寛著『賢治先生と石鳥谷の人々』所収の板垣亮一の「賢治と私」より)から、このような行為が事実あったとするならばそれは普通「当てこすり」に類するものであり、これと同様な意図で取材を依頼したという可能性がある。
(2) あるいは、この時の賢治の退職の仕方は普通のものとはかなり違ったものであったことが一部の人の間にたちまち知られてしまって、それを知った『岩手日報』はニュースバリューがあると判断して報道したという可能性である。
もちろん、このどちらでもあったという可能性も当然あろう。つまり、この衝動的な賢治の退職にはやはり私たちが知らない何らかの大きな事情があり、実は賢治は辞めざるを得ない状況に追い込まれてしまって不本意ながら退職したという可能性も一概に否定できないということである。そして『岩手日報』は、そういうことであればニュースバリューがあると判断して報道したという可能性も否定し切れない。
さりながら、これらの可能性はいずれも荒唐無稽かなと私は内心思っていたのだが、実は萬田努氏も、
農学校を依願退職した翌日、四月一日の岩手日報朝刊に、「新しい農村の/建設に努力する/花巻農学校を/辞した宮沢先生」の見出しの記事がでた。退職した翌日、それも実践活動が始まっていない時点で、何故このような記事が出たかは不思議である。常識的に考えてみて、まず、誰かがそのように吹聴しないかぎりこんなことはあり得ない。
<『孤高の詩人宮沢賢治』(萬田務著、新典社)、219p~>
と論じていることを私は知って、「実践活動が始まっていない時点で……不思議である」という萬田氏の指摘に首肯し、実はそれ程荒唐無稽なことでもなかったのだと少し安堵した。
いずれにせよ、賢治の花巻農学校の辞め方が唐突なものであったし、しかも退任式等もなかったと判断できるから、賢治自身にとってはその辞職そのものが不本意なものであったという蓋然性が結構高いと言えそうだ。おのずから、先にも述べた通り、そこには周到な準備も、綿密な計画もあったわけでもなく、ましてや将来的な展望があって賢治は花巻農学校を辞めたということではなかった、ということになりそうだ。
実際それは、先の新聞報道における、賢治が記者から取材を受けて答えたのであろう、「そこで少し東京と仙台の大學あたりで自分の不足であった『農村経済』について少し研究したい」からも窺える。なぜならば、実際に賢治がその後の「羅須地人協会時代」にそのようなことを為したということは知られていないからだ。
よって、賢治が農学校を辞めた際の「理由」としては、
賢治は生徒たちに対しては「農民になれ」と言いながらも、自分自身は俸給生活をしているということには当然矛盾があるので、実際に農民になって生徒たちに範を垂れようとして賢治は花巻農学校を辞めた。
という「通説」は常識的に判断すればおかしいし、その後でさえもそれを「羅須地人協会時代」の賢治の実践の中からは見出しにくいので、これは後の誰かが後付けした「理由」だと判断した方が妥当だということを教えてくれる。
******************************************************* 以上 *********************************************************
 “『「羅須地人協会時代」検証―常識でこそ見えてくる―』の目次”へ。
“『「羅須地人協会時代」検証―常識でこそ見えてくる―』の目次”へ。 “渉猟「本当の賢治」(鈴木守の賢治関連主な著作)”へ。
“渉猟「本当の賢治」(鈴木守の賢治関連主な著作)”へ。”みちのくの山野草”のトップに戻る。

***********************************************************************************************************
《新刊案内》この度、拙著『このままでいいのですか 『校本宮澤賢治全集』の杜撰』

を出版した。その最大の切っ掛けは、今から約半世紀以上も前に私の恩師でもあり、賢治の甥(妹シゲの長男)である岩田純蔵教授が目の前で、
賢治はあまりにも聖人・君子化され過ぎてしまって、実は私はいろいろなことを知っているのだが、そのようなことはおいそれとは喋れなくなってしまった。
と嘆いたことである。そして、私は定年後ここまでの16年間ほどそのことに関して追究してきた結果、それに対する私なりの答が出た。延いては、
小学校の国語教科書で、嘘かも知れない賢治終焉前日の面談をあたかも事実であるかの如くに教えている現実が今でもあるが、純真な子どもたちを騙している虞れのあるこのようなことをこのまま続けていていいのですか。もう止めていただきたい。
という課題があることを知ったので、 『校本宮澤賢治全集』には幾つかの杜撰な点があるから、とりわけ未来の子どもたちのために検証をし直し、どうかそれらの解消をしていただきたい。
と世に訴えたいという想いがふつふつと沸き起こってきたことが、今回の拙著出版の最大の理由である。しかしながら、数多おられる才気煥発・博覧強記の宮澤賢治研究者の方々の論考等を何度も目にしてきているので、非才な私にはなおさらにその追究は無謀なことだから諦めようかなという考えが何度か過った。……のだが、方法論としては次のようなことを心掛ければ非才な私でもなんとかなりそうだと直感した。
まず、周知のようにデカルトは『方法序説』の中で、
きわめてゆっくりと歩む人でも、つねにまっすぐな道をたどるなら、走りながらも道をそれてしまう人よりも、はるかに前進することができる。
と述べていることを私は思い出した。同時に、石井洋二郎氏が、 あらゆることを疑い、あらゆる情報の真偽を自分の目で確認してみること、必ず一次情報に立ち返って自分の頭と足で検証してみること
という、研究における方法論を教えてくれていることもである。すると、この基本を心掛けて取り組めばなんとかなるだろうという根拠のない自信が生まれ、歩き出すことにした。
そして歩いていると、ある著名な賢治研究者が私(鈴木守)の研究に関して、私の性格がおかしい(偏屈という意味?)から、その研究結果を受け容れがたいと言っているということを知った。まあ、人間的に至らない点が多々あるはずの私だからおかしいかも知れないが、研究内容やその結果と私の性格とは関係がないはずである。おかしいと仰るのであれば、そもそも、私の研究は基本的には「仮説検証型」研究ですから、たったこれだけで十分です。私の検証結果に対してこのような反例があると、たった一つの反例を突きつけていただけば、私は素直に引き下がります。間違っていましたと。
そうして粘り強く歩き続けていたならば、私にも自分なりの賢治研究が出来た。しかも、それらは従前の定説や通説に鑑みれば、荒唐無稽だと嗤われそうなものが多かったのだが、そのような私の研究結果について、入沢康夫氏や大内秀明氏そして森義真氏からの支持もあるので、私はその研究結果に対して自信を増している。ちなみに、私が検証出来た仮説に対して、現時点で反例を突きつけて下さった方はまだ誰一人いない。
そこで、私が今までに辿り着けた事柄を述べたのが、この拙著『このままでいいのですか 『校本宮澤賢治全集』の杜撰』(鈴木 守著、録繙堂出版、1,000円(税込み))であり、その目次は下掲のとおりである。

現在、岩手県内の書店で販売されております。
なお、岩手県外にお住まいの方も含め、本書の購入をご希望の場合は葉書か電話にて、入手したい旨のお申し込みを下記宛にしていただければ、まず本書を郵送いたします。到着後、その代金として1,000円分(送料無料)の切手を送って下さい。
〒025-0068 岩手県花巻市下幅21-11 鈴木守 ☎ 0198-24-9813

























※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます