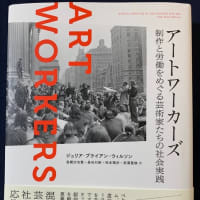羊飼いの礼拝(ルーヴル美術館)
画家の修業時代を探る(I)
青色系の少ない絵画
これまでにラ・トゥールの真作とみなされている作品群を見ていると、さまざまなことに気がつく。そのひとつは、使われた色彩について、青色系が大変少ないことである。青色が使われている作品として思い浮かぶのは、「松明のある聖セバスティアヌス」の侍女の有名なヴェール、「槍を持つ聖トマス」の外衣くらいである。前者についてはベルリン美術館所蔵のものを併せて2点あるが、ルーヴル美術館所蔵の作品にはラピス・ラズリとして知られる高価な顔料が使われている。注文主や寄贈の相手が、社会的に高位な人物であったのだろう。
青色系に代わって、全体に濃淡さまざまな褐色系の土性顔料が大量に使われている。この点、「青色の画家」として著名な17世紀オランダのフェルメールの作品などと比較すると、際だって大きな差異である。この褐色系の多い画面は、大変落ち着いた印象を観る者に与える。しかし、それだけでは作品の印象は大変暗くなる。
「ヴァーミリオンの世界」
ラ・トゥールは蝋燭などの光源によって、その点を補っているが、それとともに目立つのが、濃淡さまざまなヴァーミリオン(朱色)である。「聖ヒエロニムス」「聖アンデレ」などの使徒像、「妻に嘲笑されるヨブ」「女占い師」「いかさま師」、「生誕」など、ヴァーミリオンが画面を引き立てている作品はきわめて多い。ラ・トゥール絵画は「ヴァーミリオンの世界」といってもよいほど、ともすれば暗くなりがちな画面を朱色が引き立てている。中国の辰砂などに比較して、オレンジ・黄色系がやや強いだろうか。「蚤をとる女」の椅子の色などは、光線の関係もあってか、ややオリエンタルな感じがする。
真贋問題も関係して、ラ・トゥールの作品については、幸い異例なほど科学的な分析・検討が行われ、当時使われた下地、顔料、画法などについて、多くのことが明らかにされている。ラ・トゥールの活動した17世紀前半までは、フランスでは絵画は職人の作る製品、手仕事の作品として、親方の工房(アトリエ)で制作がなされることが前提となっていた。その多くは、パトロンや寄贈先などが想定された注文生産に近いものであった。
制作の手順
制作に当たって油彩画の場合、通常は角や隅を釘で留めた横木のついた木製の画枠に鋲やひもでカンヴァス張ったものに描かれている。カンヴァスは当時の織布技術の水準もあって、90センチほどの幅のかなり狭い織機で織られた麻布や亜麻布が使われており、必要に応じて継ぎ合わせて張られている。その上に目止めを塗り、それから絵の具が定着するに必要な層を地塗りとして、整える。そして、その上にさまざまな色彩の顔料を使用して対象を描くことになる。こうした作業やそれに必要な知識は、容易には習得できない。
徒弟制度の重要性
18世紀以降は画家の育成は主としてアカデミーへ移行し、技術的な知識の伝達は衰え、作品までのいくつかの工程は、画材商の手で行われることになった。しかし、ラ・トゥールの時代は、いまだ工房が知識、技能の伝達の中心を成していた。ラ・トゥールがどこかの親方の工房で、制作に必要な技能、ノウハウなどを習得したことはこの意味で間違いない。残念ながら、誰に師事したか特定できないことは、前回記した通りである。
制作に必要な顔料ひとつとっても、原料の調達、配合、使用法など、かなりの部分は知識の伝達を通して、工房間で技術が共有されていたとはいえ、工房がそれぞれ継承・蓄積してきた秘伝やノウハウがあったことも間違いない。親方が徒弟を受け入れる場合には、当時の職業的水準として必要な基本的熟練を伝達することは、徒弟制度がある職業については、親方・徒弟間での当然の了解であった。ラ・トゥールが受け入れた徒弟ジャン・ニコラ・ディドロとの契約書などにも、その旨が記載されている。
科学技術を駆使した研究成果
ラ・トゥールの作品については、フランス博物館科学研究・修復センターや作品を所蔵する大美術館などが、熱心に科学的研究対象としてきた。Stereomicroscope, x-radiography, infrared reflectography, neutron autoradiography などの先端分析技術が使用され、今日ではほとんどすべての作品について顔料などの分析も行われている。たとえば、X線写真を撮ると、下地塗りに含まれる鉛白のような物質には吸収されるため、明るく写るが、土性顔料やグレーズなどは通過するため、あたかも人体のX線画像のように、多くの情報が得られる。地塗りは全体的な色合いに影響するが、白亜やさまざまな色の土性顔料が地塗りに使われ、いくらかの他の顔料、しばしば赤も含まれていたことが分かっている。筆洗に残っていた顔料が混入したものかもしれないと推定もされている。
こうした顔料などは、大都市などでは薬種商などが画材向けに販売していたようだ。まったくの想像の世界だが、トレイシー・シュヴァリエの小説『真珠の耳飾りの少女』の中にも、デルフトでフェルメールと思われる画家のモデルの少女が、主人の画家から薬種商に顔料や亜麻仁油などの買い物を頼まれて、いそいそと出かける場面がありますね。
ヴァーミリオンの調達
ヴァーミリオン(Vermillion)は、朱(Cinnabar シナバル、辰砂)とも呼ばれている赤色の硫化水銀HgSである。天然にも鉱石の辰砂として産出しており、それを破砕して、粉にしただけのものも有史以前から、顔料として使われてきた。また、水銀と硫黄を化合させて人工辰砂を作る技術も古くから知られてきた。15世紀頃から人工品が使われてきたらしい。すでにローマ時代に使用されていることが確認されているし、中国では印章の朱肉材料としても知られている。顔料としてヴァーミリオンは、耐久性の高いものであり、ラ・トゥールの作品でも、あまり褪色せずに原作の美しさを今日に伝えている。
しかし、実際にヴァーミリオンを工房で作ることは原材料を粉にする作業からして、かなり大変なことであったらしい。中国から伝来した技術によって、オランダなどで製造された方法は乾式といわれる方法であった。17世紀には湿式という製法も考案されている。乾式法では鉄鍋の中に溶かしておいた硫黄に、水銀を加えて硫化水銀を作る。この結果の黒色の塊をさらに坩堝に入れて加熱、昇華させて、磁器か鉄筒に凝集させると、赤色の結晶体になる。 その後、遊離硫黄を除去するため、アルカリ処理し、水洗すると出来上がる。これに水を加えながら粉砕すると顔料となる。
製法としては、単純にみえるが、硫黄、水銀などの有毒物質を含むため、工程でもかなりの注意が必要なはずである。こうした知識なども徒弟制度の発展とともに伝承されてきたのだろう。徒弟の修業は多くの場合、教科書のようなものがあるわけではなく、OJT(On-the-Job Training)である。毎日の工房の仕事を通して、親方、兄弟子職人などから徒弟へと、多くの知識が伝達されてきた。徒弟の素質、能力などで、その後の職業生活が大きく規定されるのは、今日のOJTと通じるところでもある。
References
Melanie Gifford, Claire Barry, Barbara Berrie, and Michael Palmer, Some observations on GLT’s Painting Practice, Georges de La Tour and His World, National Gallery of Art and the Kimbell Art Museum , 1997
ザベト・マルタン「記憶の場としての絵画―ジョルジュ・ド・ラ・トゥールの作品の科学的調査」『Georges de La Tour』国立西洋美術館展カタログ、読売新聞社、2005