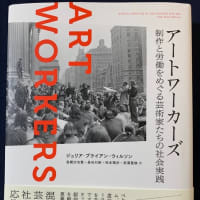Georges de La Tour, Saint Joseph Carpenter, Christ with St.Joseph in the Carptenter’s Shop, Musée du Louvre, Paris.
一本の蝋燭が映し出す光と闇の空間を、あたかも切り取ったような情景が眼前に展開している。そこに描かれているのは、木工の仕事をしている老人と幼い子供の二人。しかし、次の瞬間、見る人たちはそれが大工のヨセフであり、幼いイエスであることに気づく。
イエスの養父としてのヨセフは、額に汗して働く一人の年老いた大工として、リアリズムに徹して描かれている。蝋燭をかかげてその仕事ぶりを見る幼いイエスは、ハロー(光輪)も付されていない。澄み切った瞳に純粋な心を抱いた幼い子供として描かれている。純粋さを絵に描いたら、こうなるといってよいだろうか。そして、静謐さの中に、暖かさとともに不思議な厳しさも満ちている空間である。
来るべき時への予感
ヨセフが十字型の錐で作業をしているものを、よく見ればどうも十字架のための梁材である。自分の仕事の結果が、いかなることにつながっているか、先を知りうることもなくひたすら仕事をしているヨセフと、近い将来に苛酷な運命が待ち受けることを知るよしもない、幼い子供の純粋さをそのまま具象化したようなイエスが対面している。
ヨセフが大工であることを語るものは、簡単な工具と木材、削りくず以外にはなにもない。作業場であることを思わせるような背景は、何も描かれていない。一本の蝋燭が映しだしたもの以外は、すべて闇の中である。人物がリアリスティックに徹した描写であるにもかかわらず、この場がいかなる空間であるかを推察させるようなものはいっさいない。
自らの想像を超えた次元で、イエスの養父となる運命を担ったヨセフにとってみれば、マリアとイエスへのつながりは、理解を超えたものであり、衝撃でもあった。しかし、その神秘を彼は最後に受け入れる。
不思議なリアリズム
ラ・トゥールの天才性は、ヨセフという年老いた大工の世俗的特徴を徹底して描いたことに現れている。もしかすると実際にラ・トゥールの周囲にモデルがいたかもしれないと思うような、黙々と目前の作業をしている一人の実直そうな年老いた男である。これまでの歳月が刻み込んだ額の皺、強靱そうな肢体がそれを語っている。
他方、幼いイエスの髪の毛などには、この画家の技法がいかんなく発揮されているが、この幼き子イエスは世俗的かけらも感じられない、不思議なほどの清麗と純粋さで描かれている。蝋燭の光が映し出す子供の顔、手指の美しさは比類がない。
不思議なことに、二人の視線はなにをみているのか、交差していない。ヨセフはなにか考えごとをしているように、その目はイエスには向いていない。ヨセフの仕事を無心に見ているイエスの視線もなにをとらえているのか、実に不思議なまなざしである。なにか分からないが、お互いに、これから起こるべき出来事を予感している一瞬が描かれている。背景には深い闇が広がっている。
静かな衝撃
この作品は1640年代頃に制作されたと推定されている(Pariset and Sterling)。この頃には聖ヨセフへの崇拝はかなり一般化していたようだ。伝承によると、ヨセフはイエスが30歳になる前に亡くなったと言われている。マリアとイエスに付き添われ、平安な臨終を迎えたヨセフは、臨終の苦しみを和らげてくれる保護者として崇められていた。
この絵を見てラ・トゥールに関心を抱くようになった人は多いと思われる。私もかつてオランジュリー展でラ・トゥールの一連の作品を見た時、たちまち魅了された。
洋画家の青木敏郎氏が今回のラ・トゥール展にちなんだ雑誌『美術の窓』(「夜の光が生んだ驚きの写実力」2005年3月号)への寄稿で、20歳の頃、「フランスを中心とする17世紀ヨーロッパ名画展」で、この作品に出会った時の衝撃を次のように記されている。「日本の巨匠たちの作品ですら、ラ・トゥールの作品と比較して大人と子供以上の差があることを一瞬にして悟ってしまった」。
この一枚の絵画が芸術の世界にとどまらず、多くの領域に影響を及ぼしたこともさまざまに察知される。書棚の片隅にある哲学者ジョージ・スタイナー Georges Steinerの名著Real Presence,1989の表紙には、まさにこのラ・トゥールの作品が使われている。
この作品は、1938年頃にイングランドで発見された。1948年、持ち主であったパーシイ・ムーア・ターナー Percy Moore Turnerから、ラ・トゥールの研究者でもあり、ルーヴルの学芸員などもつとめたポール・ジャモ Paul Jamot を偲んで、ルーヴルへ寄贈された*。ラ・トゥールのサインはないが、直ちに画家の第一級の真作と認定された(2005年5月2日記)。
* 今回の国立西洋美術館「ジョルジュ・ド・ラ・トゥール」展出品の作品は、このルーヴル美術館所蔵作品の模作であり、ブザンソン市立美術館・考古学博物館蔵。真作はおそらく海外出品は期待できないでしょうから、ルーヴルへ行かれた折、ぜひご覧ください。(幸い、その後2009年5-6月の「ルーブル特別展」に出展された。)
一本の蝋燭が映し出す光と闇の空間を、あたかも切り取ったような情景が眼前に展開している。そこに描かれているのは、木工の仕事をしている老人と幼い子供の二人。しかし、次の瞬間、見る人たちはそれが大工のヨセフであり、幼いイエスであることに気づく。
イエスの養父としてのヨセフは、額に汗して働く一人の年老いた大工として、リアリズムに徹して描かれている。蝋燭をかかげてその仕事ぶりを見る幼いイエスは、ハロー(光輪)も付されていない。澄み切った瞳に純粋な心を抱いた幼い子供として描かれている。純粋さを絵に描いたら、こうなるといってよいだろうか。そして、静謐さの中に、暖かさとともに不思議な厳しさも満ちている空間である。
来るべき時への予感
ヨセフが十字型の錐で作業をしているものを、よく見ればどうも十字架のための梁材である。自分の仕事の結果が、いかなることにつながっているか、先を知りうることもなくひたすら仕事をしているヨセフと、近い将来に苛酷な運命が待ち受けることを知るよしもない、幼い子供の純粋さをそのまま具象化したようなイエスが対面している。
ヨセフが大工であることを語るものは、簡単な工具と木材、削りくず以外にはなにもない。作業場であることを思わせるような背景は、何も描かれていない。一本の蝋燭が映しだしたもの以外は、すべて闇の中である。人物がリアリスティックに徹した描写であるにもかかわらず、この場がいかなる空間であるかを推察させるようなものはいっさいない。
自らの想像を超えた次元で、イエスの養父となる運命を担ったヨセフにとってみれば、マリアとイエスへのつながりは、理解を超えたものであり、衝撃でもあった。しかし、その神秘を彼は最後に受け入れる。
不思議なリアリズム
ラ・トゥールの天才性は、ヨセフという年老いた大工の世俗的特徴を徹底して描いたことに現れている。もしかすると実際にラ・トゥールの周囲にモデルがいたかもしれないと思うような、黙々と目前の作業をしている一人の実直そうな年老いた男である。これまでの歳月が刻み込んだ額の皺、強靱そうな肢体がそれを語っている。
他方、幼いイエスの髪の毛などには、この画家の技法がいかんなく発揮されているが、この幼き子イエスは世俗的かけらも感じられない、不思議なほどの清麗と純粋さで描かれている。蝋燭の光が映し出す子供の顔、手指の美しさは比類がない。
不思議なことに、二人の視線はなにをみているのか、交差していない。ヨセフはなにか考えごとをしているように、その目はイエスには向いていない。ヨセフの仕事を無心に見ているイエスの視線もなにをとらえているのか、実に不思議なまなざしである。なにか分からないが、お互いに、これから起こるべき出来事を予感している一瞬が描かれている。背景には深い闇が広がっている。
静かな衝撃
この作品は1640年代頃に制作されたと推定されている(Pariset and Sterling)。この頃には聖ヨセフへの崇拝はかなり一般化していたようだ。伝承によると、ヨセフはイエスが30歳になる前に亡くなったと言われている。マリアとイエスに付き添われ、平安な臨終を迎えたヨセフは、臨終の苦しみを和らげてくれる保護者として崇められていた。
この絵を見てラ・トゥールに関心を抱くようになった人は多いと思われる。私もかつてオランジュリー展でラ・トゥールの一連の作品を見た時、たちまち魅了された。
洋画家の青木敏郎氏が今回のラ・トゥール展にちなんだ雑誌『美術の窓』(「夜の光が生んだ驚きの写実力」2005年3月号)への寄稿で、20歳の頃、「フランスを中心とする17世紀ヨーロッパ名画展」で、この作品に出会った時の衝撃を次のように記されている。「日本の巨匠たちの作品ですら、ラ・トゥールの作品と比較して大人と子供以上の差があることを一瞬にして悟ってしまった」。
この一枚の絵画が芸術の世界にとどまらず、多くの領域に影響を及ぼしたこともさまざまに察知される。書棚の片隅にある哲学者ジョージ・スタイナー Georges Steinerの名著Real Presence,1989の表紙には、まさにこのラ・トゥールの作品が使われている。
この作品は、1938年頃にイングランドで発見された。1948年、持ち主であったパーシイ・ムーア・ターナー Percy Moore Turnerから、ラ・トゥールの研究者でもあり、ルーヴルの学芸員などもつとめたポール・ジャモ Paul Jamot を偲んで、ルーヴルへ寄贈された*。ラ・トゥールのサインはないが、直ちに画家の第一級の真作と認定された(2005年5月2日記)。
* 今回の国立西洋美術館「ジョルジュ・ド・ラ・トゥール」展出品の作品は、このルーヴル美術館所蔵作品の模作であり、ブザンソン市立美術館・考古学博物館蔵。真作はおそらく海外出品は期待できないでしょうから、ルーヴルへ行かれた折、ぜひご覧ください。(幸い、その後2009年5-6月の「ルーブル特別展」に出展された。)