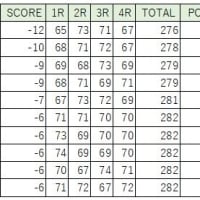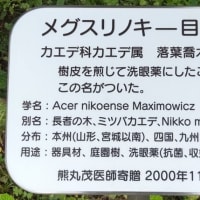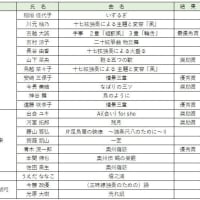先日放送されたNHKスペシャル「熊本城再建 “サムライの英知”を未来へ」。

番組の中で、石垣の、裏込栗石の沈み込みによるハラミをどうやって防ぐかという話を見ながら、ふと次のようなことを思い出した。
一つは熊本城築城に携わった高瀬の大工棟梁・善蔵の話。清正公も裏込石には相当神経を使っていたことが偲ばれる。
「大工善蔵より聞覚控」より
栗石の細かいものや大きな裏石などを入れ込む時には、天気の具合と潮時を御殿様はようく見ておった。水呑場台やら角石などの置き方と縄張りの時、やり方がまずいと何べんも何べんも据え方をやり直したり、また自分で手を下しておられた。今時の人の出来る事じゃない。あの御殿様は凡人じゃなかった。
もう一つは「穴太衆石積みの歴史と技法」という福原成雄氏の研究論文の中から。今回、熊本城では栗石の間にシートを敷いて、沈み込みを防止する計画が話されていたが、他の城ではこんな工法が採られているという事例。
近代になりコンクリートの出現によって裏込栗石を裏込コンクリートに変えた練積みと呼ばれる工法が多く見られるようになった。練積み工法によって土留めの強度が高まり裏込めの心配が無くなり石積みの意匠にも変化が現れている。
▼二様の石垣


番組の中で、石垣の、裏込栗石の沈み込みによるハラミをどうやって防ぐかという話を見ながら、ふと次のようなことを思い出した。
一つは熊本城築城に携わった高瀬の大工棟梁・善蔵の話。清正公も裏込石には相当神経を使っていたことが偲ばれる。
「大工善蔵より聞覚控」より
栗石の細かいものや大きな裏石などを入れ込む時には、天気の具合と潮時を御殿様はようく見ておった。水呑場台やら角石などの置き方と縄張りの時、やり方がまずいと何べんも何べんも据え方をやり直したり、また自分で手を下しておられた。今時の人の出来る事じゃない。あの御殿様は凡人じゃなかった。
もう一つは「穴太衆石積みの歴史と技法」という福原成雄氏の研究論文の中から。今回、熊本城では栗石の間にシートを敷いて、沈み込みを防止する計画が話されていたが、他の城ではこんな工法が採られているという事例。
近代になりコンクリートの出現によって裏込栗石を裏込コンクリートに変えた練積みと呼ばれる工法が多く見られるようになった。練積み工法によって土留めの強度が高まり裏込めの心配が無くなり石積みの意匠にも変化が現れている。
▼二様の石垣