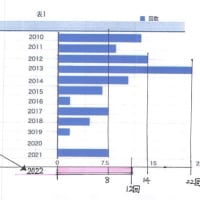16~17世紀のイギリスの思想家F・ベーコンは、著書 「学問の進歩」 の中
で、「医師は患者の健康を回復させるだけでなく回復の見込みのない病気で苦痛に悩まされている患者では息をひきとらせ苦痛を取り除くことも任務であろう」 とし, これを安楽死と呼び、西洋の人々の関心を集めていた。
しかし、実際には、この行為は殺人に相当するので、医師は加担できないことであった。
幕末の蘭方医である緒方洪庵(1810~1863)はドイツ人医師フーフェランドの著書にある医の道徳についての記述を訳し「医戒」として広めたが、その中で 「たとえ病気が、もはや重大な危機に至っているとはいえ、医師としてもう全く救済の手がないなどとは断定すべきでない。ヒトの生命を保全し、努めてこれを長く有しめるのは、医師の最大の目的である」としている。この考えは我が国の医師の倫理として長い間重視されてきた.
時代が流れ、 1960年代後半になると、 特に人工呼吸器が進歩普及し、意識もなく人工呼吸器につながれ、漫然と生き長らえるような患者が目立つようになり、そのような場合には人工呼吸器を取り外すべきであるという考えが台頭してきた。
そのころアメリカを中心に医療における患者の自己決定権の尊重という考えが普及し、患者の意思があればこれを容認しようという考えが起こってきた。しかし、終末期にある患者はすでに正常な判断ができない状況にあることが多く、このような状況に至る前にあらかじめその意思を文書にしておき、 終末期になったら医師に意思を尊重してもらい延命治療の差し控えや中止を認めさせようということで、この事前指示書の作成を推進する社会運動も盛んになった。さらにベーコンの言う、いわゆる積極的安楽死も容認しようという考えも強くなった。
死にゆく過程について医師の役割も複雑になってきた。医師はこの生死にかかわる問題について何が重要な問題なのかを十分に理解しておくことが肝要である。その際のキーポイントは患者本人の意思確認になる。
この頃、射水市民病院事件が明らかになった。
2006年3月射水市民病院で、当時50歳の外科医師が78歳の入院患者の人工呼吸器を取り外そうとする、不自然な点があったために、病院が調査を始め警察に届け出た。
2008年に、警察は問題の7件のうち六件の主治医だった外科部長二人を殺人容疑で地検に書類送検した。
最終的に不起訴となったが延命治療に消極的な考えを持つ私は主治医に共感したものであった。
この事件を機に本人の意思確認ができないときは家族等の話から本人の意思を推定する方向も認められるようになり、延命処置中断の条件が多少緩和される事になったのは朗報であった。