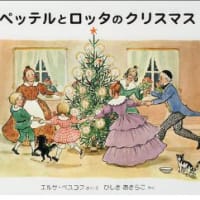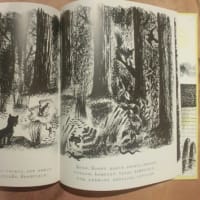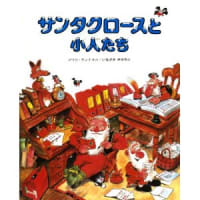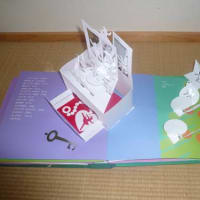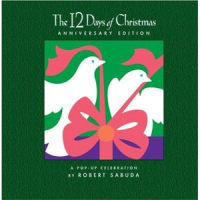▲三重県熊野市にある丸山千枚田
山林多い、三重県ではこのように斜面に畑が成るものが多い。
田んぼだけでなく、みかんや梅も段々畑になっているものが多い。
そのためか?この地区では養蜂と農家の結びつきもうまくできていたそうです。

確かに段々畑だったら
人工授粉より、ミツバチ受粉の方が効率が良い。
そのうえ雨が多い地区では、
このような形で
作物をつくると水はけが良いのだろう。
しかし作業する農家さんが高齢化しているから
機械化しずらい、段々畑では継続が難しいといわれています。

先日、越前和紙の職人さんの家を訪ねたときも同じようなことをいわれた。
「私のつくる紙は、段々畑で植林している楮からつくる。
でも、和紙の生産者も高齢化してきてね」
段々畑でつくられた楮は水はけがいいから良質な和紙ができるといわれている。
もちろん今の時代は畑でも楮が植えられきています。
林業も同じようなことが言われる。
紀州のように傾斜の激しい土地に
植林している木は油分が多く粘りが強い。
確かに木を人間に代えて想像したら
崖っぷちのようなところで生きていたら
根をはって地にしっかりつかないと
すぐに倒れてしまいますよね(笑)
6年前くらいになるだろうか?
舅と姑に山仕事のお話を聞き、メールニュースにまとめたことがあります。
トラックや林道が無かった時代の山仕事
主人から聞いた話ですが、
海外の木は、たいてい日本のような傾斜に植林されておらず
平地に近い土地で、伐採されるので
植林してから伐採されるまでのコストが全く違うそうです。
そうそうなんでこんな話になったのか?
今、小川社の山sun通信を製作中。
「蜜ロウワックス仕上げ 紀州杉 柾目のブラインド」が商品化されます。
そこで他のブラインドなどと比較して
いたら、WAVEしすぎて原料が生産される地形をクローズしてみました。

▲蜜ロウワックス仕上げの杉ブラインド
でもよく考えてみれば
ブラインドの板は機能上、かなり薄いし、常に紫外線にあたる窓に設置するので
ブラインドの板がめくれあがったら
ブラインドの機能がはたせません。
製材の時点では、狂い少ない柾目。
材は油気の多い、紀州杉だったらまさに「用の美」
値段は高いが
メーカーは「100年もつブラインド」という姿勢で生産しており、
美術館などでも多く使われているそうです。
紀州の地形を生かした商品に育てようと
あちこちの視点から商品をみています。
誰か地形と作物の関係で詳しい方、是非教えてください。
宜しくお願いします。