いつもあっている人でも
意外と会話する幅って決まっており
本をキッカケに会話がはずむってことありませんか?
 →←
→←
先日、cafeスケールの濱野さんの声かけで「アート、デザイン関係の興味のある人の雑談のワーク」がありました。
そこで濱野さんが「深澤さんの本を貸して、代わりにコレ読んで下さい」と渡された本。
当時は何も考えていなかったですが・・・・・・
自分の高校時代からセゾン文化事業がはじまっており
よくよく考えると、かなりセゾン系の発信のサブカルチャー文化に多くの刺激を受けていたことに気づきました。
まだ読んでいませんが、16歳~24歳の自分が夢中になっていたフィールドを思い出しそうです。


同じく、先日の雑談ワークにきていた
紀伊長島のデザイン会社ディグリーンのMさんが「貸して下さい」といった本。
自分の中では、この2冊が一番大切な本。
Mさんは一ヶ月ほど海外に行かれるのでそのときに読みたいそうです。
一瞬「なくさないかな」とちょっとだけ不安になりましたが
若いMさんが、この本を読んだ感想も聞きたいなとも思い・・・・・貸しました。
生物学から展開する造形論は、自分もが一番好きな分野です。
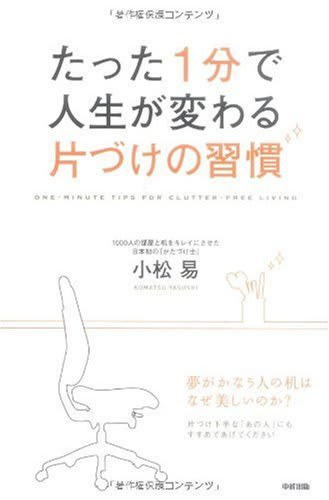
▲ブログに書いたせいか色々な人から「続いている」と声をかけてくれ、反響があったのはこのDVD。
誰でもスタートしやすい片付け方法で、レクチャーが展開されます。片付けの方法論というよりは、
自分の習性を見直すのが目的。はじめて10日しか経っていないので大きなことは言えませんが
「人生を変える」というコピーは大げさでも無いような気がします。
DVDを見たときはさほど感動しなかったけど、実践してみると「なるほど」と思うことが多いい。
なぜか?結婚してから、小川の家の納戸の整理、実家の父の事務所解体の整理、父が亡くなり実家の整理
小川製材の工場の整理など、大掛かりな片付けを受け持つことが多く、また自分たちの家庭も4回引越したためか?
元々片付けや掃除が好きではなかった自分にとって、大きく変わったのがこれらの作業でした。
大きく変わるというとなんだかロマンチックですが、なんせ片付けですから。正直いうと誰もがあまりしたくない役割です。(笑)
しかし「なにかを始めるより、何かを整理するほうが大きなエネルギーを使う」と気がつきました。
しかし、また日常生活に戻ると 片付けって難しいんですよね。
このDVDはこの類の本と言っていることは、さほど変わらないのですが
すごく小さなことからはじめるので、このやり方は自然に身体が動くから不思議です。
人生、夢のような出来事で変革するよりも身近なことから気がつくほうが、変革できるのかもしれないな・・・・・。
同じく整理整頓の発展形系の本です。

▲デザイナー、アートディレクターの佐藤可士和さんの本。

▲アートディレクターの佐藤可士和がディレクションしたキャラクター。モッチはおしりだけちょっと毛があって、そこもさわりたくなるような感じになり、ケボに関しては、ふわふわした感じでカラフルに。
従妹の子どもはNHK教育番組「英語で遊ぼう」が大好きで3歳のころから自分から英語を習いたいと」といったそうです。
また幼なじみの子どもも「この番組に釘づけになっている」とのこと。
製作スタッフを調べたら、なんとアートディレクターは佐藤可士和さんでした。
番組プロデューサーは
「いちばん意識しているのは、子どもたちに英語に親しんで貰うこと。遊んで貰う、ちょっとでも好きになってもらう。
タイトル通りですけど、製作中に壁にぶつかったときはいつでもそこに戻りますね」
と語っていました。
「好きになってもらうのが、実は一番大変なんですよ」
そこで子ども達に好きになってもらう仕掛けとして、アートディレクションを佐藤可士和さんに依頼したとか。
この番組は“視覚で英語を楽しむ”ようにつくられているなーとおもっていましたが
番組キャラクターも「クマ」や「うさぎ」ではなく、触りたくなる感覚をそのままキャラクターにしているのも凄い。
によく子どもの行動を観察しているなぁと思います。
この本は主人がプレゼントしてくれました。
はじめは(私に整理整頓なんて嫌がらせか?(笑))とも思いましたが、意外と面白かったです。
佐藤さんの整理の仕方は、ダイナミックで物事の本質にえぐるような感じがします。
デザイナーなどの職業病だとは思いますが、整理術やいつも身の回りを異常にキレイする人は多いのです。
個人的にはちょっと神経質すぎない?とも思うこともありますが
野球で言えば手の延長であるグローブの手入れをするのと同じようなもので
デザイナーさんは
視覚、触覚、など五感や深層心理に働きかける仕事なので、異常なまでに空間をリセットしないと、
クリアな状態で集中して生み出し、創造し、完成を高められなられないんだろうなーと思います。
ちなみに佐藤可士和さんの事務所は、椅子の位置もフローリングの線に対し、ピッシと並んでいるそうです。
オフィスに入らしたお客様にとっては、事務所に入った瞬間からプレゼンが始まっているという考えをお持ちの方だそうです。
それにしても、お母さん同士で佐藤可士和さんの話がでるとはビックリです。
今はアマゾンや色々なサイトで色々情報を得ることができるので、色々な書籍が手に入りやすくなりましたが、
やはり人から人の方が会話が生じるので、より面白いですよね。
今回、久々に本の行き来があり、本は本棚に入れるものではないよなーと改めて思いました。
車の価値感も変わりつつある時代なので
有志で本をシェアする共同本棚とでもいうのか?
いつかそんな時代がくるかも知れないですね。
意外と会話する幅って決まっており
本をキッカケに会話がはずむってことありませんか?
 →←
→←
先日、cafeスケールの濱野さんの声かけで「アート、デザイン関係の興味のある人の雑談のワーク」がありました。
そこで濱野さんが「深澤さんの本を貸して、代わりにコレ読んで下さい」と渡された本。
当時は何も考えていなかったですが・・・・・・
自分の高校時代からセゾン文化事業がはじまっており
よくよく考えると、かなりセゾン系の発信のサブカルチャー文化に多くの刺激を受けていたことに気づきました。
まだ読んでいませんが、16歳~24歳の自分が夢中になっていたフィールドを思い出しそうです。


同じく、先日の雑談ワークにきていた
紀伊長島のデザイン会社ディグリーンのMさんが「貸して下さい」といった本。
自分の中では、この2冊が一番大切な本。
Mさんは一ヶ月ほど海外に行かれるのでそのときに読みたいそうです。
一瞬「なくさないかな」とちょっとだけ不安になりましたが
若いMさんが、この本を読んだ感想も聞きたいなとも思い・・・・・貸しました。
生物学から展開する造形論は、自分もが一番好きな分野です。
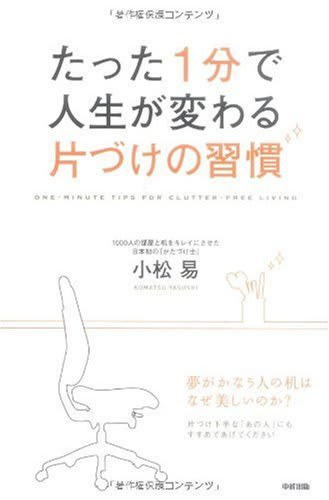
▲ブログに書いたせいか色々な人から「続いている」と声をかけてくれ、反響があったのはこのDVD。
誰でもスタートしやすい片付け方法で、レクチャーが展開されます。片付けの方法論というよりは、
自分の習性を見直すのが目的。はじめて10日しか経っていないので大きなことは言えませんが
「人生を変える」というコピーは大げさでも無いような気がします。
DVDを見たときはさほど感動しなかったけど、実践してみると「なるほど」と思うことが多いい。
なぜか?結婚してから、小川の家の納戸の整理、実家の父の事務所解体の整理、父が亡くなり実家の整理
小川製材の工場の整理など、大掛かりな片付けを受け持つことが多く、また自分たちの家庭も4回引越したためか?
元々片付けや掃除が好きではなかった自分にとって、大きく変わったのがこれらの作業でした。
大きく変わるというとなんだかロマンチックですが、なんせ片付けですから。正直いうと誰もがあまりしたくない役割です。(笑)
しかし「なにかを始めるより、何かを整理するほうが大きなエネルギーを使う」と気がつきました。
しかし、また日常生活に戻ると 片付けって難しいんですよね。
このDVDはこの類の本と言っていることは、さほど変わらないのですが
すごく小さなことからはじめるので、このやり方は自然に身体が動くから不思議です。
人生、夢のような出来事で変革するよりも身近なことから気がつくほうが、変革できるのかもしれないな・・・・・。
同じく整理整頓の発展形系の本です。

▲デザイナー、アートディレクターの佐藤可士和さんの本。

▲アートディレクターの佐藤可士和がディレクションしたキャラクター。モッチはおしりだけちょっと毛があって、そこもさわりたくなるような感じになり、ケボに関しては、ふわふわした感じでカラフルに。
従妹の子どもはNHK教育番組「英語で遊ぼう」が大好きで3歳のころから自分から英語を習いたいと」といったそうです。
また幼なじみの子どもも「この番組に釘づけになっている」とのこと。
製作スタッフを調べたら、なんとアートディレクターは佐藤可士和さんでした。
番組プロデューサーは
「いちばん意識しているのは、子どもたちに英語に親しんで貰うこと。遊んで貰う、ちょっとでも好きになってもらう。
タイトル通りですけど、製作中に壁にぶつかったときはいつでもそこに戻りますね」
と語っていました。
「好きになってもらうのが、実は一番大変なんですよ」
そこで子ども達に好きになってもらう仕掛けとして、アートディレクションを佐藤可士和さんに依頼したとか。
この番組は“視覚で英語を楽しむ”ようにつくられているなーとおもっていましたが
番組キャラクターも「クマ」や「うさぎ」ではなく、触りたくなる感覚をそのままキャラクターにしているのも凄い。
によく子どもの行動を観察しているなぁと思います。
この本は主人がプレゼントしてくれました。
はじめは(私に整理整頓なんて嫌がらせか?(笑))とも思いましたが、意外と面白かったです。
佐藤さんの整理の仕方は、ダイナミックで物事の本質にえぐるような感じがします。
デザイナーなどの職業病だとは思いますが、整理術やいつも身の回りを異常にキレイする人は多いのです。
個人的にはちょっと神経質すぎない?とも思うこともありますが
野球で言えば手の延長であるグローブの手入れをするのと同じようなもので
デザイナーさんは
視覚、触覚、など五感や深層心理に働きかける仕事なので、異常なまでに空間をリセットしないと、
クリアな状態で集中して生み出し、創造し、完成を高められなられないんだろうなーと思います。
ちなみに佐藤可士和さんの事務所は、椅子の位置もフローリングの線に対し、ピッシと並んでいるそうです。
オフィスに入らしたお客様にとっては、事務所に入った瞬間からプレゼンが始まっているという考えをお持ちの方だそうです。
それにしても、お母さん同士で佐藤可士和さんの話がでるとはビックリです。
今はアマゾンや色々なサイトで色々情報を得ることができるので、色々な書籍が手に入りやすくなりましたが、
やはり人から人の方が会話が生じるので、より面白いですよね。
今回、久々に本の行き来があり、本は本棚に入れるものではないよなーと改めて思いました。
車の価値感も変わりつつある時代なので
有志で本をシェアする共同本棚とでもいうのか?
いつかそんな時代がくるかも知れないですね。

















