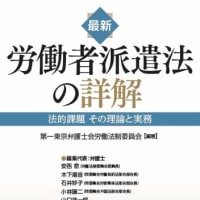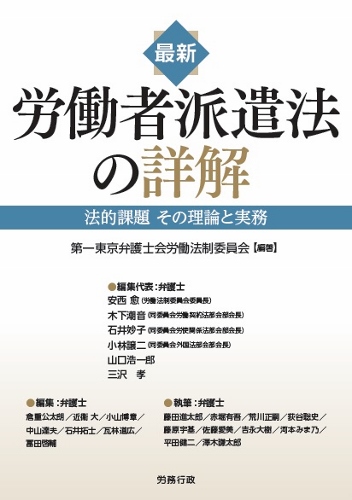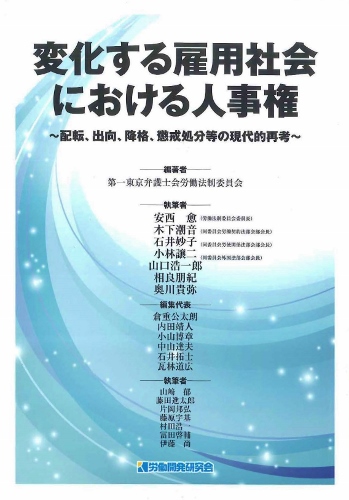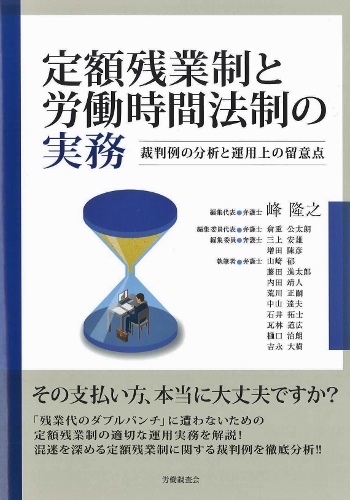-
民法上の原則では,「当事者が雇用の期間を定めなかったときは,各当事者は,いつでも解約の申入れをすることができる。」(民法627条1項)とされており,一見,使用者は,正社員であっても,民法627条2項等所定の期間前に解約を申し入れてさえいれば,労働契約を自由に終了させることができるようにも思えますが,実際には,正社員の解雇は厳しく制限されています。
-
まず,不当労働行為となる解雇,女性であることを理由とする解雇,公益通報をしたことを理由とする解雇等,一定の場合については,法律上解雇が禁止されています。
-
また,使用者が労働者を解雇しようとする場合には,原則として,30日以上前に解雇の予告をするか,30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払わなければなりません(労基法20条)。
解雇予告又は過去予告手当の支払なしに即時解雇がなされた場合は,即時解雇としての効力は生じませんが,使用者が即時解雇に固執する趣旨でない限り,通知後,30日の期間を経過するか,又は通知の後に所定の解雇予告手当の支払をしたときは,そのいずれかのときから解雇の効力を生じることになります(相対的無効説,細谷服装事件における最高裁昭和35年3月11日判決)。 -
さらに,当該解雇が,客観的に合理的な理由を欠き,社会通念上相当であると認められない場合は,解雇権を濫用したものとして,解雇は無効となります(労働契約法16条)。
訴訟で解雇の有効性が争われた場合,解雇権濫用の有無が中心的争点となることが多いのですが,原則として解雇は無効で,特別な事情がある場合に限り解雇が有効となるというように,原則と例外が逆転し,解雇権濫用法理の濫用ともいうべき運用がなされていますので,有効な解雇を行うことは極めて難しくなっています。
解雇を契機として紛争が表面化し,解雇権濫用の疑いが強いことを理由に,多額の解決金の支払を余儀なくされることが多くなっていますので,弁護士に相談せずに解雇することは,極力控えることをお勧めします。
最新の画像[もっと見る]