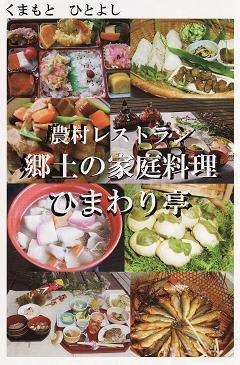出久根さん68歳古本屋の店主だったが直木賞作家になった
嵐の日の講演を聞く人もすごいが やってくる講師もすごい
お話は石井桃子の「ノンちゃん雲に乗る」に生活の原点を見た話
皇后殿下の好まれた童話の話しは講演でしか聞けないマル秘話
また新刊書店は良く売れるので 補充が間に合わない
それで本棚に隙間があり 地震の時に本棚から落ちることがある
古本屋はぎっしり詰まっているので地震に強い
本棚の本はぎっしり詰めるに限ると笑わせた
出久根さんは少年時代は貧乏で本を買えなかった
移動図書館で借り 漱石全集や江戸川乱歩全集を読んだ
中学生の時に自転車で16キロ離れた書店に行き
立ち読みする楽しみを覚えた
邪魔だと文句を言う客に 女性のご主人は
「あの子たちは 将来のお客さんなの」と言ってとがめなかった
その時に 本屋は貧乏人も金持ちも 大人も子供も
人を区別しない 就職先は書店とこの時に決めた
学校に来た求人で東京・月島の本屋に就職が決まった
上京してから初めて勤め先が新刊書店ではないと知った
かびくさい15坪の店に上から下まで本が積んである
「出世できるような店じゃないな」とがっくりした
しかし今になってみるとそれが良かった
新刊書店では忙しい 古本屋は暇だから本が読める
売り物の本なので 感動した言葉は書き写して置いた
自分の字で書いたものは 後々必ず読み直す
自分の精神を培った過程を見ることができ
それが貴重な財産となる
本を読むコツは 「これは何だろう」と考えながら読む
1冊読んで完結しないでそれに付随する本を数冊読む
人は誰でも後世に名を残すことができる それは
後ろ指さされない生き方をし 楽しい人生だと常に思うこと