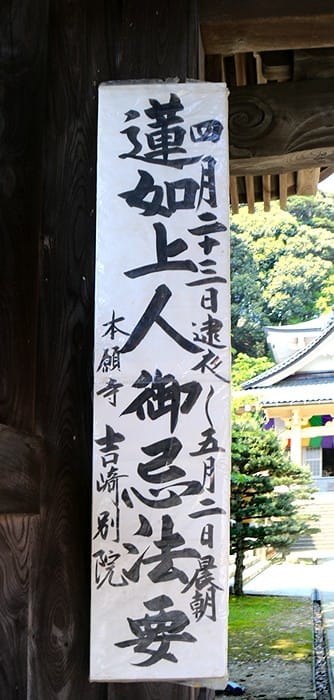勅使門(唐門)
大本山 永平寺
福井・永平寺町
永平寺は
1244年に開山された曹洞宗の大本山です
宗祖は道元禅師
本尊は釈迦如来・弥勒仏・阿弥陀如来
33万平方メートルにも及ぶ広大な敷地があり、
境内には大小70棟余りの建物が並んでいます、
特に回廊で結ばれている七堂伽藍は
日常の修行に欠かすことのできない大事な建物であると同時に
(山門・仏殿・法堂・僧堂・大庫院・浴室・東司などの 七堂伽藍)
樹齢600年を越える老杉の巨木の中にたたずむ
七堂伽藍は見事というほかに言葉が見当たらない。
修行僧(150名もいらっしゃいます)の修業は厳しく、
雪の降る冬は特に厳しい環境に置かれる
お土産屋さんの駐車場に置いて、お土産で清算します


通用門(つうようもん)
観光客はここから入ります

吉祥閣(きちじょうかく)

境内図

傘松閣(さんしょうかく)

230枚の花鳥図

山門にある四天王


鐘楼堂


大庫院(だいくいん)



中雀門(ちゅうじゃくもん)
(先に見えるのは山門)

仏殿

承陽殿(しょうようでん)

承陽門(しょうようもん)



祠堂殿(しどうでん)舎利殿(しゃりでん)






今日も
ご最後まで覧頂きましてありがとうございました
明日も皆様のお越しをお待ちしております
8時間ダイエット
5月13日より
−3.55kg
70.00kg