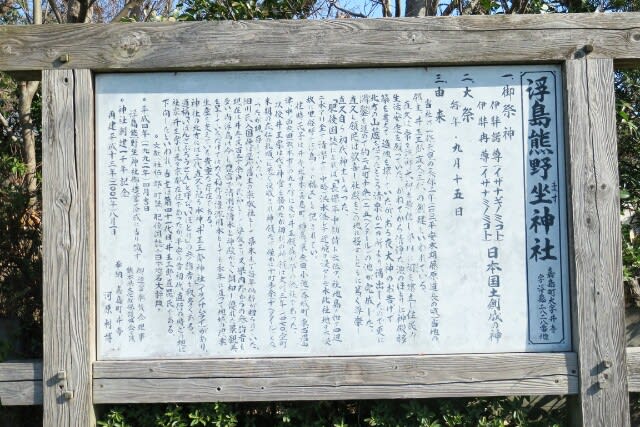舞鴫文殊堂
-もうしぎ もんじゅどう-
熊本・宇城市
3月20日~4月16日 熊本一人旅の記録
この度の震災に対し、心からお見舞い申し上げますとともに
一日も早いご復興と、皆様のご健康を心からお祈り申し上げます。
1593年(文禄2年)、
文禄の役において肥後国城主加藤清正のもと従軍した
舞鴫(現熊本県宇城市小川町東海東内)出身の勇臣らによって、
朝鮮京畿道の文殊寺より勧請、創建された。
西の大宰府とも称する
文殊菩薩を本尊に、
阿弥陀如来、秋葉明神、生目八幡の4神仏を合祀する
(神仏習合の仏堂)
熊本地震によって
熊本城の石垣が崩れました。
武者返しと呼ばれる
頑丈な石垣の積み方の原点ともいえる
舞鴫文殊堂へ上る坂道の両側に積まれた石垣を知ってもらいたいとUPしました。


立派な石垣
熊本城の石垣 (武者返し)を造った石工が造ったそうです
(武者返しの原点と言うべき石垣です)







舞鴫水神
1963年(元禄6年)の当地の大水害の後、
水難の守護神として水天宮(福岡県久留米市)より勧請

文殊菩薩は、
「三人よれば文殊の知恵」ということわざにあるように、
知恵と弁説をつかさどる仏であるため、
学問の神さまとして有名な菅原道真を祀る天満宮同様に、
成績向上、進学成就などの目的で、学生・受験生らが参拝に訪れる






今日も
最後までご覧頂きましてありがとうございました
明日も皆様のお越しをお待ちしております