このところ、毎日雪に埋もれる生活だった。
あらためて、庭に見る雪景色の美しさを思った。
雪景色の美しさには、これまでも何度も感動してきた。幾度となく書き残してきた。
今朝の思いもまた格別だ。
車の凍てついた雪を除いていると、東山から朝日が昇り始めた。
カメラを取りに戻り、山の端にかかり上る間際のお日様を撮った。
深呼吸し、神々しい陽の光を浴びた。
すがすがしい気持ちで、孫を学校まで送った。





 磐梯 雲に隠れる
磐梯 雲に隠れる
キリの大木から風花が舞い散る。
そのキラキラ落ちる美しい風花を浴びながら、シャッターチャンスを狙った。


いつかの感動を拙ブログに見た。
【癒される 風花】 2012-01-14 https://blog.goo.ne.jp/tosimatu_1946/e/4d26660809ac8bbf231cefeaa2b770e5
一部をあげる
《 雪の花を写しに庭に出た。長靴が埋まるほどの積雪だ。朝日が燦然と差し、輝く枝の雪が美しい。》
《真上の桐の枝を見上げると、青空に薄いもやが流れている。心が洗われるようだった。それはたぶん、眼に映ったその美しい光景はこころのファインダーを通るからに違いない。
そしてまた、その感動は冷たい澄みきった空気がなければ生まれないものだろう。とすると、本当の感動は、そのとき一瞬の美しさで、写真のデータは偽物の美しさかもしれない。
一瞬の感動であれば、しばらくはその余韻を楽しむことは出来るが、いずれ思い出として記憶されるものだ。記憶をたどり、これまでの感動のいくつかは思い出せる。
出来ればこれからも沢山の感動を味わえる人生でありたいものだ。
****************
もう10年も前のことだが、嫌な思い出がある。
この雪の美しさを新聞に投稿したことがあった。その日、その文章について粗暴な脅迫の電話があった。
1~2分の一方的な話で恐ろしさを感じた。あまりにひどい話で、警察へ相談に出向いたことがあった。
趣旨は、「みんな大雪で苦労しているのに、風物詩的な書き方をするな。書くのも悪いが、載せる新聞社も悪いと。今後一切投稿するな、殺すぞ!」と。
奥会津金山の記述が悪かったのか?。苦労を逆なでするつもりもないし、しばらく我慢して春を待とうとの本意だった。
人それぞれの思いであり、尊重されるべきだ。どこの誰かもわからない、どんなに被害意識があったにしても異常とも思える電話だった。
(参考までに) 以下、新聞掲載文
「会津の雪景色を楽しみたい」 福島民友新聞「窓」(2011.2.1付)
今朝も枯れ木に雪の花が咲いた。妻は積もった雪かきに余念がない。昨年末の大雪で、庭はうずたかい雪に埋まっている。
今が一年中で一番の寒い時期、しんしんと降る雪、横殴りの吹雪の日と、毎日自然の厳しさを見つめている。
何年も前に、読者の欄(*)に「豪雪に悩む地域の方のつらさはわかるが、私は雪が大好きだ。そして雪が降るから冬が好きだし、会津が好きだ。」と書いた。
その数日後、奥会津金山の人からお叱りのはがきを貰い、それで済まない辛さを詫びて反省したことがあった。
確かに、来る日も来る日も鉛色の空から落ちてくる雪には恐ろしささえ感じるし、膝ほどの雪道でも、開けるのに一苦労だ。
とはいうものの、雪を厄介者としか見ない生活は味気ない。厳寒の中にも雪のぬくもりも感じられるものだ。
しばらくは雪マークの予報が続き磐梯の雄姿も見えないが、やがて節分、雪解けの陽が差す日も訪れるだろう。
それまで、密かに会津の雪景色を楽しみたいと思っている。
読者の欄(*)
「楽しみたい会津の雪景色」 朝日新聞「声」(2005.1.23付)
昨夜来の吹雪に車がすっぽり埋もれていた。市道までの雪かきを妻に任せ、徒歩で出勤することにした。
「雪の降る街を」と口ずさみながら、何を考えるでもなく歩を進めた。太郎の屋根、次郎の屋根に降り積む雪は人の心にお構いなしだ。
豪雪に悩む地域の方のつらさは時折の体験から十分わかるが、私は雪が好きだ。そして雪が降るから冬が好きだし、会津が好きだ。
立ち止まり手袋に舞い降りた雪の美しさに見入った。時折小止みになると、目の前に杉林の雪景色が山水画のようにぼんやりと浮かんだ。
「雪は天から送られた手紙である」と言ったのは中谷宇吉郎。私には雪は天からのこの上ない贈り物だ。
雪景色にどれほど感動し、こころ癒されるか知れない。
雪を厄介者としか見ない生活は実に味気ない。厳寒の中にも雪には暖かささえ感じられるものだ。
厳しい寒さに耐える静寂の木々だが、じきにすべてが萌える季節が巡る。
雪に埋もれる会津の冬をしばし楽しみたいと思っている。
************
いつか書いたことがあるかも。忘れて、雪景色を愛でたいと思う。
日々生きて、いろいろな幸せを楽しみたい。
まずは「存命の喜び、日々に楽しまざらんや」 兼好

















 磐梯 雲に隠れる
磐梯 雲に隠れる

 日橋川の流れ、ゆく川の流れは絶えずして。
日橋川の流れ、ゆく川の流れは絶えずして。


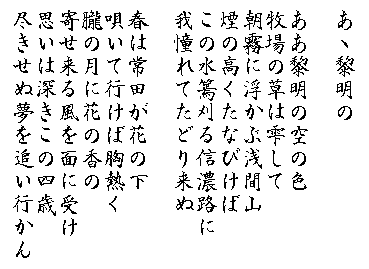
 庭で
庭で




 リンゴ咲く
リンゴ咲く 





 チオノドグサ
チオノドグサ
 スノードロップ
スノードロップ


















