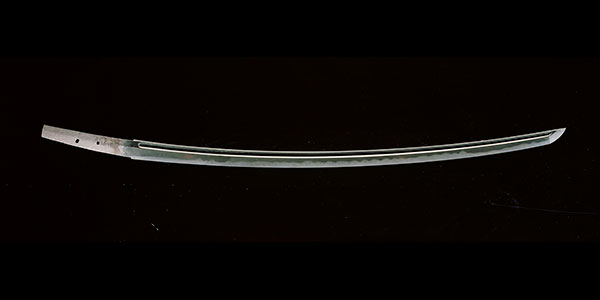P+D MAGAZINE
著者・原田まりるにインタビュー!
哲学を体感せよ! あなたを救う新しい言葉との出会いが詰まったコミック版『ニー哲』の魅力!
コミックで読むと、哲学はこんなにわかりやすい!
第5回京都本大賞を受賞した、原田まりる著『ニーチェが京都にやってきて17歳の私に哲学のこと教えてくれた。』のコミック版が、2018年11月12日に発売。
ある日突然、現代に降臨したニーチェが、悩める女子高生のアリサに、哲学の教えをナビゲート。生きるヒントが詰まった哲学漫画の読みどころを、著者の原田まりるさんにインタビューしました。
コミックで読むと哲学はこんなにわかりやすい!
京都在住の女子高生・アリサの前に現れた青年は、なんと「ニーチェ」。迷えるアリサに、わかりやすく人生哲学を説いてくれます。ニーチェの他にも、ショーペンハウアーにキルケゴール、サルトルなど、哲学者が次々降臨。哲学を知らなかったアリサは、彼らとの出会いを通じて成長していきます。
人生を豊かにする言葉たち――哲学との出会い
――まずは、原田さんと哲学の出会いについて教えてください。
原田まりるさん(以下、原田):もともと、尾崎豊さんの大ファンだったんです。その歌詞に感銘を受けて、「生きるって何」「自由って何」ということの答えを知りたい、と強く思っていました。どうすればその答えを知ることができるのかわからずに悩んでいたのですが、ある時、近所の書店で、哲学書の特集がされていて。それを見て、哲学書を読んでみよう、と思ったのがきっかけです。
――哲学者にもさまざまな人がいますが、原田さんが特に影響を受けた哲学者は誰ですか?
実際にお会いしたことはないのですが、中島義道先生です。先生の著書を読んで、哲学への興味・関心がより強くなりました。「そもそも、生きるということはしんどいんだ」、ということが、腑に落ちたというか。
パスカルの言葉で「幸福とは気を紛らすことである」という言葉があるのですが、今まで悩んでいて答えが出なかったことに、光を当ててくれるのが哲学であると思います。
――『ニーチェが京都にやってきて17歳の私に哲学のこと教えてくれた。』(以後『ニー哲』)のコミック化にあたって、「哲学」という、一見敷居の高い学問を、分かりやすく、身近に感じられる本にするには、どのような点に苦労しましたか?
原田:もっとも気を遣ったのは、実際に哲学者が話していることを、超訳しすぎると、誤訳になってしまうところ。時代背景も大きく異なるので、哲学者が話している意図を、できるだけ意訳にならないように現代風にわかりやすくする、というところに気をつけましたね。
――確かに、違和感なく読むことができて、哲学者の言葉もスッと入ってきます。 ニーチェほか、偉大な哲学者たちが現代に降臨する、という設定は、どのように思いついたのでしょうか?
原田:哲学をわかりやすく伝えるために、キャラクター設定はしっかりしたい、と思っていたので、翻訳されている哲学書をじっくり読んで、ニーチェや他の哲学者の言葉のテンションをくみ取ることから始めました。そして、もし現代に居たら、と想像を膨らませ、キャラクターを作り、デフォルメして描いていきましたね。
例えばニーチェだったら、内向的でピュアな性格なのに、「女性とは」みたいなことを語っていたりするので、ネット民っぽい青年、という設定にするとしっくりくるかな、とか。現代という時代背景に溶け込みやすいように考えながら、哲学者たちの個性が際立つようにキャラクターを肉付けしていきました。
――確かに個性豊かなイケメンで、実際に会ってみたいと思わせるようなキャラクターばかりですね。コミックならでは、というこだわりの箇所や、苦労した点はどんなところですか?
原田:コミカライズにあたって、作画を担当してくださった荒木宰先生に、とても良く内容を理解していただいて。荒木先生がきっちり各キャラの性格を掴んで描いてくださったので、苦労したというところはないかもしれません。小説版では説明がメインだったので、コミック版ではポップなラブコメ要素も少し足して、名言にもインパクトを持たせた形で登場するようにしました。コミックだけのオリジナルの話も創ったり、より一層キャラクターが身近に感じられるようなエピソードを追加しましたね。また、ルー・ザロメというニーチェが心酔していた女流作家がいたのですが、コミック版にはザロメも登場させたりして主人公であるアリサちゃんの嫉妬心を煽りながら哲学思考に繋げるエピソードなんかもいれています。
哲学の持つ力とは?
――主人公のアリサの人物像は、どのように創っていったのですか?ご自身を投影している部分などは?
原田:男の子のキャラクターが多数出てくるので、趣味が高じたBL(ボーイズラブ)のような雰囲気にならないように(笑)、アリサという女の子を主人公にしました。「女の子に嫌われないタイプの女の子」で、ニーチェとも恋愛関係にならず、自我も強すぎない。同性からも異性からも共感を呼べるキャラクターにしたいと思ってできたのがアリサです。自分を投影しているところは、特にないですね(笑)。
――読んでいると、アリサの等身大の悩み事に、思わず感情移入してしまいます。京都の町が舞台となっていることも、作品にピッタリですね。
原田:そうですね。マジックリアリズムではないけれど、京都は、哲学を始めとする学問や、思想などに雰囲気が合う町だと思います。それに、私にとっては生まれ故郷でもあるので、情景も描きやすんですよね。
――作品中にも出てくる「縁切り神社」には行かれたことはあるのですか?
原田:縁切り神社には、定期的に行きます! 親に「そんな(何回も)行く?」と言われるほど(笑)。厄払いにも効果があると言われていて、しかも願いが叶うと言われているパワースポットですね。正直オカルトはあまり信じませんが、周りの友だちに聞いても効果があるという声が多いですよ。何かトラブルが起きたときにはぜひ、行ってみることをおすすめします。
――京都だけでなく全国にあるみたいですね。ぜひ行ってみたいです。
ところで、ニーチェが説いている、「永劫回帰を受け容れる」ということや「自己流の価値をしっかり持つこと」などは、生きていく上でとても励みになりますが、原田さんご自身も、支えにしている哲学の教えはありますか?
原田:たくさんありますが、意識的によく思い出すのは「事実などはなく全ては解釈だ」「死ぬ直前にリピート再生したいような人生を」。ことあるごとに、思い出しますね。人生訓として身に染みます。
――とてもいい言葉ですね。たとえばニーチェはとても自身に溢れ、前向きですが、原田さんの考える「哲学のちから」とはどんなところだと思いますか?
原田:哲学って、ふんわりしていてわからないことを、ズバリ、言い当ててくれるんです。例えるなら毒舌なコメンテーターのように爽快感を与えてくれる存在ですね(笑)。迷うことや、嫌なことがあったりしたときに、俯瞰で見る視点を与えてくれるので、冷静な友だちを持ったみたいな感覚がありますね。
――哲学が自分を導いてくれるんですね。たくさんの哲学者がいて、その教えもさまざまですが、原田さんの座右の銘は?
原田:「好事、魔多し」と「窮鼠猫を噛む」ですね(笑)。私、調子に乗ったことは一度もないって言い切れます! いいことがあるときこそ警戒しなければならない。慎重に、警戒心旺盛ですし、常に懐疑的ですね。ですので、定期的に縁切り神社通ってしまうのかもしれません(笑)。
――それは、ポジティブなのでしょうか?
原田:愚痴をこぼしたりもしないので、ポジティブです! 考え方としては、もし、ひとつの良いことがあったとします、でも、カーナビの経路候補みたいに、「他にこういうパターンでこういうことが起きるかもしれないし……」、と幅広い選択肢を複数持ち、リスクを減らす思考をするんです。そうすることで、もし最悪なことが起こっても、逆にそれから他の道を選び、最善の策を尽くせば、最小限のダメージで済むと思います。
――確かにそうかもしれません。幅広い思考が大切なのですね。
ところで、作中にも出てくる、キルケゴールの言葉で、「何でも手に入るから幸せ、とは言いがたい」「誠実に自分の人生と向き合うことが大切」「人生は後ろを向くことでしか理解できないが、前にしか進めない」とありますが、原田さん個人の見解はいかがですか?
原田:誰しも、高級車が欲しいとか、良い時計が欲しいとか、そういう欲求があるかもしれませんが、人間として追い求めるべきは「高い精神性」だと思っています。といっても私も全然、「ポルシェのケイマン欲しいなー」とか常日頃考えていますけど(笑)。
みんな理想を求めたい気持ちはあると思うけれど、現実との折り合いの中で、「結局こういうものだし」、とどこかで自分を納得させているんだと思います。たとえ人に裏切られたりしても、それも糧になるんじゃないかと思いますね。人生経験が豊かな人には特に、共感していただけるんじゃないかな。コミックには、小説にはないオリジナルのエピソードも盛り込まれているので、ぜひ手にとってみて欲しいです。
_MG_6573_01
コミックならではの読みどころは?
――他、コミックならでは、という箇所はどんなところですか?
原田:ニーチェとアリサの距離がより近いところ。若い女の子がキュンとするようなエピソード、高校生特有の、早く大人になりたい気持ちや、思春期の繊細な思いを、小説よりも多く入れています。
――コミック化することで、どんな層に届けたいですか?
原田:小説を読むよりも、低カロリーで読めるので、入門編として、哲学を簡単に知りたい人に伝えたいですね。思い描いていたキャラクターが動くというところがとても新鮮なので、哲学を身近に感じていただけると思います。
――「哲学する」というのは具体的に言うとどういうことなのでしょうか?
原田:例えば、学校の授業のように、ソクラテスの時代から歴史を追って哲学史を学ぶことと、「哲学する」ことは違うと思うんです。「哲学する」というのは、既存の価値観だったり、知っているつもりでいることをもっと疑って、コアに近づいて行くという行為。アリサを通じて、読者の皆さんにも哲学してほしい、と思います。
――哲学を体感する、ということですね。
原田:そうですね。落ち込んだ時とか悩んだときの入門書にもぴったりだと思うので、ぜひ、体感しながら読み進めて欲しいです。コミックの中では「これが名言」というところを分かりやすく提示しているので、自分だけの「推し哲」を見つけるのもオススメです! 私の「推し哲」は、ショーペンハウアーかキルケゴールかな。
_MG_6691_01
――ズバリ、哲学とはなんだ、というと?
原田:固定概念からの解放。自由を与えてくれるもの。哲学とは、一面ではなく、いろんな角度から見て物事を理解するということであり、バイアスをとって偏見、固執しているものから自由になるということなので、独断してしまいがちなことを、自由にもっといろんな視点から考えられるようになります。自分でも、哲学を学んでから、寛容になったなと良く思いますね。
「~すべき」、というのは1つの考えであり、目の前に居る人は記号ではなく個人なのだから、排他的にならない、受け容れる、という考えを持てるようになりました。
――哲学を知ってからの人生を振り返ると?
原田:救われる部分が本当に多いです。波瀾万丈でしたが、後悔していることは特に無いですね。瞬間、瞬間でベストを尽くした、と言える。それは哲学の持つ力が大きいからだと思っています。学生の頃などは親や先生の言うことが全てと思いがちですが、どんなに小さい悩みだとしても、その時は自分の人生を揺るがすことであったりするので、そういう時に手にとって読んでもらえたらいいなと思います。
<了>
『ニーチェが京都にやってきて17歳の私に哲学のこと教えてくれた。』
プロフィール
原田まりる(はらだ・まりる)
作家・哲学ナビゲーター。
1985年、京都府生まれ。哲学の道のそばで育ち、高校生時、哲学書に出会い感銘を受ける。『ニーチェが京都にやってきて17歳の私に哲学のこと教えてくれた。』(ダイヤモンド社)で第五回京都本大賞受賞。2018年『アラフォーリーマンのシンデレラ転生』でカクヨムWEB小説コンテストキャラクター文芸部門大賞受賞。文芸誌「ダ・ヴィンチ」(KADOKAWA)にてAIヒューマンコメディ小説『ぴぷる』連載中。
![[芦部聡, 生島淳, 大友信彦, 熊崎敬, 小林深緑郎, 堂場瞬一, 永田洋光, 野澤武史, 藤島大, 村上晃一, 吉田宏]のそして、世界が震えた。 ラグビーW杯2015「Number」傑作選 (文春e-book)](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/31eaZnwDgkL.jpg)