我が家は毎週末、房総半島ドライブや道の駅、ショッピングセンターなどに家族3人で出かけます。
20才になる息子はこのお出かけをとても楽しみにしていて、出かける準備をしてるとウキウキしています。
障がいが重くて言葉を理解できなくても、親の動きを見て次の展開が読めるんですよね~。
卵アレルギーがあり、ペースト状のものしか食べられないので、外出にはお弁当持参。それとオムツも。
出先のレストランやショッピングセンターのフードコートでも、どこでも広げて食べさせちゃいます。
と言っても、食べさせるのは主人。外出先では、私とは食べてくれないんです・・・・。
車椅子に乗っていることと、大人なのに親に食べさせてもらっている姿は、周囲の目を引くようです。
特に子供たちは容赦のない視線を向けてくる。それだけ障がい児者に触れ合う機会がないってことなんですよね。
以前住んでいた大阪では、障がい児者がもっと街に出ていました。
大阪の北摂(ほくせつ)地区は、障がい児も地域の通常学級(支援学級ではない)で受け入れているので、その周辺の
ショッピングセンターに行くと見向きもされない。 「車椅子ですよ!見えていますか?無視してませんか?」って
言いたくなるくらい、フツーの存在なんですよ。
学校教育の受け入れ体制が、障がいの理解につながっているのかな~。
大阪では、重度の障がいがあっても地域の学校に通学する子どもが多くいて、重度重複障がいの息子もその一人でした。
人権運動が盛んな土地柄ならでは、ですね。
千葉に来て、地域の学校に通う障がい児があまりにも少ないことに驚きました。
それゆえに障がいの理解が進まないのかもしれませんね。
でも今住んでいる飯沼(いいぬま)は、ちょっと違うんです!
息子を車椅子に乗せて散歩していると、屈託のない笑顔で「こんにちは」と挨拶してくれる子ども達に出会います。
地区の方にお話しを伺うと、日々の生活の中で挨拶を大切にされていて、子ども達はそんな大人の姿を見て
自然に身につけて育ってきたことがわかります。
車椅子を特別視することもなく、ごくごく普通に受け止める子ども達に出会って、教育は学校だけでなく
家庭や地域の力も大切だと改めて感じました。
高齢者も子どもも、障がいがあってもなくても、全ての人がありのままの姿を認め合う社会を、飯沼から発信
できるのではないかと思いました。










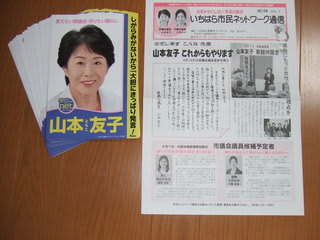



 。日本人ですな~。
。日本人ですな~。





