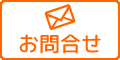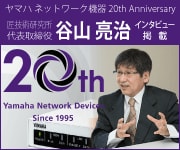Linux,Groovy-IoT, Arduino,GroveでSensorネット-Arduinoを試す
いつもアクセスありがとうございます。匠技術研究所の谷山 亮治です。
様々なセンサーからの情報をLinuxに集めることを試しています。
センサーその他様々なデバイスをつなぐ仕組みとしてArduinoマイクロコンピュータボードがあります。
Arduinoを使ってセンサ、制御、表示装置をつなぐ規格としてGROVEがあり、既に普及しています。
GROVE対応デバイスの使い方を知るためにGROVE Starter Kit for Arduinoを購入してみました。


私はこのキットにはArduinoマイクロコンピュータが含まれているものだと思い込んでいましたが、含まれていません。
そこで、Arduino本体と、Arduinoに重ねて使うことができる「Multifunction Shield」というデバイスを一緒に購入してみました。
Arduino本体だけでは視覚的に動作を確認することができないと思った次第です。
上の写真の箱に乗っているデバイス、下の写真の一番下にあるデバイスは同じもので、やはりGroovy-IoTでStarter Kitには含まれません。
Groovy-IoTについては前回の記事で概要を説明しています。
■ArduinoとMultifunction Shieldが動いているところ

これは、私のMacとUSB接続しているArduino上に装着したMultifunction Shieldを時計にして動かしている様子です。
Multifunction Shieldの開発元が配布しているライブラリと実装例が提供されているので、Arduinoの開発環境の使い方が判れば、時計を動かすことは簡単でした。
Arduinoも初心者、その機能を拡張するモジュールの追加も初心者でしたので、ここまで一日半ほどかかりました。大半はArduino開発環境をこさえる時間、使い方を知るためにLEDを点滅させるプログラムを作った時間になります。プログラムはサンプルが沢山あるので、それを使って変形して作りました。
■ArduinoとMultifunction Shield
Ardiunoは検索すると何種類も出てきます。メーカーもいろいろあるので「模造品」かと思って調べていると「正規の模造品」でした。
Ardiunoの仕様は公開されており、だれでもつくって良いそうです。オープン・ハードウエアとして普及しています。
そのため、目的に応じて様々な形をしたものがあり、様々な機能を載せたものがあります。
一番典型的なものはArdiuno UNOとして発売されたものです。これも、本家以外は”UNO Like”で、UNOの機能を備えていますが、ちょっとだけ違うところもあります。初心者の私には違いも何も判らず、正規版があることも知らなかったので、とにかく最初のArdiuno基板は”UNO”を目印に選びました。
「きっと失敗して壊す」と思って「二枚でいくら」の安価なArduino基板を選び、結果としては”UNO Like”品でした。問題があるかどうかも判りませんが「期待通り」動いています。購入品は電源が入るとLEDランプが点き、直感的に通電していることが判るので便利です。またこのLEDをプログラムで点滅させることができ、最初の一歩に適しています。
Multifunction Shieldの写真を見ると、Ardiuno本体と大きさがそっくりなので、重ねて使えそうです。
仕様も、どう使うかも全く知らずに購入しました。使い方マニュアルや、使い方の紹介Youtubeも購入後に見つけています。
手に入れてみると、四つの赤色LED、LED数字表示パネル、スイッチ、可変抵抗(いわゆるボリューム)、センサー、制御装置、通信装置などをつなぐ端子がついています。使うためには以下のマニュアルが必須です。
Multifunction ShieldのPDFのマニュアルはこちら(En)
■Ardiunoの電源は?
ArduinoとPC間をUSB接続するだけです。ArduinoはUSB接続から電力をもらいます。最初の一歩はそれで十分です。
Arduino基板に電源供給用のコネクタがついていますが、これを使う機会は少ないと思います。
Aduinoアプリが完成し、PC無しでArduinoを動かす場合、USB2規格以上の電力が必要な開発や稼働環境では電源アダプタによる電力の供給が必要です。PC無しでArduinoを使う場合も、USB2規格のUSB充電器を電源にすれば簡単に動きます。