日本映画の「おくりびと」がアカデミー外国映画賞を受賞し、話題になっています。
様々なメディアで取り上げられ、静かで淡々とした、しかし味わい深い日本らしい感情表現が世界に認められたと絶賛されています。
「おくりびと」は、英語タイトルでは departureと訳されています。
出発、とか、旅立ち、といった意味です。
ちょっと興味深く思いました。
つまり、「死者を送る人」に焦点をあてたタイトルではなく、「逝く」という現象そのものをタイトルにしているのです。
「おくりびと」は、「送る」「人」です。
日本語では「送る」は、もともと「意思的にあとからついていく」という意味で、去り行く死者を葬送したり別れを告げたりする意味も含まれます。
駅まで送る、卒業生を送る、などの送ると、死者を送る、はきわめて近い意味で使われます。
そこには、生きている人が死にゆく人への別れを惜しみ、死への道の途中まで送っていくというニュアンスが言葉の裏に込められているようです。
英語には、このようなニュアンスを含む言葉はありません。
モノなどを「送る」という意味のsendや、人を「見送る」のsee、see offなどは、死者を弔うという意味では使われていないようです。
「弔う」という意味では、grieveという単語がありますが、これは「死を強く悲しむ」という意味で、残された人々の感情を純粋に表した言葉です。
生きている人が死者の向かう先へついていこうとするニュアンスはありません。
日本語の「送る」という言葉を英語の「grieve」と比べてみると、東西の人の死生観の違いが表れているように思います。
日本では、白から黒へがらりと変わるかのように、生きている人がある日ある瞬間に「死ぬ」というよりは、生から死へと緩やかなグラデーションを持ちながら人は死へと移りかわっていく、という連続性があるように感じられるのです。
インドのベナレス(ワーラーナシー)は、仏教の聖地で、死を待つ人がここに住み、死を向かえると火葬されて、あるいはそのまま、ガンジスに流され荼毘に付されます。
この街では、生と死の境目を強く感じることができると言います。
仏教的な死生観に基づく空間だと思います。
仏教の価値観を色濃く残す日本文化の中では、「死者を送る」という言葉は自然な感覚なのかもしれません。
英語になりにくい言葉である「送り人」は、まったく発想を変えて、departureとタイトルをつけるしかなかったようです。
様々なメディアで取り上げられ、静かで淡々とした、しかし味わい深い日本らしい感情表現が世界に認められたと絶賛されています。
「おくりびと」は、英語タイトルでは departureと訳されています。
出発、とか、旅立ち、といった意味です。
ちょっと興味深く思いました。
つまり、「死者を送る人」に焦点をあてたタイトルではなく、「逝く」という現象そのものをタイトルにしているのです。
「おくりびと」は、「送る」「人」です。
日本語では「送る」は、もともと「意思的にあとからついていく」という意味で、去り行く死者を葬送したり別れを告げたりする意味も含まれます。
駅まで送る、卒業生を送る、などの送ると、死者を送る、はきわめて近い意味で使われます。
そこには、生きている人が死にゆく人への別れを惜しみ、死への道の途中まで送っていくというニュアンスが言葉の裏に込められているようです。
英語には、このようなニュアンスを含む言葉はありません。
モノなどを「送る」という意味のsendや、人を「見送る」のsee、see offなどは、死者を弔うという意味では使われていないようです。
「弔う」という意味では、grieveという単語がありますが、これは「死を強く悲しむ」という意味で、残された人々の感情を純粋に表した言葉です。
生きている人が死者の向かう先へついていこうとするニュアンスはありません。
日本語の「送る」という言葉を英語の「grieve」と比べてみると、東西の人の死生観の違いが表れているように思います。
日本では、白から黒へがらりと変わるかのように、生きている人がある日ある瞬間に「死ぬ」というよりは、生から死へと緩やかなグラデーションを持ちながら人は死へと移りかわっていく、という連続性があるように感じられるのです。
インドのベナレス(ワーラーナシー)は、仏教の聖地で、死を待つ人がここに住み、死を向かえると火葬されて、あるいはそのまま、ガンジスに流され荼毘に付されます。
この街では、生と死の境目を強く感じることができると言います。
仏教的な死生観に基づく空間だと思います。
仏教の価値観を色濃く残す日本文化の中では、「死者を送る」という言葉は自然な感覚なのかもしれません。
英語になりにくい言葉である「送り人」は、まったく発想を変えて、departureとタイトルをつけるしかなかったようです。










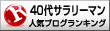

















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます